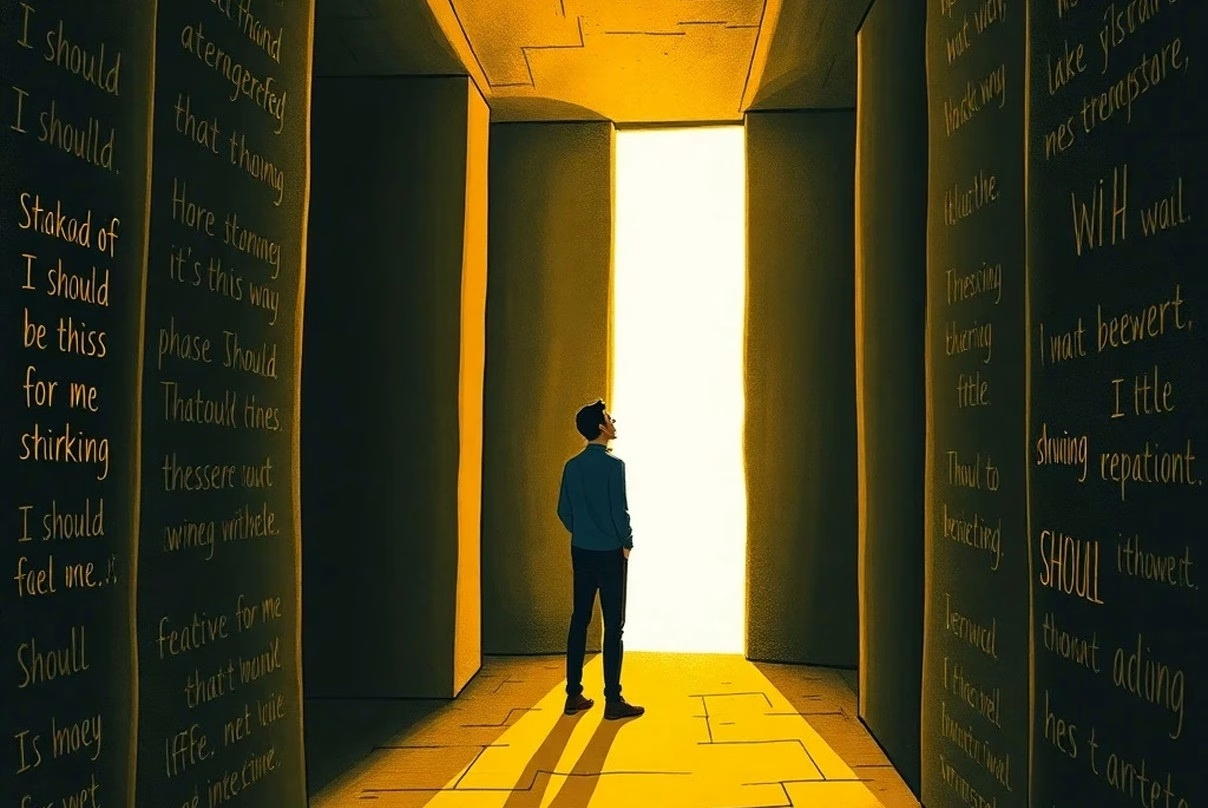「もっと頑張らなきゃ」「みんなはもっと上手くやってるのに」――
そんなふうに、自分にプレッシャーをかけ続けていませんか?
SNSを開けば、完璧なライフスタイルやキャリア、理想的な人間関係を見せつけるような投稿が溢れています。
「こうあるべき」という無数の価値観に触れるたびに、なぜか焦りや劣等感が湧いてくる。そして、気づけば本当の自分が何を大切にしていたのか、何を望んでいたのか、わからなくなってしまう──
そんな経験はありませんか?
これはあなただけの問題ではありません。現代の20〜30代、とくに自己成長を真面目に求める人ほど、自分の価値を「他人の評価」や「社会的な正解」に委ねがちです。
そしてそれが、自分の軸を見失うきっかけになります。自己肯定感が低下すると、私たちは「外の声」を頼りにしてしまうのです。
でも、その声は本当にあなたのためのものですか?
たとえば、「もっと成果を出すべき」「常にポジティブでいるべき」「やりたいことを見つけなければならない」という言葉。これらは一見正しく聞こえますが、実は心を疲弊させる「べき論」の正体かもしれません。
そして、この「べき論」が内なる声をかき消し、あなたの“本当の変化”を遠ざけているとしたら?
なぜ「変わりたい」と思うほど自分を見失いやすいのか、そしてどうすれば他人と比較せずに「本当の自分」とつながり直せるのかを深掘りしていきます。
まずは、あなたの心に問いかけてみてください。
「私はいま、本当に“自分の声”を聞けているだろうか?」
なぜ「変わりたい人」ほど自己肯定感を失いやすいのか?――努力が空回りする心理構造
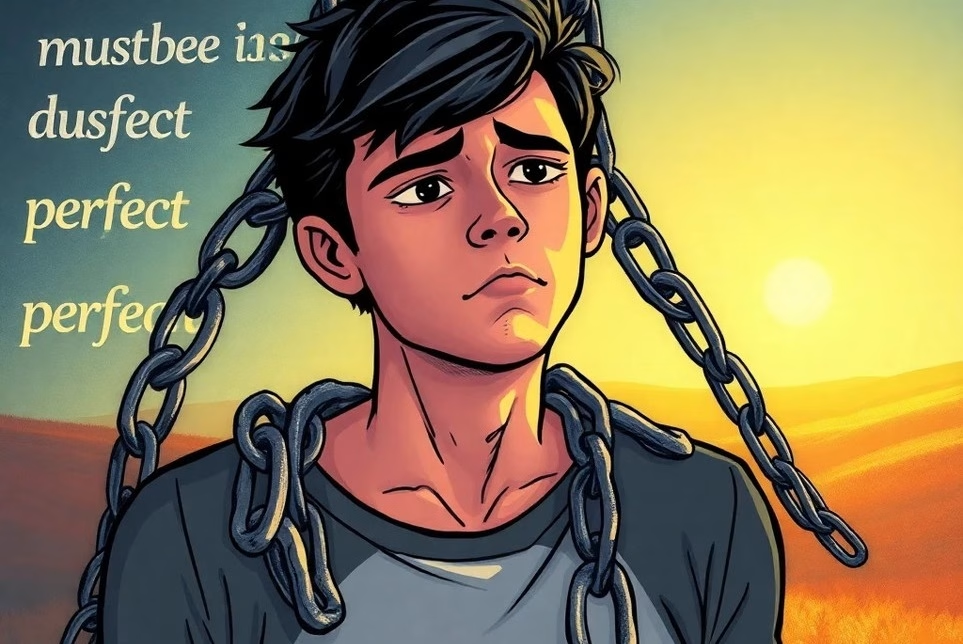
「もっと前向きに生きたい」「今の自分を変えたい」。
そんな思いを抱くことは、決して悪いことではありません。むしろ、成長意欲がある証拠であり、人生を主体的に切り開こうとする健全な動機でもあります。
しかし皮肉なことに、この「変わりたい」という願望が強ければ強いほど、自己肯定感が下がりやすくなる、という現象が数多くの心理学研究で指摘されています。
つまり、「自分をよくしたい」という善意が、「今の自分はダメだ」という否定感と結びつくことで、心のバランスを崩してしまうのです。
なぜ“変わりたい人”ほど自己肯定感を失いやすいのか、その心理構造をひも解きます。
「変わりたい」は、裏を返せば「今の自分は不完全」というメッセージ
自己啓発の本やSNSでは、「理想の自分を手に入れよう」「今のままではダメだ」といった言葉があふれています。
一見、モチベーションを高めてくれるように感じますが、裏を返せば「現状の自分では不十分」「もっと努力しないと価値がない」というメッセージでもあります。
心理学ではこれを「条件付きの自己肯定(conditional self-regard)」と呼びます。
つまり、「〜ができたら」「〜のようになれたら」自分を認めていい、という条件付きの自己評価です。
こうした自己評価のパターンは、達成できた瞬間は一時的に満足感を得られますが、すぐに新たな条件が生まれ、永遠に「今の自分を否定し続けるループ」に陥るのです。
✅ 実際、ハーバード大学の研究(Neff, 2003)によると、「自己肯定感が高い」とされる人の中でも、条件付きの自己肯定を持つ人は、ストレス耐性が低く、ネガティブ感情を長く引きずりやすいことが分かっています。
SNSがつくり出す“比較の罠”と「自分の価値」の不安定化
特に現代の若年層にとって、自分の変化や成長は、SNS上の「他人との比較」の中で測られがちです。
InstagramやX(旧Twitter)、TikTokでは、毎日のように誰かが「理想的なライフスタイル」「成果」「努力の記録」を発信しています。
「自分もああならなければ」と無意識に感じてしまうのは自然な反応ですが、ここには大きな落とし穴があります。
SNSで見かける投稿は、本人が“見せたい自分”だけを切り取った、きわめて編集された情報であり、実際の人間関係や日常の挫折・迷いは映し出されていません。
しかし、その情報と「今の自分」を比べることで、「まだまだだ」「自分は劣っている」という感情が増幅します。
このようにして生じる比較は、「上方比較(upward comparison)」と呼ばれ、特に自己評価を不安定にさせる要因とされています。
✅ カナダのトロント大学の調査(Feinstein et al., 2013)では、SNS利用時間が長い若年層ほど、自分を他者と比べて落ち込む頻度が高く、結果として自己肯定感が低下していくことが報告されています。
このように、SNSは意図せずして「他者との比較ベースでしか自己評価できない」状態をつくり、変わりたいという気持ちを「今の自分ではダメだ」という思い込みへと変質させてしまうのです。
「努力が足りない」のではなく、「評価の軸が外側にある」
自己肯定感が下がると、多くの人は「もっと頑張らなければ」と思います。
さらに自己啓発書を読み、朝活や副業、運動、読書、ポジティブ思考などに取り組もうとします。もちろん、これらは有益な行動ですが、“なぜそれをするのか”の動機が外側にある場合、むしろ心をすり減らす結果になります。
ここで大切なのは、「評価の軸をどこに置いているか」という視点です。
- SNSで「いいね」をもらえるかどうか
- 他人に「すごい」と言われるかどうか
- 書籍やインフルエンサーが勧める方法かどうか
これらはすべて外発的動機です。対して、自分が「こうしたい」と心から思えるかどうかが、内発的動機です。
✅ 自己決定理論(Deci & Ryan, 1985)では、内発的動機に基づいた行動は幸福感・継続力・パフォーマンスすべてにおいて高いという結果が一貫して示されています。
変わりたいと思ったとき、自分にまず問いかけたいのは、「それは本当に、自分が望んでいることなのか?」という問いです。
外側の誰かに認められるためではなく、自分が心地よくあるために変わるのであれば、それは自己肯定感を高める変化となります。
自分を変える第一歩は、「今の自分」にやさしくなること
「変わりたい」という気持ちが強い人ほど、実はすでに多くの努力をしています。それでも報われない、満たされないのは、自分を変えようとする動機や評価の軸が“他人”にあるからです。
自己肯定感とは、「どんな自分でもOK」と思える感覚です。そしてそれは、「今の自分」にやさしくなることからしか始まりません。
「今の私はこうでいい。そのうえで、もう少しこうなれたら嬉しい」
こうした内側からの声に耳を澄ませることができたとき、変わりたいという願いは、“自己否定”ではなく“自己信頼”に支えられたものへと変化します。
その変化こそが、自己肯定感を下げることなく、本当の意味で自分を成長させる力となるのです。
「べき思考」とSNS依存が、あなたの“内発的動機”を奪う――やる気が続かない本当の理由

「もっと頑張るべき」「ちゃんとしなきゃ」「成功しなきゃ」。
これらの“べき思考”に突き動かされて日々を過ごしている人は少なくありません。
努力家で真面目な人ほど、この思考に支配されやすく、それが一見「やる気」のようにも見えるため、自分でも気づかないままストレスや疲労を蓄積していきます。
加えて、SNS上には日々、成功した人の投稿や努力の記録が並び、「私はまだまだ足りない」「もっとやらなくては」と焦りを煽る構造が存在します。このように、べき思考とSNSの情報に囲まれることで、私たちの「内発的動機」は静かに失われていきます。
ここでは、そもそも内発的動機とは何か、べき思考とSNSがどのようにその動機を奪っているのかを明らかにしながら、本当に持続可能なやる気の出し方について考察していきます。
内発的動機とは「自分の内側から湧き上がる動きたさ」
「動機」には大きく分けて2つの種類があります。
1つは、誰かに褒められたい、認められたい、怒られたくない、評価されたいなど、外側の期待に応えるための“外発的動機”。
もう1つは、純粋に「楽しい」「もっと知りたい」「やってみたい」と自分の内側から湧き上がる“内発的動機”です。
内発的動機に基づいた行動は、モチベーションが高く持続性があり、満足感や幸福度も高いとされます。
心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによる自己決定理論(Self-Determination Theory)では、内発的動機は「自律性・有能感・関係性」の3つの心理的欲求が満たされたときに自然と生まれると定義されています。
✅【参考データ】自己決定理論に関する複数のメタ分析(Deci et al., 1999)では、内発的動機が高い人は、外発的動機に依存している人に比べてパフォーマンスが30%高く、継続率は2倍以上であることが明らかになっています。
ところが現代では、この内発的動機が失われやすい状況にあります。その原因のひとつが、「〜すべき」という思考パターン、いわゆる“べき思考”とSNSによる情報過多です。
「やる気が出ない」は、サボりではなく“外発的動機の副作用”
べき思考は、自分を律し、行動の原動力になるように見えます。たとえば、「早起きすべき」「毎日運動すべき」「ポジティブでいるべき」といった内面の声は、自己啓発書やSNS上でもよく見られます。
しかし、べき思考の問題点は、それが“外から与えられた理想像”に自分を当てはめようとする圧力であることです。こうした外発的な基準で自分を動かしていると、次第に「なぜこれをやっているのか分からない」「やる気が湧かない」と感じるようになります。
✅ 米国の心理学誌『Motivation and Emotion』に掲載された研究(Ryan & Deci, 2000)では、べき思考が強い人ほどバーンアウト(燃え尽き)しやすく、内発的動機が低下することが示されています。
つまり、「やる気が出ない」「継続できない」という悩みは、意志の弱さではなく、外発的動機に支配された状態の副作用である可能性が高いのです。
SNSは「内発的動機を感じにくくする装置」になっている
SNSは、人々の感情に瞬時に作用し、行動の動機づけを変えてしまう強力なメディアです。SNSを見ていると、自分の興味やペースとは無関係に、「誰かが成功している」「自己管理できている」「常に成長している」というメッセージが大量に流れてきます。
これに触れているうちに、本来は自分のリズムで進めていたことにまで「評価されるため」という目的が紛れ込んでくるのです。
- 読書をしても「これをXに投稿すべきかな」と考える
- ジムに行っても「映える写真を撮らなきゃ」と意識する
- 朝活しても「#朝活」のハッシュタグを気にしてしまう
これらは一見、自律的な行動に見えますが、動機の中心が「誰かに認められること」に移っているため、内発的な満足感が得にくく、達成しても虚しさが残るのです。
✅ イギリスのバース大学(University of Bath)の研究(2022)によると、SNSを1週間休んだ被験者は、幸福度が25%向上し、不安感が20%以上減少したという結果が報告されています。
→ 情報との“距離”を取ることで、自分の内面に目を向ける余白が生まれ、内発的動機が回復するという実証的な示唆です。
自分に戻るには、「何をしたいか」ではなく「なぜしたいか」を問う
「変わりたい」「前向きに行動したい」と思うとき、最初に確認すべきは「何をするか」ではありません。
最も大切なのは、「なぜ、それをやろうとしているのか?」という問いです。
- 誰かに褒められたいから?
- 自分が心から楽しめるから?
- 義務感から?
- 自分の価値観に合っているから?
この“なぜ”が他人の評価や世間の正解から来ているなら、それは外発的動機です。逆に、自分の感情や身体感覚、心の声に根差しているなら、それは内発的動機です。
「〜すべき」ではなく、「〜したいから、やる」。この構造が整えば、やる気は無理なく湧き上がり、努力は自然に続きます。そして何より、行動したあとの自分に対して満足感を感じることができるのです。
🌱「変わるべき」ではなく、「感じたい自分に近づく」
内発的動機は、評価や義務の外側にある。
SNSやべき思考から距離を置いたその先に、本当に心地よく続けられる行動が待っています。
自分の声と再接続するための内面対話法
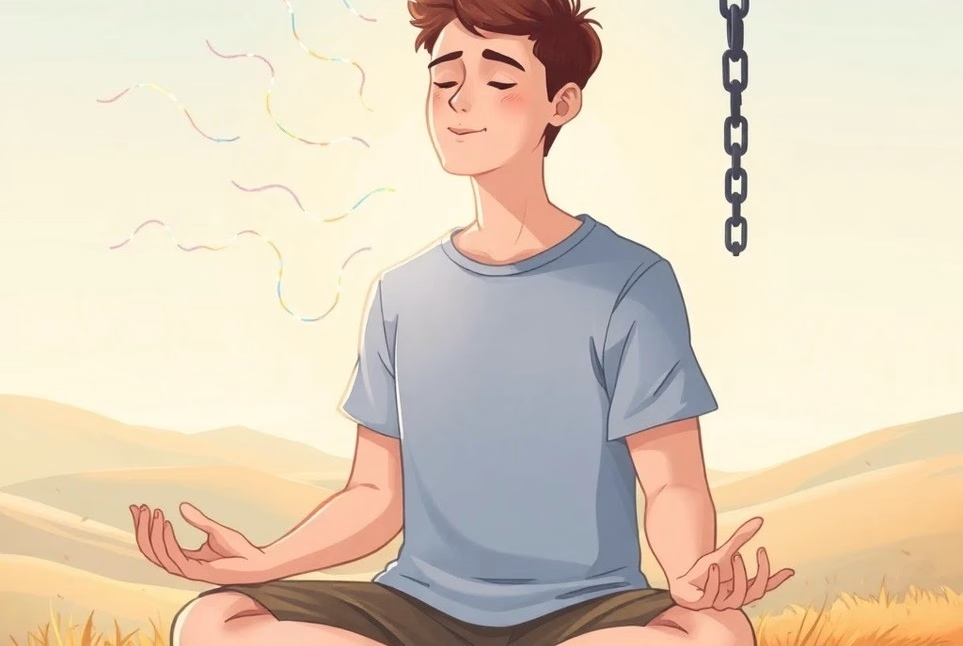
「自分を変えたい」と願う多くの人が見落としがちなのは、変化の起点が外側ではなく“内側”にあるという事実です。
SNSの情報、周囲の期待、そして「こうあるべき」という価値観が渦巻く現代において、本当の自分の声に耳を傾けることは意外なほど難しい作業です。しかし、自分との対話を通じて「内発的動機(自分の心から湧き上がる願いや関心)」に再接続することこそ、持続可能な自己変革への最も確かな道です。
自分の声を取り戻すための「内面対話」の重要性を解説します。
自分の中に“もう一人の自分”をつくる
「内面対話」とは、心の中に“もう一人の自分”をつくり、その自分と語り合うプロセスのことです。これは決して特殊なスキルではなく、人間誰もが本来持っている力です。心理学ではこの行為を「セルフ・リフレクション(自己内省)」と呼び、自己認識力やメンタルヘルスの回復にとって極めて重要であるとされています。
たとえば、米国の心理学者ジョン・D・テフィが提唱した「メタ認知モデル」では、「自分の考えを“俯瞰”して見る力」がストレス耐性や自己調整力と直結しているとされます。これは「自分が今、なぜこう感じているのか」を冷静に捉える力であり、まさに“内面の声を聴く”スキルに他なりません。
1日10分の「意識的な沈黙」が脳に与える効果
現代人の脳は、常に外部刺激にさらされています。スマホの通知、SNSのスクロール、動画の自動再生──こうした刺激に反応しているうちは、自分の内側にアクセスすることは困難です。
そこで有効なのが、1日10分でも「意識的に沈黙する時間」をつくること。これは“マインドフルネス”や“ジャーナリング”のような形式でもよく、自分の中で「今、何を感じているか」「何が本当にしたいのか」をただ観察することに集中します。
カリフォルニア大学の研究によると、1日10分のマインドフルネスを2週間継続した被験者は、自己認識力が平均で33%向上し、ストレス反応が21%軽減したという結果が得られています。
つまり、外の情報をシャットアウトして内側と向き合うだけで、脳のモードが“反応”から“選択”へと切り替わるのです。
書くことが「思考の地図」になる
言語化は、思考の整理に極めて有効です。ジャーナリング(日記やノートに自由に書き出すこと)は、内面対話の基本ツールといえます。とくに「Why」よりも「What」に焦点を当てることが効果的です。
例:
- 「なぜ私はこう思ったのか」→「私は何を感じたのか?」
- 「どうして不安になるのか」→「何が今、不安にさせているのか?」
心理学者のペネベーカーによる実験では、「感情を言語化する」ことによって免疫力が高まり、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が抑制されることが示されています。つまり、心の声を“書いて”明確にすることは、精神面だけでなく身体面にも好影響を与えるのです。
自分の“本音”を引き出す3つの問い
内面対話を深めるために、以下の3つの問いを毎日自分に投げかけてみてください:
- 「今、自分は何を感じているか?」
→感情に“ラベル”を貼ることで、感情の波に呑まれにくくなります。
- 「この感情の奥に、どんな願いがあるか?」
→怒りや焦りの背後には、「認められたい」「安心したい」などの未充足のニーズが潜
んでいます。
- 「本当はどうしたいと思っているのか?」
→社会的な「べき」から離れ、自分の“意志”に触れることができます。
これらの問いは一度に答えを出す必要はありません。繰り返し問い直すことで、少しずつ「自分の本音」に輪郭が浮かび上がってきます。
内面対話がもたらす「他人との比較からの解放」
SNS時代の大きな問題は、「他人の人生」が常に可視化されていることです。つい人と比べて落ち込んだり、焦ったりするのは自然なことですが、それに飲み込まれ続けると「自分の人生の主語」が他人になってしまいます。
内面対話を通じて「自分はどうありたいのか」を問い続けることで、他人のペースや評価から一歩距離を取れるようになります。
これは「自己決定理論」に基づく動機づけの原則であり、内発的動機が高い人ほど幸福度・充実感・パフォーマンスのいずれもが高いことが複数の研究で明らかになっています。
自分の声を聴く習慣が、持続可能な変化をつくる。
変わることに焦る必要はありません。まずは立ち止まり、静かに自分と話す時間をつくる。その積み重ねこそが、周囲に左右されない“軸のある自分”を形づくる最初の一歩となるのです。
自己比較から離れて“ほんとうの変化”を手に入れるには

「他人と比べないことが大切」とはよく言われますが、現代のSNS社会では、それが極めて難しくなっています。
タイムラインには成功や充実をアピールする投稿が並び、それを目にした瞬間、自分の生活が色褪せて見える。
そんな経験を、あなたも一度はしたことがあるのではないでしょうか。
特に「自分を変えたい」「成長したい」という思いが強い人ほど、自己比較の罠にはまりやすく、逆に本来の自分から遠ざかってしまうリスクがあるのです。
SNSは「比較」のスイッチを押す装置
米国の心理学者メリッサ・ハントが2018年に行った研究によれば、SNSの使用時間を1日30分以内に制限したグループは、うつ症状と孤独感が有意に減少しました。
これは、SNSによる“自己比較の機会”を減らした結果であると分析されています。
現代人の多くは、無意識に他人の「成果」や「幸せそうな生活」と自分の現状を比較し、自信を失っているのです。
心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した「社会的比較理論」では、人間は自己評価を行うために、他人と比較する傾向があるとされています。
しかし、重要なのは「比較の対象の選び方」ではなく、「そもそも比較しない視点」を持つことです。
自己比較から抜け出すことは、単なるメンタルケアの話ではなく、“本当の変化”を引き寄せる鍵となります。
自己比較をやめると、成長速度はむしろ上がる
意外に思われるかもしれませんが、「他人と比べることをやめた人」のほうが、自己成長の速度が速いというデータもあります。
日本のリクルートワークス研究所が2022年に発表した報告によると、「自己内省型(自分の価値観や感情に意識を向ける)」の人は、「比較型(他者の評価を基準に行動する)」の人よりも、自己効力感が約1.8倍高いという結果が出ています。
つまり、自分の内面と向き合う習慣こそが、長期的な成長につながるのです。
「このままではダメだ」「もっと頑張らないと」という焦燥感からではなく、「自分がどう在りたいか」「何を心地よく感じるか」といった内発的な動機からの行動は、継続力にも影響します。
心理学では、外発的動機よりも内発的動機のほうがパフォーマンスの質と持続力が高いとされており、その効果は教育やビジネス分野でも広く確認されています。
比較を手放す具体的な方法
では、自己比較をやめるにはどうすればいいのでしょうか? いくつかの効果的な方法がありますが、ここでは3つに絞って紹介します。
- SNSの使用ルールを設ける
1日1回、10分以内など制限を設けることで、無意識の比較を防ぎます。スマホアプリで使用時間を管理するのも有効です。
- 自分専用の「振り返りジャーナル」をつける
1日の終わりに「今日うまくできたこと」「自分がうれしかったこと」を3つ書き出すことで、自分の軸を再確認できます。これは自己肯定感を高め、比較癖を抑える力があります。
- 他人を“比較対象”ではなく“参考モデル”に変える
嫉妬や劣等感を感じたときは、「この人のどこに惹かれているのか?」を言語化してみましょう。そうすることで、感情に流されず、ヒントとして活かす姿勢が育ちます。
「比べない自分」がもたらす深い満足感
最終的なゴールは、他人との比較で生まれる「勝ち負け」ではなく、自分が納得できる「在り方」を見つけることです。
そのために必要なのは、「変わろうとする」ことではなく、「すでにある自分の価値に気づく」ことなのです。
「ほんとうの変化」とは、外見やステータスの変化ではなく、視点が変わることです。
たとえば、同じ日常を送っていても、「誰かと比べて退屈だ」と感じていた毎日が、「今日は自分の心が静かだった」と気づけるようになる。そのような小さな気づきが、実は一番深い変化なのです。
他者との比較をやめ、自分自身との対話を深める。そのプロセスは、地味で、時間がかかるかもしれません。
しかしそれは、あなただけの「確かな軸」をつくるための、確実な一歩です。そしてその軸ができたとき、誰とも比べる必要のない「本当の自分」としての人生が、静かに始まります。
★この記事について:質問と答え
Q1.自己肯定感が低下すると、なぜ「べき思考」や他人の期待に流されやすくなるのですか?
A1.
自己肯定感が低下しているとき、人は「自分には価値がある」と信じられなくなります。その結果、「他人の評価」や「社会の基準」に自分を合わせることで安心感を得ようとし、「こうあるべき」という“べき思考”に依存しやすくなります。とくにSNSでは理想的な生き方が可視化されているため、自分軸を失いやすくなります。
Q2.SNSが内発的動機を奪うとはどういう意味ですか?
A2.
内発的動機とは、自分の価値観や興味から生まれる自発的な行動意欲のことです。しかしSNSでは「いいね」やフォロワー数といった外部評価が行動の動機になりやすく、知らず知らずのうちに“やりたいこと”ではなく“評価されること”を優先してしまいます。これは内発的動機の低下に直結し、行動の本質を見失わせます。
Q3.「本当の変化」を起こすには、まず何を意識すれば良いのでしょうか?
A3.
まず重要なのは、「自己比較」から一歩距離を置き、自分自身の内面と静かに対話する時間をつくることです。呼吸に意識を向けたり、ジャーナリング(書く瞑想)を行うことで、自分の“内なる声”に気づくことができます。そのうえで、自分の中にある「小さな違和感」や「ささやかな願い」に耳を傾けることが、“本当の変化”の出発点になります。
▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。


▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。