40代後半から50代にかけて、なんとなくやる気が出ない、眠りが浅い、朝の目覚めが悪い──
そんな「自分らしくない不調」に悩まされていませんか?「年齢のせいかな」「仕事の疲れがたまっているのかも」と、つい自分を納得させようとしてしまう。
でも、以前はもっとアクティブに過ごせていたはず。そう思いながらも、気づかないうちに心と体が重くなっていく。これは、男性にも訪れる「更年期障害」のサインかもしれません。
「更年期」という言葉を聞くと、多くの人は女性特有のものだと感じるかもしれません。しかし実際には、男性にもホルモンバランスの変化が起こり、さまざまな身体的・精神的な症状が現れることが、医学的にも明らかになっています。日本では「LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症)」とも呼ばれ、近年ようやく社会的な認知が進みつつあります。
でも、なぜか男性の不調には、「気の持ちよう」や「甘え」といった無意識の偏見が根強く残っています。あなたの周りにも、「体がだるい」「イライラする」と言いながらも、それを口に出せず、ただ我慢している人はいないでしょうか?
もしかすると、あなた自身がその状態にあるのかもしれません。
家庭では父親としての役割を担い、職場では責任ある立場を任される。そんなプレッシャーの中で、自分の心と体の異変に耳を傾ける余裕を失っていませんか?
「これって年齢のせい? それとも何かの病気?」
そう感じたとき、誰に相談できますか?
まだまだ知られていない「男性更年期障害」の実態と、なぜ多くの男性がこの問題を“ないこと”にしてしまうのかを紐解いていきます。
自分のために、そして、大切な誰かのために、いま、知っておいてほしい話があります。
男性の更年期障害についての理解

男性更年期障害は、身体的や精神的な症状を引き起こす状態です。
医学的には「男性ホルモン低下症候群」とも呼ばれ、中高年の男性に多く見られます。この障害は、テストステロンという主要な男性ホルモンの減少が原因で、疲れやすさ、抑うつ感、不眠、筋力の低下、性欲の減少など、さまざまな影響があります。
女性の更年期障害に比べてあまり注目されていませんでしたが、20世紀に入ってからようやく科学的に研究されるようになりました。
この障害の歴史を考えると、社会や文化の変化とともに、医療分野の進歩が男性更年期障害の認識に影響を与えてきたことがわかります。
古代から中世における男性更年期障害の認識
古代ギリシャやローマでは、男性が年を重ねることは知恵や成熟の象徴とされていました。身体的な衰えはほとんど注目されず、男性の役割は戦士や指導者、哲学者としての活動が中心でした。身体の変化が生活や社会的地位に与える影響は軽視されていたのです。
一方で、中国やインドの伝統医学では、男性の健康とホルモンに関するエネルギーの流れを関連付ける理論が発展していました。
例え挙げると、中国の「陰陽五行説」では、男性のエネルギーが年齢とともに低下する現象が記録されており、これを補うための薬草療法や針灸が推奨されていました。
近代における医療の進歩と男性ホルモンの発見
近代に入ると、科学技術の進展により人体についての研究が進みました。特に19世紀から20世紀初頭にかけて、ホルモンという概念が登場し、内分泌学の分野が急速に発展しました。1935年にはドイツの科学者アドルフ・ブテンandtがテストステロンを初めて分離し、男性ホルモンの研究における進展が見られました。この発見により、テストステロンが男性の性機能や筋力、骨密度、心理的安定に関与していることが明らかになり、男性の加齢に伴うホルモン変化に対する関心が高まりました。
1940年代から50年代にかけては、欧米でホルモン補充療法の研究が進められ、テストステロンが健康維持に果たす役割が次第に明らかになっていきました。しかし、この時期には男性更年期障害という概念自体はあまり広まっておらず、老化現象の一部として扱われていました。
20世紀後半から現代にかけての認識の変化
1970年代に入ると、医療技術の進歩によりホルモンレベルの測定が可能になりました。この技術革新によって、男性の健康問題とテストステロンの関係が明らかにされ始めました。
また、同時期に女性の更年期障害が社会的に認識されるようになり、男性の同様の症状に対する関心も高まりました。
2000年代には、世界保健機関(WHO)を含む国際的な医療機関が男性更年期障害を正式に認め、その症状や診断基準が広く共有されるようになりました。
具体的には、血中のテストステロン値が一定の基準を下回ることと、上記のような症状が現れることが診断の基準とされています。これにより、多くの中高年男性が体調不良の原因を特定し、治療を受けられるようになりました。
男性更年期障害の影響を受ける年齢
データによると、男性更年期障害は40代後半から60代にかけて急増し、50歳以上の男性の約30%が何らかの形でこの障害の影響を受けているとされています(2020年、アメリカ内分泌学会の報告)。
また、ホルモン補充療法を受けた患者の約70%が症状の改善を実感したという研究結果も報告されています(2015年、イギリス・キングスカレッジの研究)。
ただし、テストステロン補充療法にはリスクも伴います。特に心血管疾患のリスク増加や前立腺癌の進行可能性が指摘されており、安全性を確保するためには慎重な治療が必要です。
男性更年期障害は、単なる健康問題にとどまらず、加齢に対する社会的・文化的な認識の変化を象徴しています。
この障害に対する歴史的な視点を理解することで、現在の医療や社会のアプローチがどのように形成されてきたのかを知る手がかりが得られます。
また、適切な治療やサポートを提供することで、男性が健康で充実した中年期を送る基盤を築くことができるでしょう。男性が健康で充実した中年期を送るための基盤を築くことが可能となるでしょう。
月の満ち欠けとホルモンの関係について

月の満ち欠けが人間の体に与える影響は、古代からの伝承や文化的信仰の中で語られてきました。
最近では、科学的にもこのテーマが議論されています。特に「月が人間のホルモン分泌に影響を与える可能性」という仮説は、現代の科学でも完全には否定されていない未知の領域です。
この視点を深掘りし、男性更年期障害やホルモンの低下との関連性を考えることで、月が与える影響について新たな理解が得られるかもしれません。
古代からの月と人間の関係
古代エジプト、ギリシャ、ローマ、中国、インドなどの文明では、月の周期が農業や医療、宗教儀式において重要な役割を果たしていました。特に、女性の月経周期が平均28日であり、月の満ち欠けの周期(約29.5日)と近いことから、古代の人々は月が人体に影響を与えていると考えていました。
中国の伝統医学では、月の満ち欠けが人体の「気」の流れに影響を与えるとされ、月の位相に合わせて薬草の使用や治療法が調整されてきました。
また、古代ギリシャの医学者ヒポクラテスは、月齢が病気の進行や治療の速度に影響を与える可能性を提唱しました。このような古い考えは、現代の科学的研究の基礎を築いていると言えます。
現代の科学研究と月の影響
現代の科学研究でも、月が人体に影響を与える可能性が議論されています。特に、月齢が睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌に影響するという仮説が注目されています。
2013年にスイスのバーゼル大学で行われた研究では、満月に近い夜にメラトニンの分泌が低下する可能性が示されました。この研究では、被験者の睡眠パターンを調べた結果、満月の夜には平均して入眠が5分以上遅れ、睡眠時間が20分以上短くなることが確認されました。さらに、被験者の睡眠の深さも減少していたという報告があります。
他の研究では、月齢が自律神経系に影響を与える可能性も示されています。自律神経系は心拍数や血圧、消化活動を調整する役割があり、これらはホルモン分泌にも影響を及ぼすと考えられています。
これらの研究はまだ発展途上であり、サンプルサイズの限界や因果関係の証明不足が課題となっていますが、月がホルモン分泌に何らかの影響を与える可能性は完全には否定されていません。
月の満ち欠けと男性更年期障害の関連性
月の影響が男性更年期障害にどのように関わるのかについては、直接的な科学的証拠はまだありません。しかし、いくつかの仮説を基に可能性を探ることができます。
たとえば、月齢がメラトニン分泌に影響を与えることで、間接的にテストステロンの分泌が変動する可能性があります。メラトニンは体内のホルモンバランスを調整する重要な役割を持っているためです。
テストステロンの分泌は睡眠の質や深さに密接に関連しており、十分な深い睡眠が確保されないとホルモン分泌が乱れる可能性があります。
もし満月が男性の睡眠パターンに影響を与えるなら、それがテストステロンの分泌に影響を与え、結果として男性更年期障害の症状を悪化させる可能性も考えられます。
また、心理的な要因も無視できません。月齢が睡眠や感情に影響を与える場合、男性更年期障害における抑うつや不安感の増加が月と関連している可能性も検討する価値があります。
月とホルモンの因果関係に関するデータ
現在のところ、月とホルモンの直接的な因果関係を示すデータは十分ではありません。
しかし、睡眠障害や精神的な変動がホルモンバランスに影響を与えるという知見から、間接的な関連性を探る研究が期待されています。
2020年のデータによると、テストステロン分泌量は男性が40歳を過ぎると年間1%ずつ減少すると報告されています。この減少が睡眠障害やストレスによって促進される可能性を考えると、月齢がこれらの要因に影響を与えるかどうかを調査することは、男性更年期障害研究の新たな方向性となるでしょう。
また、ビッグデータやAIを活用して、月齢と男性ホルモン分泌の関連を大規模に解析する試みも進められる可能性があります。
このようなアプローチは、未知の関連性を解明し、月が人体に与える影響についての科学的理解を深める助けとなるでしょう。
月とホルモン分泌の関係は、古代からの伝承と現代科学が交わる興味深いテーマです。
月の満ち欠けが男性更年期障害に直接的または間接的に影響を与える可能性は、今後の研究によって解明される余地があります。この未知の領域を探求することで、男性更年期障害の治療や予防に新たな道が開けるかもしれません。
男性更年期障害に対する社会的な認識の不足
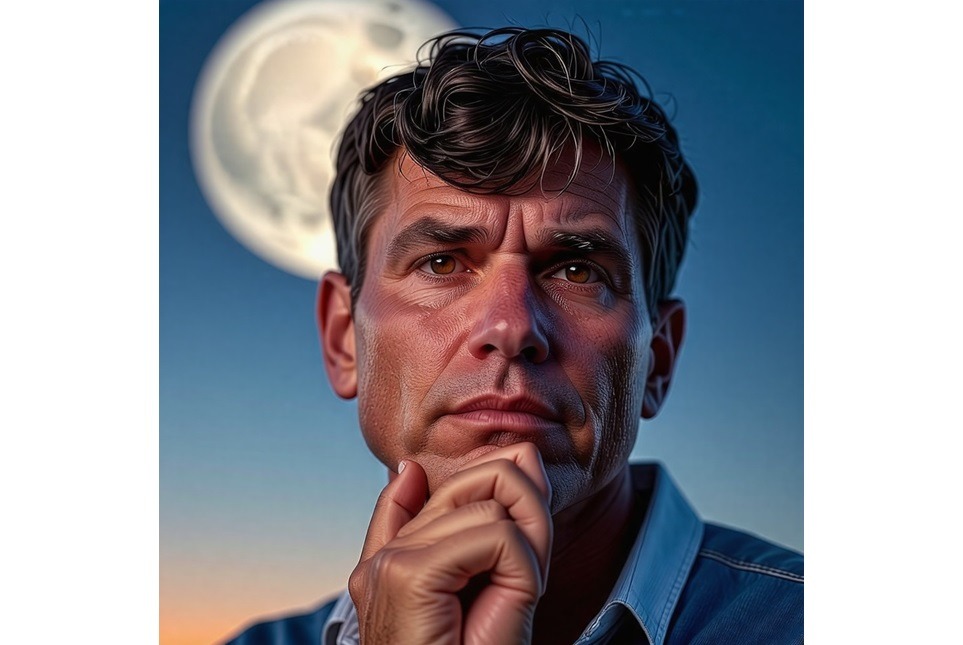
男性更年期障害(LOH: Late-Onset Hypogonadism)は、40代以降の男性に見られるホルモンバランスの変化に起因する健康問題です。
この状態は身体的や精神的な症状を引き起こします。主な症状には、抑うつや不安、疲れやすさ、性欲の低下、筋力の低下、不眠などがあります。
しかし、社会における認識や理解が不足しているため、多くの男性が適切なサポートや治療を受けられない状況が続いています。この問題は、個人の生活の質だけでなく、家庭や職場、社会全体にも影響を及ぼしています。
男性更年期障害が認識されにくい理由
男性更年期障害が社会であまり知られていない背景には、いくつかの要因があります。
- 健康問題としての認知度の低さ 女性の更年期障害は広く知られており、支援策も整っていますが、男性の更年期障害については認識が低いままです。この差は、女性の月経や閉経が生理的に明確であるのに対し、男性更年期障害の症状が多様で、加齢の変化として捉えられがちな点から来ています。また、男性のテストステロンの低下は徐々に進むため、本人も周囲もその問題に気づきにくいのです。
- 社会的な偏見 「男性は強くあるべき」「感情を表に出さないべき」という考え方が根強い社会では、精神的な不調や体調の変化を相談することが難しくなります。特に、日本のような伝統的な社会では、「老化に伴う症状は仕方がない」という考えが男性自身にも強く浸透しており、医療機関を受診する動機が欠けていることが多いです。
- 医療現場での対応不足 男性更年期障害に対する診療体制は、女性に比べてまだ発展途上です。専門的な診断や治療を行う医師が少ない地域もあり、医療サービスの格差が問題となっています。また、男性更年期障害の症状が他の病気と重なることがあるため、誤診や未診断のまま放置されるケースも少なくありません。
男性更年期障害の認識不足がもたらす影響
- 個人の生活の質への影響
2020年の研究によると、男性更年期障害の典型的な症状である抑うつや疲労感を抱える男性は、日常生活での生産性が平均で25%低下することが示されています。また、性欲の低下や感情の不安定さは、配偶者や家族との関係悪化を引き起こしやすく、これがさらなる精神的な負担を生む悪循環に繋がることがあります。 - 職場や社会全体への影響
40代から60代の男性に多く見られるため、職場でのパフォーマンス低下や長期休職、最悪の場合は離職につながることもあります。厚生労働省が2021年に発表したデータでは、中高年の男性の約15%が何らかの健康問題で労働時間を減らしていると報告されています。そのうち、男性更年期障害に起因する可能性のあるものは20%に上ると推測されています。 - 経済的負担
男性更年期障害が未診断または未治療の場合、症状が慢性化し、より深刻な病気(心疾患やメンタルヘルスの悪化など)を引き起こすリスクが高まります。これにより、結果的に医療費が増加し、個人の負担だけでなく医療保険制度全体への圧力にもなります。
解決へのアプローチ
男性更年期障害に対する社会的認識を向上させるためには、以下のような取り組みが必要です。
- 啓発活動の強化
公共機関や民間企業が連携し、男性更年期障害に関する正しい情報を広めるキャンペーンを実施することが重要です。特に、中高年男性がアクセスしやすいメディア(テレビ、SNS、職場内の研修など)を活用し、相談しやすい環境を整えることが求められます。 - 医療体制の整備
男性更年期障害を専門的に診断・治療できる医療機関や医師を増やす必要があります。また、一般診療においても、男性更年期障害の症状を見逃さないための教育を医療従事者に行うべきです。 - 社会的支援の充実
職場での健康管理制度やカウンセリングサービスを拡充し、男性更年期障害に悩む社員が安心して相談できる仕組みを作ることが重要です。これにより、早期発見と治療が促進され、労働生産性の向上にも繋がるでしょう。
早期介入がもたらす改善の可能性
イギリスのNHS(国民保健サービス)による調査では、男性更年期障害に対して早期介入が行われた場合、患者の75%以上が症状の改善を報告しています。
また、治療を受けた男性のうち60%が職場での生産性向上を実感したとされています。これらのデータは、適切な支援体制の整備が個人だけでなく社会全体にも利益をもたらすことを示唆しています。
男性更年期障害は、個人の健康問題にとどまらず、家庭や社会全体に影響を及ぼす重要な課題です。
その認識を高め、適切な医療やサポートを提供することで、男性が健康で充実した中高年期を送るための基盤を築くことができるでしょう。
また、認識向上に向けた取り組みは、ジェンダーバランスの観点からも、男性の健康問題への関心を高める良い機会となります。
★この記事について:質問と答え
Q1.男性更年期障害とは何ですか?女性の更年期とどう違うのですか?
A:
男性更年期障害は、加齢に伴って男性ホルモン(主にテストステロン)の分泌が減少することで起こる心身の不調のことです。医学的には「LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症)」と呼ばれます。女性の更年期がエストロゲンの急激な低下によって起こるのに対し、男性の場合はテストステロンのゆるやかな低下が背景にあります。症状も多様で、「だるさ」「不眠」「イライラ」「性欲の低下」など、心身両面にわたります。
Q2.男性更年期障害の症状はどのように現れるのですか?ストレスとの違いは?
A:
男性更年期障害の代表的な症状には、疲労感、集中力の低下、抑うつ、不眠、性機能の低下、筋力の衰えなどがあります。一見するとストレスや仕事疲れにも見えますが、原因がホルモンバランスの乱れにある場合、休養や気合だけでは改善しません。血中のテストステロン値を調べることで診断されるため、医療機関での検査が有効です。
Q3.男性更年期障害はどう対処すればいいの?治療は可能ですか?
A:
男性更年期障害は治療可能です。治療にはホルモン補充療法(テストステロン投与)や生活習慣の見直し、カウンセリングが含まれます。まずは内科や泌尿器科など専門医を受診し、血液検査によってホルモン値を確認することが重要です。また、家族や職場の理解も回復の支えとなります。放置せず、「年齢のせい」と決めつけずに専門的な対応を考えましょう。
▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。


▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。





