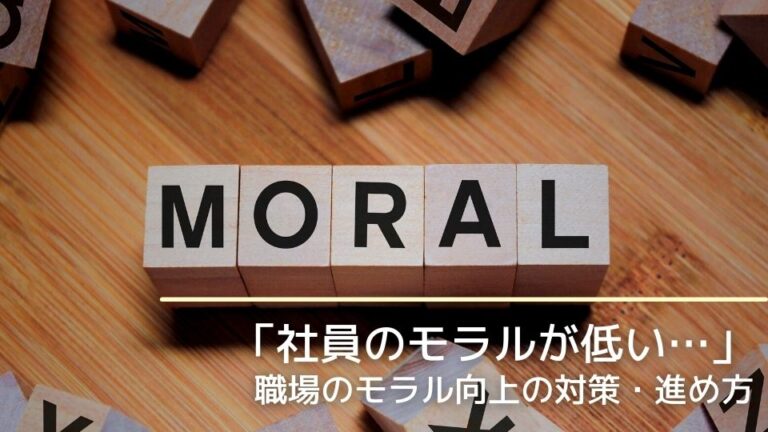「ルールを守るのがバカらしい」「真面目にやってる人だけが損している」――そんなふうに感じたことはありませんか?
たとえば、時間通りに出社しているのに、遅れてくる人が当たり前のように許されている。提出期限を守っても、ギリギリまで出さない人と同じ評価でした。
黙ってルールを守っている側が損をして、要領よく立ち回る人が得をする――そんな不公平な現実に、もやもやしたことはないでしょうか。
日本の職場では、表向きは「ルールを守ることが大事」とされていますが、実際には「空気を読む」「波風を立てない」ことが優先される場面も少なくありません。
すると、ルールを厳密に守る人ほど疎まれたり、「あの人、融通が利かない」と言われてしまうことも。
では、どうすれば“ルールを守るのがバカらしい”という空気を変えられるのでしょうか?「みんながやっていないから自分もしない」「注意するのが面倒くさい」「上が何も言わないから黙っておく」――そんな日常的な小さな判断が、職場の“空気”や“文化”をかたちづくっています。
「ルールって、誰のためにあるんだろう?」「守る価値があると思えるには、何が必要なんだろう?」
そう感じたことはないでしょうか。
「ルールを守るのが当たり前」とされる職場文化をどうつくるか、なぜ空気が人の行動を左右するのか、そして一人ひとりにできる小さな行動の力について解説していきます。
真面目に頑張る人が報われる、納得できるルールのある職場にしたいと願うすべての人へ――。
ルールは「守ること」より「どう扱うか」が重要 ― 「納得感」が文化を変えるカギ

「ルールを守ることが正しい」と頭で分かっていても、実際の現場でルールが形骸化していたり、誰も守っていなかったりすると、「守ること」に意味を見出せなくなってしまうのは自然な反応です。
しかし、本当に重要なのは「そのルールがどう扱われているか」という点です。ルールの運用方法や共有の仕方によって、組織の空気や一人ひとりの行動は大きく変わります。
「守られないルール」は、“意識の問題”ではなく“仕組みの問題”
日本のある大手企業で、社員約1,000人を対象に行われた調査によれば、「社内ルールを守らない理由」のトップは「ルールの意図が分からない」(41.7%)でした(※HR総研調査, 2022年)。
これは、「ルールに反対している」わけではなく、「なぜそれが必要なのか理解できていない」状態を意味します。
つまり、ルールを守らないことの多くは、モラルや意識の低さではなく、情報共有の不全と納得の欠如によって引き起こされています。
この調査結果が示す通り、「守れ」と強制する前に、「なぜそのルールがあるのか」「それによって誰がどう得をするのか」といった価値の意味付けと丁寧な運用こそが、実はもっとも効果的な「ルール遵守の促進策」なのです。
「納得感」があるルールは自律的に守られる
たとえば、ある中堅IT企業では「業務開始前の朝礼参加」が形式的になっており、出席率が6割を切っていました。しかし、このルールを見直すにあたり、以下のような運用変更が行われました。
- 目的を明確化:「チーム間の状況共有と業務トラブルの早期把握のため」
- 内容を短縮:5分以内、個人の発言義務なし
- 参加形式:出社でもリモートでもOK
- フィードバック制度:月1回、参加者の意見を反映する機会を設置
この施策後、朝礼の出席率は85%以上に上昇し、加えてチーム内の業務ミス報告が30%減少しました。
この例のように、「やらされ感」のあるルールでも、「自分たちの仕事を助けてくれる仕組み」に変換されれば、納得感のもとに自律的に守られるようになります。
運用と共有が“ルールの空気”を決める
職場におけるルールの価値は、その設計よりも運用における「扱い方」に左右されます。特に重要なのは次の3点です。
- 意図と背景の説明があるか
- 「目的は何か」「誰のためか」が共有されているルールは受け入れられやすい。
- 説明がないと、「一部の人間の都合で決まった」と受け取られやすい。
- 例外の扱いが一貫しているか
- 同じ行動でも人によって注意されたりされなかったりすると、空気が濁る。
- 例外対応こそ「空気」の正体であり、ルールの信頼性を左右する。
- “小さな成功体験”があるか
- 守った結果、チームがうまく回った、トラブルが減った、などの体感があると、人は納得して行動を継続する。
- 成功事例の可視化は、ルールを空気に浸透させる有効な手段。
ルールが空文化する最大の要因は、こうした運用の曖昧さにあります。誰もが納得できるよう、一貫性・目的の共有・結果のフィードバックという3点を徹底することが、空気を変える鍵になります。
数字で見る「納得感のあるルール」の効果
- 納得できるルールは3倍守られやすい:経済産業省の報告書(2021)では、従業員がルールの目的を理解している企業の方が、コンプライアンス違反の発生率が約1/3に低下したと報告されています。
- リーダーが説明責任を果たしている職場では、チームの規律遵守度が平均27%向上(産業能率大学・組織心理学研究 2023年)。
このように、ルールそのものを見直すのではなく、「どう共有されているか」「どう受け止められているか」を改善するだけでも、大きな行動変化が生まれるのです。
ルールは「空気」によって機能する、だからこそ扱い方を変えよう
ルールは、単に「守る・守らない」という2択で測れるものではありません。その真価は、どう理解され、どう受け入れられ、どう実行されているかという「扱い方」にこそあります。
その扱い方を決めるのは、制度や命令ではなく、「空気」です。
そして空気をつくるのは、日々の小さなコミュニケーションと態度です。
- ルールを守る理由を言葉にする
- 他者の遵守をさりげなく評価する
- ルールの背景を繰り返し共有する
こうした行動が、空気を変え、ルールを機能させる文化をつくっていきます。
つまり、ルールを守らせるよりも、ルールを育てる組織文化が重要なのです。
あなたが感じている違和感は、ルールの“内容”よりも、“運用の質”に起因しているかもしれません。
その運用を少しずつ変えていくことが、空気を変え、ルールが生きる職場への第一歩になるのです。
ルールを守る意味がわからない ― その“違和感”はむしろ職場環境を見抜く正常な感覚

「自分だけがルールを守ってバカを見るのでは?」
「他の人は守っていないのに、なぜ私だけが…?」
――このような疑問や不満を抱いたことがある人は決して少数派ではありません。むしろ、そうした“違和感”こそが正常な感覚であり、職場環境や組織文化の歪みに気づく重要なセンサーです。
これは単なる愚痴や被害者意識ではなく、組織行動論や心理学的にも根拠のある反応であり、放置されると職場の生産性や信頼関係にも深刻な悪影響を及ぼすことがわかっています。
「みんな守ってないのに、なぜ自分だけ?」と感じる心理は自然なもの
ルールに対する“違和感”は、多くの場合、ルールそのものではなく、その「運用の不公平さ」に由来しています。
たとえば以下のような状況です:
- ルールを破ってもおとがめなしの人がいる
- 上司や一部の社員だけがルールの例外扱いを受けている
- 説明なく新しいルールが突然導入される
- ルールを守っても評価されず、むしろ時間的・心理的に損をしているように感じる
これらは全て、ルールの「公正さ」や「納得感」が欠けた状態であり、その場にいる人が「なぜ自分だけが律儀に守らなければならないのか」と感じて当然の環境です。
実際、ある調査(日本能率協会マネジメントセンター、2023年)によれば、20〜50代のビジネスパーソン約1,200人のうち、58.2%が「ルールの運用に不公平を感じた経験がある」と回答しています。
さらに、不公平を感じた人の約65%が「ルール自体への不信感を抱いた」とも回答しており、ルールの信頼性は“内容”よりも“運用”で決まることがうかがえます。
「違和感がある=悪い社員」ではない。むしろ健全な組織感覚の持ち主
ルールに対する違和感を覚える人にありがちな悩みは、「真面目すぎる自分が悪いのかもしれない」「周囲に合わせて黙っていた方がいいのかも」という内向きな思考です。
しかし、違和感は組織文化を改善する重要な“初期症状”です。心理学では、これを「認知的不協和」と呼びます。自分の信念(ルールを守るべき)と、周囲の現実(誰も守っていない)が矛盾することで、強い不快感を覚えるという現象です。
この状態を放置すると、次の2つのいずれかに進みます:
- 自分もルールを破るようになり、罪悪感を抱えながら行動するようになる
- 「正しい行動をしているのに報われない」という無力感から、モチベーションが低下し、組織への信頼を失う
つまり、“ルールに疑問を抱く健全な感覚”が、放置されることで自己効力感と組織全体のパフォーマンスを下げる危険性があるのです。
「誰も守っていないから守らなくていい」は危険な判断
では、違和感を感じたときにどう行動すべきなのでしょうか?
ありがちな対処法が「周囲に合わせて自分もルールを軽視する」ことですが、これは一時的に楽に感じられても、長期的には次のようなリスクを孕みます。
- 組織全体の信頼感・一体感の低下
- 評価の透明性が失われ、実力主義が形骸化する
- ルールを守っていた人ほど早く辞めてしまう「真面目な人から辞める現象」が起こる
実際、経済産業省の2021年の企業調査では、コンプライアンス違反が頻発する企業では、離職率が平均より20%以上高い傾向があると報告されています。これは「守る人が報われない環境」が、組織から人材を流出させている証拠です。
「意味のないルール」と「意味が伝わっていないルール」は別物
もうひとつ、重要な視点があります。それは、ルールの意図や目的が共有されていない場合、人はそれを「意味のないルール」と誤解してしまうという点です。
たとえば、以下のようなルールはどうでしょうか?
- 「社内では挨拶を徹底しましょう」
- 「業務日報を毎日提出しましょう」
- 「月末は全員で掃除をしましょう」
これらは一見、前時代的で形骸化したルールに見えるかもしれませんが、その目的(コミュニケーション活性化、業務改善の可視化、衛生意識の共有)を明確にすれば、納得感のある行動に変わる可能性があります。
目的が共有されていない状態では、ルールは単なる「義務」や「面倒なもの」に見えてしまうのです。
実際、日報を「作業報告」ではなく「気づき共有ツール」として活用した企業では、社員の日報提出率が32%から91%に跳ね上がったという事例もあります(東京のベンチャー企業A社、2022年社内データより)。
違和感の正体に気づいたときが、職場の空気を変えるチャンス
「なんで自分だけが…」と感じる違和感を、「私の感覚がおかしいのかも」と自己否定する必要はありません。むしろ、それは職場の空気に歪みが生じているサインであり、放置することであなたのモチベーションも職場の信頼も蝕まれていきます。
違和感を感じたら、以下の行動を検討してみてください:
- そのルールの目的や背景を周囲に確認する(直接でなくてもOK)
- 自分なりに「このルールの意味」を整理してみる
- 周囲と共有できそうな納得感のある説明があれば、さりげなく言語化してみる
あなたの「違和感」は、ルールを改善し、職場の空気を変えるきっかけになります。
問題は「守るか、破るか」ではなく、「この違和感にどう向き合うか」にこそあるのです。
“空気”がルールを決める:職場の社会的規範の仕組みを読み解く

ルールがあるのに誰も守らない。逆に、ルールに明記されていないのに、なぜか全員が従っている行動がある。こうした現象の背後には、「空気」として共有されている社会的規範が存在します。
これは法律や明文化されたルールとは違い、「みんながそうしているから、そうするのが当然」という、無意識の行動ルールです。
この“空気”こそが、職場でのルール遵守や逸脱の実態を左右する最も強力な要因のひとつであり、組織文化の本質ともいえるものです。
人はルールではなく「周囲の行動」に従う
社会心理学では、個人の行動は意志やモラルではなく、周囲の人の行動パターン(=規範)に大きく影響されることが分かっています。これは「社会的証明(Social Proof)」と呼ばれる現象です。
たとえば、カリフォルニア大学の研究(Cialdini, 2003)では、ホテルのバスルームに以下の2種類の表示を設置し、タオルの再利用率を比較しました。
- A:「地球環境のため、タオルの再利用にご協力ください」
- B:「このホテルの宿泊者の75%がタオルを再利用しています」
結果、Bの文言を掲示した部屋では再利用率が26%高くなったのです。
このように、人は「何が正しいか」よりも「みんながどうしているか」に強く引きずられる傾向があります。
この心理は職場でも同じであり、ルールの文面よりもそのルールに周囲がどう対応しているかの方が、行動に与える影響力は圧倒的に大きいのです。
職場における「空気のルール」が個人行動を支配するメカニズム
職場での“空気”は、以下のような形で私たちの行動を無意識に縛っています:
- 始業時間ギリギリに出社するのが常態化している職場では、早く来ることが「浮いた行動」になる
- 会議中に積極的に発言しない空気があると、誰も話さなくなる
- 昼休憩を取らないのが暗黙のルールの職場では、休憩を取ることに罪悪感が生まれる
これはすべて、「みんながしているから、そうしないと居心地が悪い」「逆に正しいことでも、空気を読まないと評価が下がるかもしれない」という同調圧力によって生じます。
このようにして、「本来あるべきルール」ではなく、「空気によって生まれた裏ルール(非公式規範)」が力を持ち始め、やがてそれが“事実上のルール”として定着してしまうのです。
事例:ルール違反が黙認される“空気”が招く崩壊
ある国内製造業の中堅企業(従業員300人規模)では、「就業中の私用スマホ使用禁止」という明確な社内ルールがありました。ところが現場では、上司自身が業務中に頻繁にスマホをチェックしており、結果として約8割の社員がこのルールを実質無視しているという実態が明らかになりました。
さらにこの企業では、守らないことに対して注意する文化もなく、「言ったところで変わらない」「自分だけが損をする」という諦めの空気が支配的でした。その結果、
- 若手社員の定着率が年間で40%を下回る
- 生産効率に関わるヒューマンエラーが前年より27%増加
- 社員のエンゲージメントスコアが業界平均より21ポイント低い
という深刻な結果を招いていました。
この事例は、「空気」がいかに公式ルールの実効性を奪い、組織の信頼と効率を蝕むかを端的に示しています。
空気を変えるのは「個人の小さな行動」から始まる
では、どうすればこのような空気による悪循環を断ち切れるのでしょうか。
答えは、「空気の発生源は、特定の制度ではなく、人々の繰り返される行動そのもの」であるという点にあります。
つまり、
- ルールを守っている人を評価する
- 違反に対して攻撃的ではなく、事実ベースでやんわり指摘する
- ルールの背景や目的を何度でも丁寧に共有する
――といった個人のさりげない言動が、「空気の圧力」を少しずつ逆方向に動かしていきます。
また、Google社の「プロジェクト・アリストテレス」(2015年)では、「効果的なチーム」に共通する要素のひとつに“心理的安全性”が挙げられました。これもまさに、空気による無言の支配を解きほぐす文化が、成果や創造性に直結することを示す実証データです。
組織文化は「空気」がつくる、“空気”は行動がつくる
ルールを守らせるために重要なのは、「制度を厳しくする」ことではなく、「空気を変えること」です。
そして空気は、一人ひとりの小さな行動の連鎖によって自然と形成されていくものです。
- 1人がルールを守る → それを評価する人がいる → 守る人が増える
- 守らない人にやさしく指摘する → 「それを言っていい空気」が生まれる
この循環が進めば、「守るのが当たり前」という空気=社会的規範が根付き、明文化されたルールよりも強い力を持つようになります。
つまり、職場におけるルールの実効性は、「空気」によって決まり、空気は個人の行動と関係性から生まれる。
これが、職場の社会的規範の本質であり、ルール遵守文化を根づかせるための最も現実的で確実なアプローチです。
不公平感をなくすには?:「納得できるルール」を“価値”に変える方法

職場のルールに不満や反発が生じる最大の原因は、「守ること自体が損だと感じる」ことにあります。つまり、ルールそのものの存在よりも、「それをなぜ守らなければならないのか」という納得感の欠如が問題なのです。
ルールを単なる命令や押しつけとして受け止めるのではなく、「自分や組織にとって意味がある」「価値あるものだ」と感じられれば、人は自発的に従うようになります。不公平感の解消には、「ルール=価値」の転換が不可欠なのです。
「納得感」のないルールは守られない
日本能率協会の調査(2023年、企業勤務者1,000人対象)によると、「職場ルールに不満がある」と回答した人のうち、67.4%が「そのルールの目的が不明確」と感じており、61.2%が「組織や個人にとって意味がないと感じる」と答えています。
この結果から分かるのは、ルールそのものの厳しさや数ではなく、「意味や目的への納得度」が遵守の最大の分岐点だということです。
例えば、
- 「毎日の日報提出」→「上司の監視が目的」と思えば苦痛だが、「自分の成長を可視化できる」と感じられれば価値になる
- 「会議は原則出席」→「無意味な時間の浪費」と思えば不満だが、「自分の意見が反映される場」と思えれば積極的に参加できる
このように、ルールに「主観的な価値」を見出せるかどうかが、実際の行動に大きな影響を与えるのです。
ルールの背景と意義を「つなげる」だけで反発は減る
人がルールに納得するためには、「何のためにこのルールがあるのか」と「自分にとってどんな意味があるのか」を理解する必要があります。
それをうまく“つなげる”ことができれば、反発は大きく減ります。
たとえば、あるIT企業では「PCの自動ロックを5分でかける」というルールに対して、「頻繁にロックされて業務効率が悪い」と不満の声が続出していました。
しかしその後、社内で起こった情報漏洩未遂事件を機に、「このルールが顧客データを守るためである」ことが説明された結果、遵守率が54%から91%へと急上昇。この背景には、「面倒だけど、自分たちの信用や仕事を守る手段だ」との納得感が浸透したことがあります。
つまり、ルールに対する不満の多くは、「内容そのもの」ではなく「伝え方」によって生まれている。情報が不足し、文脈が欠けているルールほど、不公平感が強くなるのです。
「みんなが守っている」ことは納得の材料になる
社会心理学では、人は「他人がやっていること=正しい」と無意識に判断する傾向があることが知られています(これを「規範的影響」と言います)。
つまり、「自分だけが守っている」と感じるときほど、ルールは苦痛になりますが、「みんなが守っている」と感じるときほど、その行動に対する納得感や意義は増すのです。
ある金融機関では、毎朝の朝礼参加が義務化されていたが、出席率が60%を切る状態が続いていました。そこで「出席率をリアルタイムで全員に可視化」し、部門別に推移を共有するようにしたところ、平均出席率は74%まで上昇。
個々の強制ではなく、「みんなが参加している」という状況の可視化が、ルールの“納得感”を高めた事例です。
不公平感を生むのはルールではなく「説明と運用の不一致」
ルールによる不公平感は、実はルールそのものではなく、次のような状況から生まれます:
- 一部の人にだけ例外が許されている
- ルールを破っても黙認される人がいる
- 導入理由や背景が説明されていない
- 守っている人が報われない
これらを避けるには、ルールの意義と運用の整合性を取ることが不可欠です。ルールは「守る価値のあるもの」として機能する時にこそ、人はそれに従い、納得するのです。
また、守っている人がきちんと評価される仕組みを作ることで、「損してる感」や「やっても意味がない感覚」を減らすことができます。
そのためには、評価制度とルール遵守の連動も重要です。たとえば、
- コンプライアンス順守を評価項目に入れる
- 定期的に「守っている人」を表彰する
- ルールを見直す機会に社員の意見を取り入れる
といった仕掛けが有効です。
「価値あるルール」は、組織の信頼と一体感を生む
ルールが組織に根づくかどうかは、そのルールが「納得できるか」「自分たちにとって価値があるか」にかかっています。
ルールに価値を与えるためには、内容よりも「意味づけ」と「運用の公正さ」が鍵になります。
- 何のためのルールなのか?
- 誰にとってどんな利益があるのか?
- なぜ今、それが必要なのか?
これらの問いに答えられるルールだけが、人の行動を動かし、不公平感のない健全な組織文化を育てていきます。
つまり、ルールを「守らせるもの」から「共に守る価値あるもの」へと転換することが、不満を納得に変える唯一の道なのです。
小さな行動が空気を変える:あなたにもできる“ルール文化”づくり

「ルールを守らせる文化」というと、組織のトップや管理職だけの課題に思われがちですが、実は、もっとも効果的に空気を変えるのは現場にいる一人ひとりの小さな行動です。
大がかりな制度変更や厳しい監視を行わずとも、周囲の“雰囲気”に影響を与えるような行動を地道に積み重ねることで、職場の規範意識は確実に変わっていきます。
本当に文化をつくるのは、「制度」ではなく「人のふるまい」なのです。
「ルールが守られている空気」を日常の中で自然に生み出す
文化とは、繰り返される行動が蓄積された結果、無意識のうちに共有される価値観です。
その意味で、「ルールを守っている人が評価される」「守らない人にやんわりと指摘が入る」「ルールの意義がさりげなく語られる」といったさりげない場面の積み重ねが、最も影響力のある文化形成装置になります。
たとえば、次のような行動は「空気づくり」において効果的です:
- ルールに従った行動をしている同僚に「いいですね」と肯定的な一言をかける
- 誰かがルールを逸脱したとき、非難ではなく「それ、大丈夫でした?」と確認する
- 雑談の中で「なんでこのルールがあるんでしょうね」と背景を問い直す機会をつくる
こうした日常的な行動が周囲の認識に影響し、「ルールを守るのが当たり前」という規範を自然に醸成していくのです。
実際、職場の心理的安全性とルール遵守との関連を調べた2022年の国内企業研究(N=512)では、「同僚がルールを守っていることに気づき、それを評価する空気のある職場」では、自己申告によるルール遵守率が84.1%と高くなるという結果が出ています。
対して、「誰も声をかけない・関心がない職場」では遵守率は54.7%にとどまり、空気の力が明確に表れていました。
一人の行動が周囲の“許容範囲”を変えていく
人は、「これくらいは大丈夫だろう」「誰も言わないから問題ない」という“暗黙の許容範囲”の中で行動を調整しています。この範囲は、実は柔らかく、日々のコミュニケーションで簡単に変化します。
たとえば、ある会社で「就業中のイヤホン着用は禁止」というルールがあっても、誰も注意せず黙認していれば、着用はすぐに日常化します。しかし、ある日「そのルールって、気づいてる?」と一人がやんわり指摘しただけで、その行動が「少し気まずいこと」に変わる。
そして別の人が「今日はイヤホンなしで集中できたかも」と言えば、「着けない方がいいのかな」という空気が生まれる。
このように、一人の“声”や“ふるまい”が、許される行動の範囲=空気をジワジワと変えていくのです。
指摘より「示す」が空気を変える最大の力
行動変容においてもっとも効果的なのは、強制でも説得でもなく、「ロールモデルとしての実践」です。
つまり、誰かが率先してルールに則った行動をするだけで、それが周囲に影響を与えるのです。
ハーバード大学の調査(2019年)では、職場におけるコンプライアンス遵守の実験で、上司ではなく“周囲の同僚”がルールを守る姿勢を示した場合の方が、部下のルール遵守率が17%高かったという結果が報告されています。
これは、「私も見られている」「ここでは守るのが普通だ」という無言の圧力=規範形成が働いたことを意味します。
つまり、口で「守れ」と言うより、自らが実践する方が何倍も強い影響を与えるのです。
“ルール文化”は、特別な人だけが作るものではない
「文化づくり」と聞くと、大掛かりなプロジェクトや経営層の決断が必要だと感じるかもしれません。
しかし実際には、空気を変える力を持っているのは日々現場で働く一人ひとりです。誰でも今日からできる行動が、職場の“空気”を少しずつ変えていきます。
その積み重ねが、やがて「ルールを守ることが自然」「守らないと違和感がある」という組織文化へとつながっていくのです。
- 誰かのルール順守を肯定的に言葉にする
- さりげなく背景を共有する会話を挟む
- 自ら率先してルールに従う姿を見せる
こうした行動こそが、“ルール文化”を内側から育てる最も確実で、持続可能な方法です。
空気は変えられる。あなたの行動から始まる
職場の文化や空気は、決して自然発生的なものではありません。
人の行動の積み重ねによって形成され、またその行動によって更新されていくのです。
そして、その行動を変える力は、特別なリーダーだけでなく、あなた自身の「小さな一歩」にある。
誰もができる小さな言動が、やがて組織全体の空気を変え、ルールを「守られるもの」ではなく「守りたくなるもの」に変えていきます。
文化は制度で決まるのではない。人がつくり、人が守るもの。
ルールの力を最大化する鍵は、あなたのふるまいの中にあります。
▼以下のリンク先の記事もお薦めです。
★この記事について:質問と答え
Q1. なぜ職場でルールが守られないのですか?
A.
ルールが守られない最大の理由は、「個人の意識やモラルの低さ」ではなく、職場に流れる“空気”や社会的規範にあります。たとえ制度としてルールが整っていても、周囲が守っていなければ「自分も守らなくていい」という認知が働きます。逆に、多くの人がルールを自然に守っている空気の中では、違反しづらくなるのが人間心理です。つまり、ルール遵守の鍵は環境づくりにあります。
Q2. ルールを守っても損をするように感じるのはなぜですか?
A.
ルールを守ることが「報われない」と感じる背景には、ルールの目的やメリットが共有されていないことや、違反者が見逃されている不公平さがあります。このような状態では、まじめな人ほど「守る方がバカを見る」と感じやすくなります。ルールが形だけになってしまうのを防ぐためには、ルールの意味を明確に伝え、共通の価値として定着させる工夫が必要です。
Q3. 自分に何ができる?職場のルール文化を変えるにはどうすればいいですか?
A.
文化を変えるのに、特別な立場や権限は必要ありません。周囲の空気に影響を与える日常的な行動――たとえば、ルールを守る姿勢を示す、守っている人をさりげなく褒める、ルール違反に気づいたときに攻撃的でない形で声をかける、などの積み重ねが文化を変える力になります。実際に、周囲の模範となる行動があるだけで、他人の遵守率が数十%上がるというデータもあります。
▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。