私たちの日常には、目に見えない“満たされなさ”が静かに広がっています。
仕事もしている、生活もしている、SNSを開けば誰かの楽しそうな投稿が流れてくる──
けれど、なぜか心が晴れない。何かが足りない。そんな感覚に、思い当たることはありませんか?
「もっと成果を出さなきゃ」「あの人みたいにならなきゃ」「このままじゃダメなんじゃないか」──
こうした“足りない思考”は、気づかぬうちに心を疲れさせ、いつの間にか「満たされることを諦める癖」になってしまうこともあります。
けれど、それは本当に「あなたのせい」なのでしょうか?
実はこの「足りない」と感じる感覚は、脳が本来持っているごく自然な反応であり、あなたの性格や努力不足とは無関係だということが、脳科学の研究によって分かってきています。
つまり、私たちは「満たされにくい脳」と一緒に生きている──
という前提を知らずに、苦しんでいるのかもしれないのです。
では、どうすればこの満たされない日々に、小さな変化を起こせるのでしょうか?
「もっと頑張る」以外に、心を整える方法はあるのでしょうか?
もしあなたが、何となく心に余裕がない日々や、理由のない焦りに悩まされているなら――
「感謝」という、とても小さくて、けれど確かな“習慣”が、その答えになるかもしれません。
「感謝する」という行為が脳と心に与える影響を紐解きながら、なぜそれが“満たされにくい脳”を変えていくのか、そしてどうすれば無理なく始められるのかを、解説していきます。
無理に前向きになる必要はありません。今ある自分のまま、できることから始めてみましょう。
「足りない」と感じるのは、脳の本能だった──感情のメカニズムを科学で読み解く

「何かが足りない」「もっと欲しい」「このままではダメな気がする」──
こうした思いは、現代を生きる多くの人にとって日常的な感覚ではないでしょうか。SNSのタイムラインを眺めていると、他人の成功、幸せそうな日常、自分にはない何かが、次々に目に飛び込んできます。すると、今の自分の生活がどこか物足りなく、不十分に思えてくるのです。
しかしこの「足りない」と感じる感覚は、あなたのわがままや欲深さのせいではありません。実は、人間の脳が本来持っている“生存のための仕組み”によって生じている、ごく自然な感情なのです。
ネガティビティ・バイアス──生き延びるための「悪いこと探し」の癖
私たちの脳は、進化の過程で「悪いこと」「危険なこと」「足りないこと」に敏感に反応するように設計されてきました。これをネガティビティ・バイアス(negativity bias)といいます。
これは、人間が原始時代に生き延びるために必要だった本能です。
たとえば、食料が不足している、敵が近くにいる、仲間に嫌われる──このような「マイナスのサイン」に素早く気づく能力が、生存を左右していたのです。
現代では、野生動物に襲われることも飢え死にすることもありません。しかし、脳の構造自体は太古のままです。その結果、「まだ足りない」「もっとよくしないと危ない」というサインに過剰に反応し続けてしまうのです。
たとえば、2001年に発表された心理学研究(Baumeisterら)によれば、人は「悪い情報」に対して「良い情報」の約2.5倍も強く反応するというデータがあります。
これはつまり、どれだけ自分が成果を出しても、少しの失敗や他人との比較によって「自分はまだダメだ」「まだ満たされていない」と感じやすくなる、ということです。
欠乏感の正体──「恒常性維持」を求める脳の動き
もう一つ注目すべきは、人間の脳が持つ恒常性(ホメオスタシス)機能です。
これは、体温や血糖値などの生理的状態を一定に保つための仕組みですが、感情や欲求の面でも同じような「一定の状態を保とうとする力」が働いています。
たとえば、何かを達成して満足感を得たとしても、その状態は脳にとって“異常値”であり、時間が経つと自然と元の「欲しい」「足りない」という状態に戻されます。これをヘドニック・トレッドミル(快楽のランニングマシン)と呼びます。
心理学者フィリップ・ブリックマンの研究によれば、宝くじで高額当選した人たちは、数か月後には事故で障害を負った人たちと同程度の幸福度に戻っていたという衝撃的な結果が出ています。人間は、どれだけ恵まれても、やがて「慣れてしまい」、再び何かを求め続けてしまうのです。
この仕組みこそが、「いくら努力しても満たされない」「何かを手に入れても満足できない」という感覚の根本原因です。
「比較」の罠──現代の脳は情報過多にさらされている
現代社会がこの欠乏感を加速させている原因のひとつに、「比較のしやすさ」があります。
SNSやインターネットによって、他人の生活、成功、評価が一瞬で見えてしまう時代。私たちの脳は、そこに映る“理想化された他人”と自分を無意識に比べてしまい、「自分には足りない」と感じやすくなります。
2018年にアメリカの心理学誌に掲載された研究では、SNSの利用時間が長い人ほど、自己評価が低く、幸福感も低い傾向にあることが報告されました。
特に「いいね」やフォロワー数といった“数字での評価”が、承認欲求を過剰に刺激し、恒常的な不満感を生む原因になっているのです。
「足りない感情」をリセットするには、“気づく力”が必要
ここまで見てきたように、「足りない」と感じるのは、あなた自身の問題ではなく、脳の仕組みによるものです。
だからこそ、努力や思い込みだけでそれを克服しようとするのではなく、「脳がそう感じやすくできている」という前提を知り、そのパターンに“気づく”ことが第一歩となります。
そして、この“ネガティブに傾きやすい脳”の動きをリセットする手段として、効果的なのが「感謝」という行動なのです。
感謝は、今この瞬間にあるもの、すでに満たされている事実に目を向ける行為です。それは脳の“足りない探し”を一時的に停止させ、“あるもの探し”へとスイッチさせる行動でもあります。
この習慣が続くと、脳内で「あるものに注意を向ける神経回路」が強化され、やがてそれが「満たされている」と感じる感受性そのものを育てる土台になっていきます。
足りなさを感じること自体は悪ではない。問題は、それに“気づけるか”どうか
脳が「足りない」と感じるのは、ごく自然で、むしろ必要な反応です。問題は、その反応に振り回され、「永遠に満たされない渇望」のループに入ってしまうことです。
そのループから抜け出すためには、自分がいま「足りない」と感じている背景に、どんな脳の動きがあるのかを理解する必要があります。
そして、その仕組みに“気づいたうえで”、感謝という小さな行動を日常に取り入れることで、脳の働きそのものを“足りる方向”に調整していくことが可能になるのです。
つまり、「感謝」は、脳がつくる“足りなさの錯覚”を打ち破る方法なのです。
感謝が脳に起こす変化──「幸福ホルモン」がもたらす科学的な心の安定

感謝の習慣が心を豊かにする──
これは決して精神論ではなく、脳科学的に裏付けられた事実です。
実際、「ありがとう」という行為ひとつで、脳内では私たちの気分や行動に大きな影響を及ぼす“幸福ホルモン”が分泌されています。
これらのホルモンは、ストレスを緩和し、心の安定やポジティブな行動を促す働きを持っており、感謝が習慣化されることで“満たされない日々”が少しずつ変わっていくことが、脳内の生理学的変化によって説明できるのです。
ここでは、感謝によって分泌される代表的な3つの幸福ホルモン「ドーパミン」「セロトニン」「オキシトシン」について、それぞれの役割を解説します。
ドーパミン──モチベーションと達成感の源
まず、感謝の習慣によって活性化される最も代表的なホルモンがドーパミンです。
ドーパミンは、報酬系と呼ばれる脳内システムで機能しており、目標を達成したときや何か良いことがあったときに分泌されます。
いわば、「やる気」や「期待感」を生み出す原動力です。
感謝の行動──たとえば、「今日はコーヒーが美味しかった」「上司に褒められた」「友人が話を聞いてくれた」など、小さな出来事に「良かった」と意識を向けることで、脳はそれを“ご褒美”として認識し、ドーパミンが分泌されます。
ある研究(Emmons & McCullough, 2003)では、「週に1度、感謝したことを記録するグループ」は、そうでないグループに比べて行動力が向上し、運動習慣や人間関係の質も改善したと報告されています。これは、ドーパミンによってポジティブな行動が連鎖するためです。
また、別の研究(Korb, 2012)によれば、感謝の習慣によって前頭前皮質(思考や感情調整を担う脳部位)の活動が活発になり、それに伴ってドーパミン分泌が促進されることも示されています。
セロトニン──心の安定を支える「幸福の基盤」
次に、感謝が促進する重要な神経伝達物質としてセロトニンがあります。
セロトニンは「心の安定」を支える物質で、不足するとイライラ、不安、うつ症状の原因となります。
感謝の行動は、自律神経系にも好影響を与え、セロトニン分泌を自然に増やす効果があるとされています。
これは、感謝が「今ここに意識を向ける」マインドフルな行動であるため、脳がリラックス状態に入り、副交感神経が優位になるためです。
米国精神医学会の調査では、「感謝の気持ちを意識的に持った人々は、セロトニン系抗うつ薬(SSRI)を使用している患者と同程度の精神的安定を得られる場合がある」という結果も報告されています。
また、セロトニンは脳だけでなく腸にも多く存在しており(全体の約90%が腸で生成)、感謝のような前向きな感情は消化機能の活性化にもつながるという副次的効果も期待できます。
オキシトシン──「つながり」を生み出す愛情ホルモン
3つ目の重要なホルモンが、オキシトシンです。
オキシトシンは「愛情ホルモン」「絆ホルモン」とも呼ばれ、他人と信頼関係を築いたときや、誰かに優しくされたとき、逆に優しくしたときに分泌されます。
感謝の言葉を誰かに伝える──たとえば「ありがとう」「あなたのおかげで助かった」など、簡単な言葉でも、オキシトシンは活性化されます。そしてこのホルモンが、人間関係を円滑にし、孤独感を和らげ、ストレスに強い心を育てるのです。
特に現代のように、人とのつながりが希薄になりがちな社会では、オキシトシンの役割は極めて重要です。
2021年に米コロンビア大学が行った研究では、「日常的に感謝を表現する人は、孤独感スコアが20%以上低い」という結果が出ています。
また、オキシトシンは免疫力の向上にも関与しており、感謝の実践が健康全体に与える影響も注目されています。
感謝はホルモンの“同時作用”を引き出すスイッチ
感謝の行動がこれら3つのホルモンを同時に活性化させる点において、ユニークで強力な心理・生理介入手段であることは間違いありません。
しかも、これらは薬物に頼らず自然な方法で分泌され、副作用ゼロで効果を得られるという点も大きなメリットです。
- ドーパミン → モチベーションと行動力の源泉
- セロトニン → 心の安定とメンタルヘルスの土台
- オキシトシン → 人とのつながり、社会的安心感の形成
たったひとつの「ありがとう」が、脳と心と体をつなぎ直し、“満たされない”感情の背景にある機能不全を調整してくれるのです。
感謝は「幸せな自分」をつくるホルモンのトリガー
私たちが「満たされない」と感じるとき、それは外部の条件が不足しているのではなく、内部の神経伝達が“止まっている”状態である場合が少なくありません。
そのスイッチを再びオンにするのが、「感謝する」という、極めてシンプルで、人間本来が持つ行動なのです。
感謝は心のマッサージであり、脳のスイッチでもあります。
毎日少しずつ感謝を意識することで、幸福ホルモンの自然な分泌が促され、気づかぬうちに、「満たされない」状態から「十分にある」という感覚へと、心の地図が塗り替えられていくのです。
幸福とは、手に入れるものではなく、“気づいていくもの”です。
その第一歩が、「感謝する」ことなのです。
感謝を“習慣化”する力──SNSや実践者が語る変化のリアル

「感謝が脳に良いことは分かった。でも、実際にどう始めればいいの?」──
その疑問に応えるように、近年はSNSやブログ、フォーラムを中心に“感謝の習慣化”をテーマとした発信が増えています。
InstagramやX(旧Twitter)では「#感謝習慣」「#感謝日記」などのハッシュタグが日々更新され、多くの人が自らの変化を記録し、シェアしています。
感謝は一時的な「気分転換」ではなく、続けることで脳と心の回路を切り替える“再構築の技術”です。
その力を最大限に活かすには、日常生活に“習慣”として組み込むことが不可欠です。
ここでは、数万人以上の投稿や研究データから裏付けられた、感謝の実践法とその効果を紹介します。
「感謝を習慣にする」ことの脳科学的インパクト
まず前提として、脳は「繰り返される行動」に最も強く反応する臓器です。
何度も意識的に実践された行動は、やがて無意識の領域で「当たり前の思考回路」として定着します。これは神経可塑性(Neuroplasticity)と呼ばれる現象で、「感謝を習慣にすることで“満たされやすい脳”が育つ」という仕組みの根拠でもあります。
実際、米国心理学者ロバート・エモンズの研究では、感謝を週3回以上日記に記録したグループは、うつ傾向が35%減少し、6週間後には睡眠の質も25%改善したというデータが報告されています。また、感謝習慣のある人は、自己肯定感や人間関係の満足度も平均して15~20%高い傾向にあります。
こうした変化は「劇的」ではなく、「穏やかに・確実に」起こっていく点も特徴です。つまり、感謝習慣とは“脳の地図を塗り替える旅”なのです。
今すぐ始められる、SNSで人気の3つの感謝習慣
では、どのような方法なら日常に取り入れやすく、かつ効果的なのでしょうか?
ここでは、SNSや実践者たちが支持している「続けやすい感謝習慣」を3つ紹介します。どれも「手間がかからない」うえに、「継続率が高い」方法です。
① 感謝日記をつける(#感謝日記)
もっとも広く行われている感謝習慣が、「1日3つ、感謝したことを書く」というものです。
たとえば:
- 「駅で席を譲ってくれた」
- 「空がきれいだった」
- 「いつものパンが焼き立てだった」
このような“小さな出来事”で十分です。
心理学ではこれを「ポジティブ・ジャーナリング」と呼び、脳の注意を「足りない」から「すでにある」へと向ける再訓練になります。
SNSでは、「#感謝日記」の投稿件数がXで5万件以上(2025年6月時点)、多くの人が「メンタルが安定した」「怒りっぽさが減った」と実感を共有しています。
また、研究によれば、寝る前に感謝日記をつける人は、不眠症のリスクが約30%低下するとも報告されています(Wood et al., 2009)。
これはセロトニン分泌が促進され、睡眠導入がスムーズになるためです。
② 朝1分の「感謝宣言」(#朝活 #感謝習慣)
次におすすめなのが、朝起きた直後に「感謝することを1つ思い浮かべる」という方法です。
「今日も無事に目が覚めた」「天気がいい」「コーヒーが美味しい」など、内容は何でもかまいません。
この習慣は、朝に交感神経が過度に優位になる“朝ストレス”を軽減する効果があるとされ、SNSでも「#朝活」「#感謝の朝ルーティン」として注目を集めています。
特にXでは、「朝イチで感謝を3つ言うだけで、イライラが激減した」「通勤が苦じゃなくなった」といった体験談が多数投稿されています。
朝のわずか1分が、その日の精神的基盤を整える“感情の土台”になるのです。
③ 1日1回「誰かに感謝を伝える」(#ありがとう習慣)
感謝は、自分の内側に留めるだけでなく、外に「表現」することで脳への影響が強化されます。
LINEやメール、SNSの投稿、直接の会話などで、1日1回「ありがとう」を誰かに伝えてみましょう。
この行為は、前述のオキシトシン(信頼や絆を強めるホルモン)の分泌を促進し、感情の安定だけでなく、対人関係にも良い影響を与えます。
スタンフォード大学の研究では、1日1回の感謝表現を3週間続けた被験者は、職場での人間関係の満足度が平均18%向上したと報告されています。
つまり、「ありがとう」と言う習慣は、自分だけでなく相手にもプラスの感情をもたらす“感情の共鳴装置”なのです。
感謝を「習慣にするコツ」は、完璧を求めないこと
習慣化には、「毎日きちんと続けないと意味がない」と思いがちですが、感謝に関しては“ゆるくても続ける”ことのほうが効果が高いという報告があります。
これは、完璧主義に陥るとストレスになり、セロトニンやドーパミンの分泌がむしろ抑制されてしまうためです。
たとえば:
- 書けない日は「昨日の感謝」を思い出すだけでもOK
- SNSで他人の感謝投稿に「いいね」するだけでもOK
- 忘れたら翌日2倍書けばいいと軽く考える
このように“継続しやすい設計”にしておくことが、習慣定着のカギです。
感謝の習慣は、あなたの脳と人生を穏やかに書き換える「小さな革命」
感謝の習慣は、派手な変化をもたらすものではありません。
けれど、あなたの脳の回路を少しずつ穏やかに書き換えていく“静かな革命”です。
SNSやフォーラムで多くの人が感謝をシェアするようになっている背景には、明確な理由があります──
それは、「効果があるから」。
そして、何より「誰にでも、どんな環境でも、今すぐできるから」です。
習慣とは「意志ではなく、仕組みで続けるもの」。
感謝もまた、あなたの生活にそっと仕組まれたとき、本当の効果を発揮します。
「足りない」と感じる人生のなかで、「すでにあるもの」に光を当てる力。それが、感謝という“日常に組み込まれた魔法”なのです。
「感謝できない日」にこそ、感謝の本質が見えてくる──心が疲れたときの処方箋

どんなに感謝が心や脳に良いと分かっていても、「どうしても感謝できない日」は誰にでもあります。
むしろ、感謝を続けている人ほど、このような壁にぶつかります。
嫌な出来事が重なった日。心が沈んで何も感じられない日。感謝なんてきれいごとに思えるほど、現実が苦しい日──。
そんな日があるからこそ、「感謝とは何か?」を深く見つめ直す機会になります。
感謝とは、幸せな人だけができる贅沢な感情ではありません。
むしろ、「感謝できない」と感じた瞬間にこそ、脳と心は何かを訴えていて、それを見つめ直すことが“再起動”の第一歩となります。
感謝は「ポジティブ思考」ではなく「現実を見つめ直す力」
感謝が精神論に聞こえてしまうのは、「嫌なこともポジティブに捉えましょう」というニュアンスが含まれているように思えるからです。
しかし実際の感謝とは、「嫌な現実を無理に美化する」ことではありません。
感謝とは、「嫌なこと」と「ありがたいこと」が同時に存在する“複雑な現実”をまっすぐに見つめる力です。
たとえば、「仕事でミスをした」「理不尽なことを言われた」という日にも、もしかしたら「帰宅後に温かいご飯が食べられた」「友人がLINEをくれた」といった小さな事実があったかもしれません。
感謝は、それらに“気づく力”を鍛える行動なのです。
心理学者のブレネー・ブラウン博士は、「感謝は感情ではなく、選択と実践である」と述べています。
つまり、感謝は「感じる」ものではなく、「意識的に見出す」ものなのです。
「何も感謝できない日」は、脳がストレスで思考停止しているサイン
感謝できない日があるのは、あなたの心が弱いからでも、怠けているからでもありません。
それは、脳がストレスや疲労で一時的に情報処理能力を失っているサインです。
ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されると、脳の海馬や前頭前皮質(感情や記憶の調整を司る部位)の働きが低下します。
すると、目の前の出来事を多面的に捉える余裕がなくなり、「つらいこと=全て」と感じてしまいます。
このときに無理に感謝を探そうとすると、かえって「感謝できない自分」に落ち込み、自己否定のループに陥ってしまいます。
だからこそ、「感謝できない日があるのは自然なこと」と、まず自分を許すことが重要です。
ある研究では、「感謝の習慣を無理なく継続できている人」は、「できない日があっても自分を責めない人」が圧倒的に多いという結果も出ています(Emmons & Stern, 2013)。
感謝できないときにこそ役立つ3つのステップ
1. 「感謝できない」と書き出してみる
皮肉なことに、「感謝できない」と感じている思考を紙に書き出すと、それだけで脳は「主観」から「観察」モードに切り替わります。
感情を言語化することで前頭前皮質が活性化し、ストレスの感情が緩和されることが知られています(Pennebaker, 1997)。
たとえば、「今日は本当に最悪だった。何も感謝できない。」と書いても構いません。それ自体が、自分の感情を見つめる“心のデトックス”になります。
2. 感謝の「予備リスト」を用意しておく
感謝できない日のために、「いつもなら感謝できることリスト」をあらかじめ作っておくのも効果的です。
たとえば:
- 「お湯が出る」
- 「天気がいい」
- 「呼吸ができる」
- 「ペンが書ける」
あまりに小さいことに思えるかもしれませんが、実際にそれがない生活を想像してみると、その価値が実感できます。
こうしたリストは、心が疲れて視野が狭くなったときの“感謝の再起動ボタン”となります。
3. 他人の「感謝」に触れる
自分ではどうしても感謝できないときは、他人の感謝投稿や体験談を読むことも効果的です。
SNSで「#感謝日記」「#ありがとう習慣」などの投稿を見ると、他人の視点が自分の認知に新しい角度をもたらしてくれます。
脳は共感によってオキシトシンが分泌され、徐々に「感謝に対する感受性」が戻ってくるのです。
感謝は「綺麗な心」の産物ではない──痛みの中からでも育つもの
私たちは、感謝できる人=前向きで心が整った人、といった理想像を持ちがちです。
しかし実際には、傷ついた経験や不安の中にいるからこそ、感謝が深く染み込むこともあるのです。
「今日も生き延びられた」「この気持ちを抱えて、まだ頑張っている自分がいる」──
これも立派な“感謝の芽”です。
感謝とは、光が差し込むときだけでなく、暗闇の中にある微かな光を見つける訓練でもあります。
そして、その光に気づいた瞬間、脳は少しだけ呼吸を取り戻し、また新しい行動へと歩き出せるのです。
「感謝できない日」は、あなたの心が“回復を求めている”サイン
感謝は義務ではありません。
それは、心が「整っている証」ではなく、「整えようとする意志」そのものです。
だから、もしあなたが「今日は何も感謝できない」と感じたなら、それは脳が疲れているサインであり、休息と優しさを求めている証拠です。
その自分を責めずに、「今日は何もしない」ことすら、ひとつの感謝のかたちだと受け入れてください。
感謝できる日もあれば、できない日もある──その揺らぎを受け入れることこそが、真のレジリエンス(心の回復力)を育てます。
感謝とは、完成された感情ではなく、「いまを丁寧に見つめる生き方」なのです。
★この記事について:質問と答え
Q1.感謝の習慣を続けると、なぜ「満たされない気持ち」が減っていくのでしょうか?
A:感謝をすることで、脳内で「幸福ホルモン」と呼ばれるドーパミン、セロトニン、オキシトシンが分泌されます。これらのホルモンは、ストレスの軽減や感情の安定、人とのつながりの強化に関与しており、感謝を習慣にすることで脳がポジティブな刺激に気づきやすくなり、「足りない」ではなく「すでにあるもの」に目を向けられるようになります。
Q2.感謝できない日が続いてしまうと、習慣の効果はなくなってしまいますか?
A:いいえ。感謝習慣は“完璧に続ける”ことよりも、“意識的に戻る姿勢”が大切です。感謝できない日があるのは自然なことで、その状態を受け入れることで心の柔軟性(レジリエンス)も高まります。脳科学的にも、数日感謝を休んだとしても再開すればホルモン分泌は再び促進されるため、安心して続けていくことができます。
Q3.感謝習慣は、どんな人におすすめですか?
A:「何となく心が満たされない」「ストレスを感じやすい」「ポジティブになろうとするのが苦手」と感じている方に特におすすめです。感謝習慣は感情を無理に変えるのではなく、“気づき”を増やす方法であり、脳の働きに沿った自然な手法です。日本でもSNSやフォーラムで実践者が増えており、誰にでも取り組みやすいセルフケアとして注目されています。
▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。
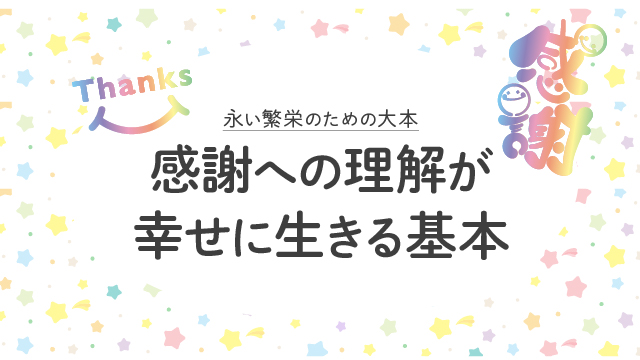
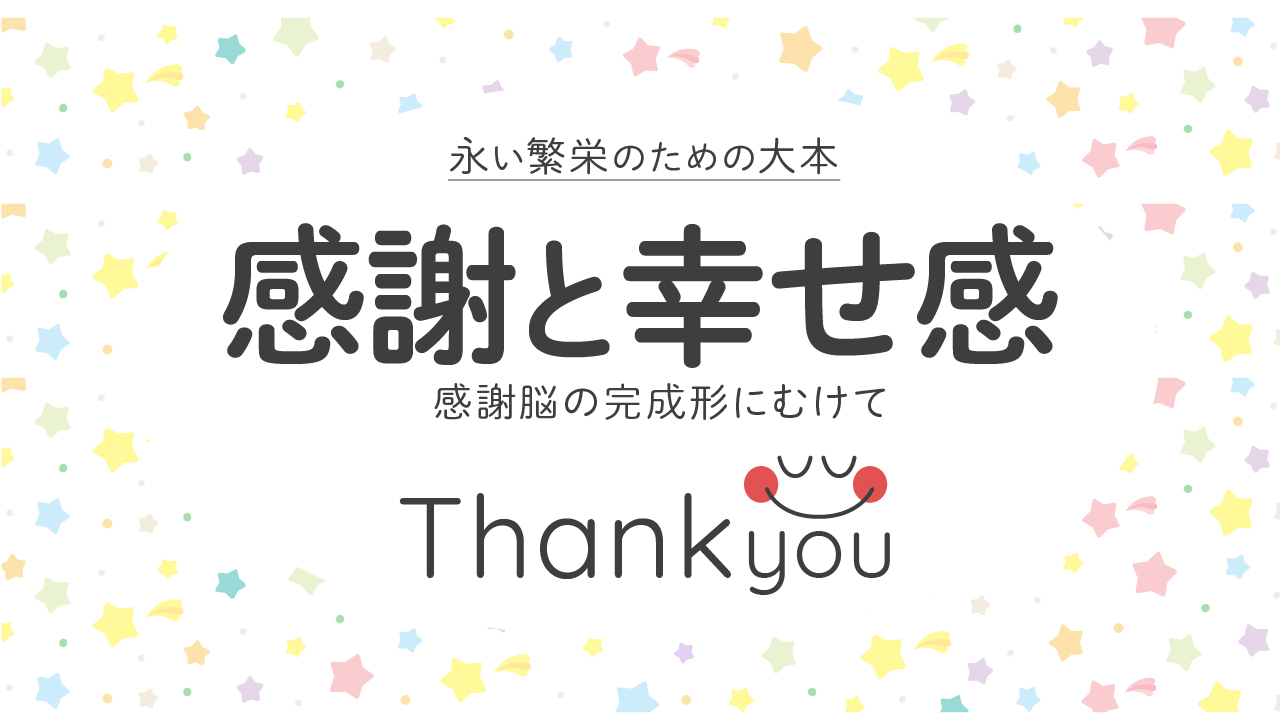

▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。



