かつて順調に昇進していたはずなのに、ある年から管理職の話が来なくなった——
そんな経験に心当たりのある方はいませんか?
「あの人は将来の役員候補だ」と言われた時期もあったのに、今では若手の部下がどんどん上に上がっていく。なんとなく置いていかれたような、見放されたような気持ちになり、自信を失いかけている…。これは多くの日本のサラリーマンが直面する、身近で現実的な問題です。
出世=成功、肩書き=価値。そんな価値観の中で働いてきた私たちにとって、「出世から外れた」という事実は、思っている以上にショックを与えます。まるで、それまで積み上げてきた努力や実績が否定されたような気がするからです。
でも、そこで問い掛けたいのです。本当に「出世しないこと=失敗」なのでしょうか?あなたの仕事には意味がないのでしょうか?
もしかすると、その問いに対する答えは、「見方を変えること」で見つかるのかもしれません。今の立ち位置をどう捉え直すか——
その視点の切り替えこそが、これからのキャリアと心の安定をつくる第一歩になるのです。
出世から外れることが意味するもの

会社組織において「出世コースを外れる」という現象は、単に昇進できなかった、昇格が遅れたといった表面的な事象にとどまりません。
これは、個人の社会的評価や職業的アイデンティティに深く関わり、心理的には「組織からの否定」と捉えられることすらあります。
とくに日本の企業文化においては、出世はその人の「人格的成熟」や「社会的成功」と直結して評価される傾向があり、それを外れた者には、しばしば目に見えないが重たい烙印が押されるのです。
終身雇用と年功序列が生み出した「出世の一本道」
日本の戦後型雇用システムは、終身雇用と年功序列を基軸として構築されてきました。特に高度経済成長期(1950年代後半〜1970年代)は、企業が社員を長期的に雇用し、その中で年齢や勤続年数に応じて役職を与えるという仕組みがうまく機能していました。
社員にとっては、「我慢していれば、いずれは昇進できる」という保証があったため、会社と個人の利害は一致していたのです。
この仕組みの中では、「出世すること」=「組織に忠誠を尽くし、長く勤め続けた結果」となり、出世とは単なるポスト以上の意味を持つようになりました。
逆に言えば、「出世から外れること」は、組織からの忠誠に報いられなかった結果、すなわち、組織の基準に照らして「期待外れ」とされたと個人が受け取る可能性が高くなるわけです。
ある労働政策研究・研修機構の調査(2023年)によれば、「管理職にならない・なれない人」の割合は、大企業で約30%、中小企業では実に45%にも上ります。
さらに「出世できなかったことにより、モチベーションが低下した」と回答した人は、そのうちの7割を超えています。これは、昇進の有無が単に役割分担の問題にとどまらず、自己肯定感や職業的意義に深く影響している証拠です。
組織の構造的変化と「ポスト不足」の現実
一方で、社会・経済の変化により、企業の中間管理職層のポストは年々減少しています。特にバブル崩壊後、企業は組織のスリム化と効率化を進め、管理職のポスト数を削減しました。
さらに、2000年代以降はフラット型組織やプロジェクトベースの業務体系の導入により、「役職に就くこと」自体の価値や意味が変わりつつあります。
日本経済新聞の調査(2022年)によれば、従業員500人以上の企業での「部長職以上のポスト」は、1995年比でおよそ23%も減少しているとされています。これは、いくら能力があっても、構造的に“椅子が足りない”状況が生じていることを意味します。
その結果、実力があっても昇進できない社員が多数出現し、「出世から外れた=無能」という従来の認識が、実態と乖離している状況が生まれています。
とはいえ、企業文化としては、まだこの変化に追いついておらず、出世を逃した人が「キャリアに失敗した」と見なされる構図は根強く残っています。
キャリアの一極集中がもたらす精神的リスク
こうした背景から、「出世を逃したこと」による心理的ダメージは深刻なものになります。
職業アイデンティティ研究で知られる心理学者エドガー・シャインは、「人は働くことを通じて自己認識を構築する」と述べています。つまり、仕事上の地位や役割が、自分自身の存在価値の根幹に関わってくるのです。
実際、キャリア構築が出世コースに集中していると、それを外れたときに代替の評価軸が存在せず、「自分には価値がないのでは」という思考に陥りやすくなります。
企業内での序列にアイデンティティを大きく依存していた人ほど、その喪失感は大きく、うつ病や離職、早期退職へとつながるリスクも高まります。
厚生労働省の調査(2021年)では、40代~50代の中間管理職未経験層で、心理的ストレスを「非常に感じる」と答えた人は全体の64%にのぼり、管理職経験者よりも約15ポイント高いという結果が出ています。この数値は、出世機会の欠如が個人の心理に与える影響の深さを物語っています。
本当に「外れた」のか、それとも「選ばなかった」のか
ここで注目すべき視点として、「本当に出世コースから外れたのか、あるいは自ら選んで外れたのか」という問いがあります。
近年では、自ら積極的に昇進を断る“ノンマネ志向”の人も増えており、その理由として「プライベート重視」「部下のマネジメントに興味がない」「業務専門性を維持したい」などが挙げられます。
パーソル総合研究所の調査(2023年)では、「昇進を望まない」と答えた30代社員は全体の41.2%。そのうちの約6割が「マネジメント職に魅力を感じない」と答えています。つまり、出世を選ばなかった人も多く存在するという現実を考慮すれば、「出世から外れた」ことを一律に失敗や劣等と捉えるのは、時代錯誤的な認識とも言えるのです。
このように、企業内の評価軸が変化しつつある中で、「出世を逃した人」をどう支援し、どう再評価するかは、組織と個人双方にとって喫緊の課題です。そして、そこで有効なアプローチこそが、認知的再評価という心理的手法なのです。
感情の支配から抜け出す認知的再評価の力
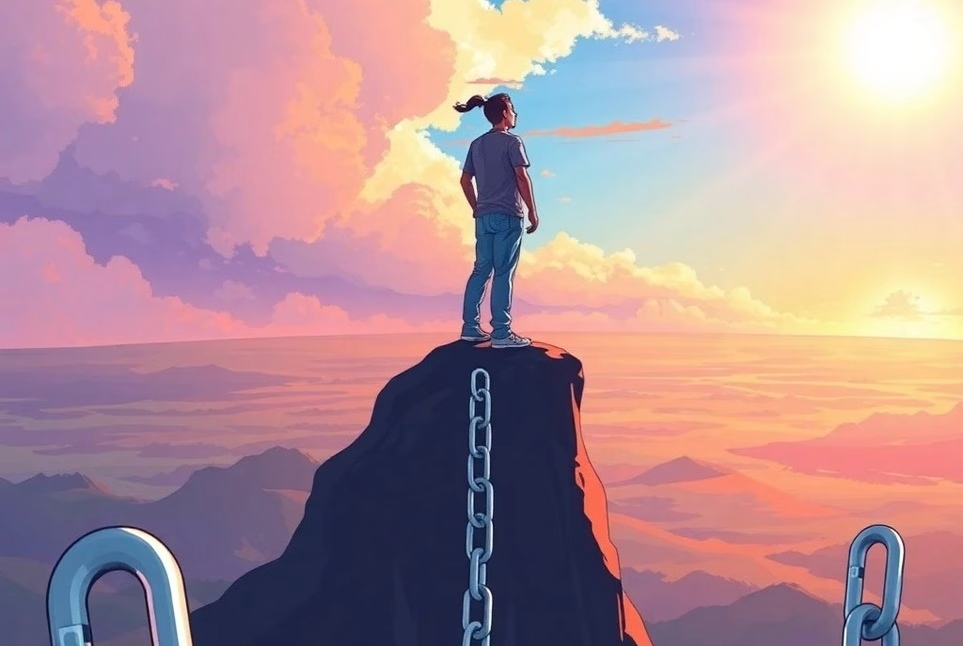
人が社会の中で生きる以上、評価・比較・期待という他者との関係性は避けられません。
とくに会社という組織では、出世という明確な指標によって、評価が見える化され、成功と失敗の線引きがなされます。この構造の中で「出世コースから外れた」と感じたとき、人はしばしば強い否定的感情、たとえば屈辱・無力感・焦燥・嫉妬などに苛まれます。
そのような感情に長く支配されると、自己肯定感の喪失や生産性の低下、果てはメンタルヘルスの悪化にまで至ることがあります。
このような心理的危機に対して有効なアプローチの一つが、認知的再評価(Cognitive Reappraisal)という感情調整技術です。
これは、ネガティブな出来事や状況に対して、その意味や捉え方を自分自身の中で意図的に変化させ、感情の反応を和らげるという心理的スキルです。単なる気休めやポジティブシンキングとは異なり、神経科学や行動心理学の研究でその効果が科学的に証明されている技法です。
認知的再評価のメカニズムと脳の働き
感情調整の代表的な理論であるGrossの感情制御モデル(1998年)によれば、人間の感情は「刺激」→「認知評価」→「感情反応」という流れで形成されます。
ここでの「認知評価」が変われば、感情の発生そのものをコントロールできるという発想が、認知的再評価の根幹にあります。
たとえば、「上司に昇進を見送られた」という出来事に対して、「自分はダメな人間だ」と捉えると強い自己否定感が生まれますが、「上司の視点と自分の価値観は違う」「今はそのタイミングではない」と再評価することで、感情の波を抑えることができるのです。
さらに、脳科学的には、認知的再評価を行ったとき、扁桃体(ネガティブ感情の中枢)の活動が抑制され、前頭前皮質(論理的判断や制御に関わる部位)の活性化が確認されています。
これは、私たちの脳が感情のトリガーに反応する前に、“意味づけ”の段階で介入できることを示しています。
米スタンフォード大学の研究(Ochsner et al., 2002)では、認知的再評価を行った被験者は、同じネガティブ映像を見たときでも、脳のストレス反応が平均で42%も減少することがわかっています。
つまり、感情は「起きるもの」ではなく、「コントロール可能なもの」だという発見は、多くの人にとって大きな希望となります。
出世から外れた経験を「成長の機会」に変える技術
出世を逃した経験を「人生の失敗」として固定するのではなく、それを通じて「自分は何を学んだのか」「どのような選択肢が開かれたのか」という観点から意味づけを再構成することが、認知的再評価の実践です。たとえば以下のような問いかけは、思考のフレームを変えるのに有効です:
- 「もし別の部門で働けたら、何ができるか?」
- 「今の立場だからこそ見えるものは何か?」
- 「管理職でなかったおかげで守れているものはあるか?」
これらの問いに真剣に向き合うことで、「出世コースから外れた」ことが単なる損失ではなく、「別の可能性への入り口」に変わります。
実際、米国心理学会(APA)が2021年に行ったビジネスパーソンを対象とした調査では、「キャリア上の挫折を認知的再評価によりポジティブに転換できた人」は、そうでない人に比べて3年後の自己満足度スコアが平均で28%高かったと報告されています。
これは、外的成功と主観的幸福感が一致しない現代社会において、「評価の再構築」がどれほど重要であるかを示唆しています。
また、メンタルヘルスにおける有用性も広く認知されており、認知行動療法(CBT)の中核技法としてもこの再評価は用いられています。
CBTにおけるデータでは、約8〜12週間のプログラムで、うつ病の症状が50%以上軽減する例が報告されており(Beck Institute, 2020)、この手法の実用性はきわめて高いものです。
「ネガティブ感情のスパイラル」からの脱出
多くの人が気づかぬうちに陥っているのが、いわゆる「ネガティブ感情のスパイラル」です。たとえば出世から外れたことに対して怒りや失望を感じ、それを周囲の成功者と比較しながら自己否定へと結びつける。
そして、そうした自己評価の低下が仕事へのモチベーションを下げ、さらに評価されなくなる……という悪循環です。
このスパイラルを断ち切るためには、「出来事」と「自己価値」を切り離すことが不可欠です。認知的再評価の第一歩は、「出世=成功、非出世=失敗」という無意識の思い込みを解きほぐすところから始まります。
個人の価値は、役職ではなく「行動」「信念」「人間関係」「継続的な努力」にもとづいて評価されるべきだという視点を持てれば、自分自身に対する見方も大きく変わってくるでしょう。
その実践の中で、日記・セルフトーク・カウンセリングといった手法が有効とされています。特に「毎日の感情記録(日々の感情とその解釈を書き出す)」は、再評価能力を育てるトレーニングとして有効です。
ある研究では、これを4週間続けたグループは、自己効力感スコアが平均で35%上昇したという結果も出ています(Kross et al., 2014)。
出世を逃した経験は、確かに苦しいものかもしれません。
しかし、そこで生じた感情をただ受け入れるのではなく、それを再構成し、新たな意味づけを与えることによって、人は「感情の奴隷」から「感情の設計者」へと変わることができるのです。
再評価から始まるキャリアの再構築と価値の再発見

出世という明確な基準が存在する企業社会において、「そのレールから外れる」という経験は、多くの人にとってアイデンティティの揺らぎや自信喪失を引き起こします。
しかしその一方で、近年では「出世以外の成功」を再定義し、自分に合った価値観やキャリアパスを再構築していく人々も増えてきました。この再構築の起点となるのが、認知的再評価による内省と価値の再発見です。
キャリアの再構築とは、単に転職や部署異動を意味するものではなく、「自分が本当に大切にしたいことに基づいた働き方を再設計するプロセス」と言えます。
ここでは、組織内の立場や肩書きに左右されず、自分の価値を見直すことで得られる新しいキャリアの在り方と、それを支える心理的な変化について、解説していきます。
人生の軌道修正は「敗北」ではなく「再定義」
日本企業では依然として、年功序列や終身雇用を前提とした出世競争の構造が根強く残っています。
2019年の経済産業省の調査によれば、「40代後半で課長になれない社員は、それ以降の昇進は極めて困難」と答えた企業が約72%に上りました。このような硬直した構造の中では、「今のポジションが天井だ」と感じる人が一定数存在するのは自然なことです。
しかし、「出世から外れた=敗北」という固定観念こそが、問題の本質です。むしろこのタイミングこそが、自らのキャリアを見直すチャンスとして捉えるべき局面です。
ビジネス心理学者エミー・レズネスキー(Yale School of Management)は、「キャリアには3つの視点がある」と述べています。
- ジョブ視点(生活の糧)
- キャリア視点(地位と昇進)
- コーリング視点(使命と貢献)
昇進を主眼に置く「キャリア視点」だけに依存すると、出世が途絶えた瞬間に目標も自己価値も失われます。
一方、仕事を「社会への貢献」や「自分らしさの表現」として捉える「コーリング視点」を導入すれば、評価軸は社内のヒエラルキーではなく、「自分にとっての意味や充実感」に移行します。
この視点の切り替えが、まさに認知的再評価の実践であり、人生の再定義の第一歩なのです。
自分の強みと価値観に基づいたキャリア設計の重要性
再評価によるキャリア再構築で重要なのは、「自分の価値観」と「本当の強み」を見つめ直すことです。企業内の評価制度は、あくまで組織の都合によって作られており、個人の多様な能力すべてを反映できているとは限りません。むしろ、組織が評価していない領域に、自分の真の価値が隠れていることも多いのです。
「調整役としてチーム内の摩擦を抑えるのが得意」「部下のメンタル面を支えることができる」など、出世とは無関係な貢献が社内では埋もれてしまうことがあります。しかしこれらの能力は、マネジメント層以上に必要とされる組織の維持・発展を支える不可欠な力です。
2023年に行われたLinkedInの日本人ビジネスパーソン調査では、「会社の評価制度と自分の強みが一致していない」と感じる人が68%にのぼりました。これはつまり、多くの人が「見えない評価軸」のもとで自己評価を行っており、社内のレールから外れた瞬間に、自分の存在意義を見失ってしまう構造を物語っています。
だからこそ、自分の価値を「会社の評価」と切り離して、自身のスキル・強み・情熱を基に再構成することが重要です。これには次のような手法が役立ちます:
- 強み診断(ストレングスファインダー、VIAなど)
- ライフラインチャートでの自己分析
- 信頼できる他者からのフィードバック(360度評価)
これらの方法を用いることで、「これまで見えていなかった自分の資産」を言語化できるようになります。たとえば、「分析力」や「共感力」、「他者の才能を引き出す力」など、再評価された自分の価値をもとに、社内外での新しい役割や活動の場が拓けてくるのです。
キャリアの再構築がもたらす心理的変化と社会的影響
キャリアを再評価し、自分軸を持って行動を始めた人には、明らかに心理的な変化が見られます。
2017年に米国心理学協会(APA)が行った調査によれば、仕事に対する内発的動機(Intrinsic Motivation)が高い人は、低い人に比べて職業的満足度が2.4倍、メンタルヘルスの安定度が1.8倍高いという結果が出ています。
また、これは個人の問題にとどまらず、組織全体にも波及します。「出世以外の成功モデル」が社内で認知されれば、若手社員の多様なキャリア志向が尊重され、組織の柔軟性や離職率の改善にもつながります。
実際、リクルートワークス研究所の調査(2020年)では、「個人の強みを活かせる制度がある企業」は、そうでない企業と比べて離職率が平均で30%低下していました。
つまり、個人が自らの価値を再構築することは、単なるキャリア転換ではなく、「組織文化の多様化」「働き方のイノベーション」へとつながっていく可能性を秘めているのです。
再評価の連鎖が生み出す、新しい働き方のモデル
再評価によって人生を立て直す人が一人現れると、その変化は周囲にも連鎖的に影響を与えます。
たとえば、ある40代の管理職が出世競争から一線を引き、自身の得意とする人材育成に専念するようになった結果、部門内の若手の成長速度が飛躍的に向上し、全体の成果にも好影響を与えたという事例があります。
このように、従来の「出世=価値あるキャリア」という一元的な見方を超えて、それぞれが自分の役割を再評価し、多様な形で活躍していく社会の実現こそが、真に持続可能な働き方への一歩となるのです。
再評価とは、自分自身に対する再定義であり、同時に「社会の価値観との再交渉」でもあります。
それは時に苦痛を伴うプロセスかもしれません。しかし、その先にある「本当の納得感」と「自分らしさを活かすキャリア」は、誰にとっても代えがたい財産となるはずです。
出世だけが人生ではないと納得するための視点

現代社会において、「出世こそが人生の成功」とされる価値観は、徐々に見直されつつあります。
しかしながら、長年そのような基準で自己評価してきた人にとって、出世から外れた瞬間に感じる「敗北感」や「空虚さ」は、簡単に拭えるものではありません。だからこそ必要なのは、“出世以外にも人生の成功や充実を感じるための視点”を再獲得することです。
なぜ私たちは出世に固執してしまうのかという社会心理的背景と、それに代わる新たな人生の指針をどのように見つけることができるのでしょうか。
視点の転換は、単に感情の切り替えではなく、生き方そのものの再設計へとつながっていく重要なステップです。
出世至上主義が形成される構造的要因
戦後日本の高度経済成長期からバブル期を経て形成された「終身雇用+年功序列型モデル」では、長く勤めれば自動的に昇進し、肩書きとともに社会的信用と経済的報酬を得るという仕組みが確立されていました。
この構造は長らく多くの企業で機能してきたため、「出世=成功」という価値観が染み付いているのです。
このモデルの強固さを示すデータとして、2020年に独立行政法人労働政策研究・研修機構が発表した調査があります。そこでは「自分の仕事にやりがいを感じるか」という質問に対し、「役職が上がるほど感じる」と答えた人が65.8%に達していました。これは、肩書きが自己肯定感や仕事の満足度に直結していることを示唆しています。
また、文化的背景として、日本では「集団内での序列」が重視される傾向があります。
心理学者のヘイダーによれば、人は自己の地位や行動を他者との比較で認識する傾向があるとされており、これが「他者より上にいること=自分には価値がある」という暗黙の前提を強化しています。
しかしながら、社会構造はすでに変わりつつあります。ジョブ型雇用の導入、副業やパラレルキャリアの推進、リモートワークの普及などにより、「出世以外の軸での価値創出」が可能となった今、かつての出世至上主義は徐々に意味を失いつつあるのです。
「他者評価から自己評価へ」視点の切り替えがもたらす影響
出世に固執するのは、実は「他者からの評価」に大きく依存しているからです。これは人間の基本的な社会欲求であり否定すべきものではありませんが、それだけを拠り所にしていると、思い通りに評価されなかったときに自己価値を見失いやすくなります。
この問題に対して有効なのが、「自己承認の視点への切り替え」です。つまり、自分の中にある満足感や成長感を、他者の評価を待たずに感じ取る力を育むことです。
アメリカの心理学者マーティン・セリグマンが提唱した「PERMAモデル」(幸福の5因子)によると、人が持続的な幸福を感じるには、以下の要素が必要です。
- P:Positive Emotion(ポジティブ感情)
- E:Engagement(没頭)
- R:Relationships(良好な人間関係)
- M:Meaning(人生の意味)
- A:Accomplishment(達成感)
このうち、「出世」はAに分類される一時的な達成でしかありません。一方、E(没頭)やM(意味)に重きを置く働き方を見つけることで、出世がなくても充実した人生を送ることができるのです。
たとえば、ある企業では、50代で課長に昇進できなかった社員が、自らの趣味であった写真撮影のスキルを活かして、社内広報チームに異動。社内誌やイベント記録を担当することで、多くの社員とのつながりを深め、社内における「縁の下の力持ち」として認知されるようになった事例があります。
彼はこう述べました。「役職はないが、いまが一番会社の役に立っていると感じる」と。
このような成功体験は、自己評価が他者評価を上回ることで可能になります。
新しい評価軸としての「社会貢献」や「内面的成長」
「社会にどう貢献しているか」や「どれだけ自分が成長できているか」を評価軸に据えることも、出世一辺倒の価値観から抜け出すための有効な視点です。
これに関連する調査として、内閣府の「国民生活に関する世論調査(2021年)」では、「幸福の要因」として多かった回答が「人の役に立っている実感」(53.1%)でした。
つまり、人は「他者から褒められること」よりも、「他者に貢献しているという実感」の方が幸福感につながるのです。これは重要なポイントです。
出世競争から外れたとしても、自分の知識や経験を地域活動、NPO、学校教育支援、社内メンタリングなどに還元することで、自分の存在意義を再確認することができます。
たとえば、2010年代から大企業で広まり始めた「プロボノ制度」(職業上のスキルをボランティアとして提供する制度)は、シニア社員の意欲とスキルを社会に還元する好例です。
また、内面的な成長、たとえば「マインドフルネス」「感情の自己調整能力」「自己理解の深化」なども、近年ビジネスパーソンに重視されるようになってきました。
GoogleやSalesforceなど、世界的企業が「社内マインドフルネス研修」を制度化しているのは、「成果主義」だけでは人のモチベーションが持続しないという気づきがあるからです。
出世以外の幸福軸を持つことが生む社会的好循環
個人が出世だけに依存しない人生の軸を確立できるようになると、社会全体にも良い影響が波及します。
第一に、多様な働き方が尊重される風土が醸成されます。2022年のパーソル総合研究所の調査では、「キャリアの多様性を推進している企業」は、そうでない企業に比べて、社員の定着率が1.4倍高いという結果が出ています。
これは、出世以外の価値観が認められることで、働く人の満足度と組織へのロイヤルティが高まることを示しています。
第二に、若手社員にとっても「出世コース」以外にモデルが存在することで、将来への不安や過度な競争意識が軽減されます。これによりメンタルヘルスの維持や、長期的なキャリア形成が可能になります。
最後に、人生100年時代において、50代以降の役職定年後の人生の再設計が極めて重要となります。出世後のキャリアの行き止まりではなく、出世の有無に関わらず価値を見出す視点を持つことで、定年後も生きがいを持って社会参加を続けられるようになります。
人生の価値は「肩書き」ではなく「意味づけ」で決まる
「出世しなければ人生の敗者だ」という思い込みを手放し、人生に意味を与える多様な価値軸を持つことが、これからのキャリアには求められます。それは個人の精神的安定のみならず、組織や社会全体の持続可能性にもつながる、きわめて重要な視点です。
出世とはあくまで“選択肢のひとつ”であり、人生の主目的ではありません。私たちはいつでも、自らの価値を再定義し直す力を持っています。そしてその力こそが、認知的再評価によって生まれる「自由な視点」なのです。
自尊心の再構築に必要な視点

認知的再評価(Cognitive Reappraisal)は、物事の捉え方を意識的に変えることで感情のバランスを整える方法ですが、必ずしも全員がそれだけで職業的な自尊心を回復できるわけではありません。むしろ、それが難しいと感じる方が少なくないのが現実です。
そんなときに重要なのは、「自尊心の再構築」を職業だけに限定しないことです。
人は本来、多面的な存在であり、キャリアの成否だけでその人の価値が決まるわけではありません。以下のようなアプローチが、キャリア以外の軸から自尊心を再び築く助けになります。
1. 自己効力感を感じられる活動に取り組む
「自分はこれができる」「役に立てている」と感じる経験は、たとえ小さなものであっても、自尊心の回復に大きく貢献します。たとえば:
- 地域のボランティア活動に参加する
- 子どもの学校行事やPTA活動に協力する
- 趣味で教室を開いたり、SNSで知識を発信する
これらは他者からの評価ではなく、「自分が意味ある行動をしている」という実感をくれます。
2. 新しい「役割」を得る
「会社のポジション」が自分の役割のすべてだったと感じる人は、そこが抜けると空白感に襲われます。ですが、役割は社会のあちこちに存在しています。
- 社内で後輩育成やメンター的な立場を引き受ける
- 家庭内での支え手としての役割を再評価する
- 外部のプロジェクトやNPOでの役割を担う
特に「人の役に立っている」という感覚は、強力な自尊心の源になります。
3. 人生全体のストーリーを見直す
過去のキャリアや人生を「ストーリー」として捉え直すことも効果的です。たとえば、「出世しなかった」のではなく、「自分らしく働くことを選んだ」と再構成する。
心理学ではこれをナラティブ・セラピーと呼びます。自分の歩みを第三者的に眺め直すことで、新たな意味づけができるようになります。
4. 専門外の成長や学びに力を入れる
自尊心は「学び」や「成長実感」からも生まれます。最近では、大人の学び直し(リスキリング)や資格取得が自己肯定感の回復に効果的という調査もあります。
リクルートワークス研究所の2023年の報告では、「学び直しが自己肯定感を高めた」と答えた社会人は全体の71.4%にのぼっています。
5. 自己肯定感の源を「比較」から「内的基準」に移す
最後に大切なこととして、他人と比較する評価軸から、自分の価値観や納得感に基づく評価軸へ移行することが挙げられます。これはすぐには難しいことですが、たとえば:
- 毎日、今日よかったことを3つ書き出す「グッドポイント日記」
- 自分が感謝された場面をメモする「感謝記録」
といった習慣が、少しずつ「自分の中にある価値」を実感する手助けとなります。
自尊心の土台は「社会的成功」ではなく「自己の意味づけ」
認知的再評価がうまくいかないときは、自分に合った別のアプローチを見つけることが重要です。キャリアはあくまで人生の一部であり、自尊心の全てではありません。
むしろ「自分がどう生きたいか」「誰とどう関わりたいか」という問いの方が、より本質的な自尊心の源になります。
自分の価値は、職位でも他人の評価でもなく、「自分がどれだけ自分を大切にできるか」によって決まるのです。
★この記事について:質問と答え
Q1. 出世コースを外れたと感じたとき、自分の価値をどう見直せばいいですか?
A. 出世という他者評価軸から自分を切り離し、「自分が何に貢献し、誰に喜ばれているか」を見つめ直すことが重要です。認知的再評価を活用すれば、「出世していない=価値がない」という思考のフレームを解きほぐし、自分らしいキャリアの意味づけが可能になります。
Q2. 認知的再評価って具体的にどんな方法なの?
A. 認知的再評価とは、自分の置かれている状況や出来事の意味を、別の視点で捉え直すことで感情のバランスを取る心理的手法です。たとえば「昇進できなかった」経験を、「自由に自分のスキルを活かすチャンス」や「他者を支える役割」として再解釈することで、ネガティブな感情を軽減できます。
Q3. 自己肯定感がどうしても回復しないときは、どうすればよい?
A. 無理にポジティブに捉え直そうとせず、「悔しさ」や「不安」といった感情を受け入れることも大切です。そのうえで、自分にとって本当に大切な価値観や強みに目を向け、役割や意味を再構築するプロセスが有効です。カウンセリングやコーチングの活用も選択肢になります。
▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。


▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。





