「やりたいことがわからない」「将来が不安だ」と感じている人は多いのではないでしょうか。日本の教育では、長い間「正しい答えを早く導き出すこと」が重視されてきました。そのため、「自分で考え、行動する力=エージェンシー」が十分に育っていないのではないかという指摘が増えています。
たとえば、学校の授業では「答えが決まっている問題」を解くことが多く、自分で質問を考えてみる経験は少ないかもしれません。テストの点数や偏差値が重視されますが、「自分が本当にやりたいことは何か?」「それを実現するためにはどうすればいいのか?」を深く考える機会はあまりないのではないでしょうか。
社会に出ると、決まった答えのない問題に直面することがほとんどです。それなのに、「答えがないと不安」「指示がないと動けない」と感じることが多いのではないでしょうか。もし、自分で考えて行動する力をもっと早くから育てていたら、未来への不安は減り、自信を持って生きることができるかもしれません。
自ら考え行動する力「エージェンシー」と教育の重要性

エージェンシーとは何か?
「エージェンシー(Agency)」とは、学習者が自分で目標を設定し、主体的に学び、責任を持って行動する力のことを指します。この考え方は、OECD(経済協力開発機構)が提唱する「Education 2030」においても重要な要素とされています。エージェンシーは、単に自発的に学ぶ姿勢を持つことだけでなく、自らの行動を通じて周囲や社会に影響を与える能力も含まれています。
この概念を理解するためには、「受動的な学び」との違いを考えるとわかりやすいです。受動的な学びは、教師や親などの指示に従って知識を得る学習方法で、日本の教育では伝統的に重視されてきました。一方、エージェンシーのある学びでは、学習者自身が「何を学ぶか」「どう学ぶか」を決定し、試行錯誤しながら学びを深めていきます。
エージェンシーが求められる背景
なぜ今、エージェンシーが重要視されるようになったのでしょうか?その理由の一つに、社会の変化があります。従来の教育システムは、決められた知識やスキルを効率よく身につけることを目的としていました。しかし、社会が変わる中で、決められた知識を覚えるだけでは対応できない場面が増えてきています。
たとえば、ビジネスの現場では、指示を待つのではなく、自ら問題を見つけて解決策を考える力が求められます。ある調査によれば、企業の採用担当者の78.3%が「主体的に学ぶ姿勢を持つ人材を求めている」と回答しています(日本経済団体連合会「2023年企業の採用と教育に関する調査」より)。さらに、別の調査では、「指示待ちの姿勢が目立つ新入社員が増えている」と感じる企業は62.5%に上るとも報告されています(リクルートワークス研究所調査)。
これらのデータからもわかるように、現代社会では、自ら考え行動できる力を持つことが個人にとっても企業にとっても重要になっています。そのため、教育の場でもエージェンシーを育むことが求められています。
日本の教育におけるエージェンシーの課題
しかし、日本の教育では、エージェンシーを十分に育てる環境が整っているとは言えません。特に、日本の子どもたちは自己肯定感が低いという課題があります。内閣府が行った「子ども・若者白書(2022年)」によると、「自分に価値があると感じる」と答えた日本の若者は45.8%で、欧米諸国(アメリカ84.0%、ドイツ67.7%、フランス72.5%)と比べてもかなり低い水準です。
この自己肯定感の低さは、「自分の考えを持つことへの不安」や「自分で決めることへの消極性」にもつながります。つまり、エージェンシーを発揮するためには、まず「自分の考えを持ってよい」「自分で決めてもよい」という感覚を育てることが重要です。しかし、日本の教育では「間違えることを恐れる風潮」や「正解を求める傾向」が強く、自由に考え、試行錯誤する機会が限られています。
エージェンシーを育むために必要なこと
エージェンシーを育てるためには、教育の現場でどのような取り組みが必要なのでしょうか?まず重要なのは、「学習者自身が意思決定をする機会を増やすこと」です。以下のような方法があります。
- プロジェクト型学習(PBL: Project-Based Learning)の導入
教師が課題を与えるのではなく、生徒自身が課題を設定し、解決策を考える学習方法です。これにより、主体的に考え行動する力を養うことができます。 - 選択肢のある学習の提供
教科書の内容を一方的に教えるのではなく、生徒が学び方を選べるようにします。たとえば、「この単元をどうやって学ぶか?」を生徒自身に決めさせることで、学習の主体性を高めることができます。 - 間違いを許容する環境づくり
日本の教育では「間違えること=悪いこと」とされがちですが、エージェンシーを育むためには、「間違えながら学ぶ」ことをポジティブに受け入れる文化が必要です。
エージェンシーを育てることは、単に学習の効率を上げるだけでなく、社会に出たときに自ら考え行動できる力を養うことにつながります。そのためには、教育のあり方を見直し、子どもたちが自ら考え行動する機会を増やしていくことが重要です。
レオナルド・ダ・ヴィンチの若い頃と主体的な学びについて
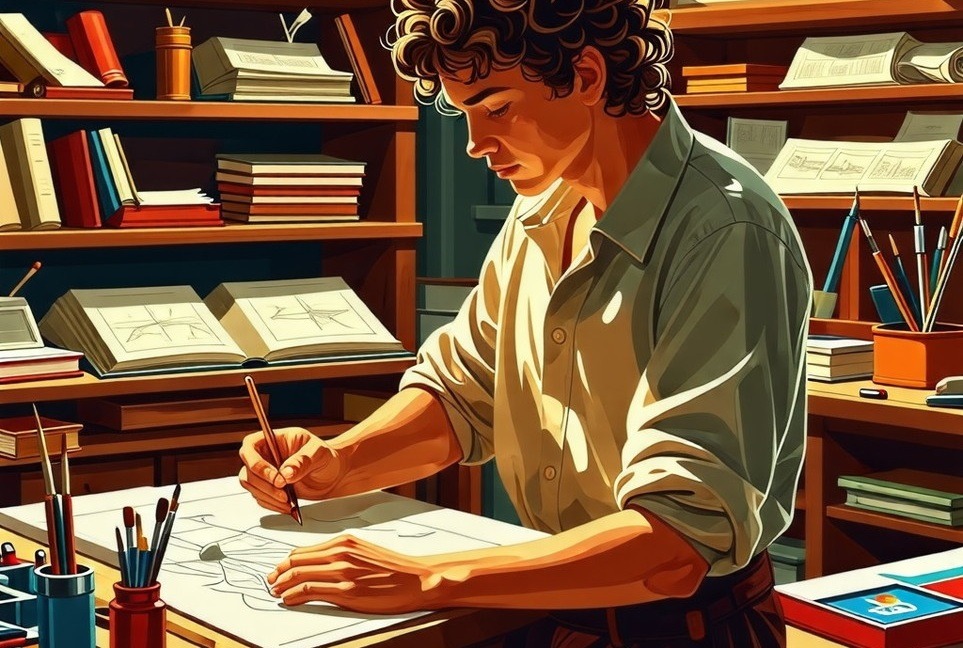
幼少期の環境と学びのスタイル
レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)は、イタリアのフィレンツェ近郊にあるヴィンチ村で生まれました。彼は正式な高等教育を受けることなく育ちましたが、幼いころから優れた観察力と探求心を持っていました。父親は公証人であり、母親は農民の出身だったため、当時の主流であるラテン語や古典文学の教育を十分に受けることができませんでした。しかし、レオナルドはこれを不利とは考えず、自ら学ぶことに強い興味を持ちました。
彼の幼少期の特徴は、自然の中で多くの時間を過ごしたことです。森や川辺で昆虫や動物、植物を観察しながら、「なぜこうなっているのか?」という疑問を持ち続け、その答えを自ら探しました。このような学びの姿勢が、後の多様な研究につながっていきます。
また、彼は多くのスケッチを残していますが、これらは単なる模写ではなく、物体の構造や動きの仕組みを理解しようとする試みでした。水の流れや鳥の羽ばたき、人体の筋肉の動きを詳細にスケッチし、自然界の法則を読み解こうとしました。この「自ら問いを立て、観察し、記録し、分析する」という学びのスタイルが、彼の才能を開花させる要因の一つです。
工房での学び方は、主体的な探求
14歳の頃、ダ・ヴィンチはフィレンツェの芸術家アンドレア・デル・ヴェロッキオの工房に弟子入りしました。当時の工房での教育は、現在の学校とは異なり、体系的な講義ではなく、実践を通じて技術を学ぶものでした。彼は単に与えられた課題をこなすだけでなく、師匠や周囲の職人たちの技術を観察し、自らの手で試行錯誤を繰り返しました。
彼は絵画の技術だけでなく、解剖学や光の屈折、遠近法についても深く研究しました。ヴェロッキオ工房では、彫刻や建築設計、金属加工などさまざまな技術が教えられ、ダ・ヴィンチはそのすべてに興味を持ち、貪欲に学びました。彼が16歳の頃に描いたとされる『キリストの洗礼』(1470年代)では、彼が担当した天使の部分が師匠ヴェロッキオの描いた部分よりも優れていたと言われています。このことが、ヴェロッキオが「もう絵を描くのをやめる」と言ったという逸話を生むことになりました(実際には、その後もヴェロッキオは制作を続けています)。
ノートによる知識の蓄積と実験の繰り返し
ダ・ヴィンチの学びのもう一つの特徴は、徹底した記録へのこだわりです。彼のノートには、解剖学的なスケッチや建築の設計図、機械の構造図、哲学的な考察がびっしりと記されています。彼は推定13,000ページ以上のノートを残したとされ、その多くが詳細な観察と考察の記録です。
彼は単に知識を記録するだけでなく、自らの考えを検証するために実験を繰り返しました。例を挙げると、彼のノートには「鳥はどのように飛ぶのか?」という疑問に対する詳細な考察が記されています。彼は翼の動きや空気抵抗の影響を分析し、飛行機械の設計に挑戦しました。彼がスケッチした飛行機械の設計図は、現代の航空技術にも影響を与えたとされています。
また、彼は人体の構造にも強い興味を持ち、遺体解剖を行いながら筋肉や骨格の構造を詳細に記録しました。彼の解剖学的スケッチは、当時の医学書よりも正確であるとされ、のちの解剖学の発展に影響を与えました。彼の研究は美術作品にも反映されており、『モナ・リザ』(1503-1519年)や『最後の晩餐』(1495-1498年)のリアルな表現は、彼の解剖学的な知識と観察力によるものです。
主体的な学びがもたらした成果
ダ・ヴィンチの学びの姿勢は、単に知識を蓄えるだけでなく、実際に試し、改良しながら発展させる点に特徴があります。彼の「主体的な学び」は、芸術、解剖学、物理学、工学などの多様な分野で成果を上げる基盤となりました。
彼の記録には、「経験はすべての知識の源である」という言葉が残されています。これは、受け身の学習ではなく、自ら体験し、考え、試すことが本当の知識につながるという考え方を示しています。この姿勢が、彼が一つの分野にとどまらず、多くの領域で革新的な発見を成し遂げた理由の一つといえるでしょう。
また、彼の学びの方法には現代の教育にも通じるヒントがあります。ダ・ヴィンチは、自分の興味に基づいて学ぶことを最優先にし、得た知識をすぐに実践し、それをノートに記録するというサイクルを繰り返していました。これは、現在の「探究型学習」や「アクティブラーニング」の考え方に通じています。
ダ・ヴィンチの学びの姿勢は、どの時代においても重要な示唆を与えてくれます。彼の人生を振り返ると、主体的に学ぶことがどれほど成果を生むかがよく分かります。
アンドリュー・カーネギーの成功と若いころの経験

移民としての出発点と厳しい労働環境
アンドリュー・カーネギー(1835-1919)は、スコットランドの貧しい織工の家庭に生まれました。当時のスコットランドでは織物産業が機械化され、多くの職人が仕事を失っていました。カーネギーの父親もその一人で、家族は生活に苦しみ、1848年にはカーネギーが13歳のときにアメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグに移住しました。
移住した当初、カーネギー家の経済状況は厳しく、彼はすぐに働き始める必要がありました。最初の仕事は繊維工場での糸巻き作業で、1週間の労働時間は72時間、週給はわずか$1.20(現在の価値で約$40)という過酷なものでした。このような劣悪な環境で、彼は「ただ働くだけでは抜け出せない」という現実を痛感しました。
その後、彼は14歳で電報会社の使い走りの仕事を得ます。この仕事は当時としては良い待遇で、週給は$2.50(現在の価値で約$85)に増えました。しかし、それ以上に重要だったのは、彼がここで「情報の価値」を学んだことです。電報会社では、鉄道会社や商社の経営者たちが交わす重要な通信を目にする機会があり、ビジネスの世界に触れることができました。
読書週間がもたらす自己教育の習慣
カーネギーの成功の土台は、彼の「自己教育」への強い意志にありました。家は貧しく、学校に通う余裕がなかった彼は、独学を決意しました。当時のピッツバーグには公立図書館がなく、労働者階級の子どもたちには本を借りる機会がありませんでした。しかし、カーネギーは裕福な実業家・大佐ジェームズ・アンダーソンが自宅の蔵書を週に一度、労働者に開放していることを知り、毎週本を借りて読書に没頭しました。
彼はこの機会を最大限に活用し、歴史、経済、政治、文学など幅広い分野の本を読みました。後に彼は「この図書館がなければ、自分の人生は違ったものになっていただろう」と語っています。この経験が、後のカーネギーの「図書館建設運動」につながったことはよく知られていますが、何よりも彼が知識を得ることが貧困から抜け出す手段であると確信した点が重要です。
鉄道業界での台頭と戦略的な行動
カーネギーが16歳のとき、彼の人生を大きく変える出来事が起こります。それは、鉄道会社「ペンシルベニア鉄道」の社長、トーマス・スコットの目に留まり、彼の個人秘書兼電報係として雇われたことです。この仕事により、カーネギーは鉄道事業の中枢に近い位置で学ぶ機会を得ました。
ここで彼は鉄道業界の仕組みを徹底的に学び、特に「コスト削減と効率化」に注目しました。彼は鉄道の運営に関するデータを分析し、運行の遅れやコストの無駄を減らす方法を考案しました。その結果、彼は短期間でスコットの信頼を勝ち取り、19歳で管理職に昇進しました。この年齢での管理職就任は当時としては異例で、彼の優れた観察力と戦略的思考が評価された証です。
また、彼は給与を使うだけでなく、「投資」という概念を学びました。スコットの助言により、彼は最初の投資として$500(現在の価値で約$15,000)を鉄道会社の株式に投じました。この投資は成功し、カーネギーは「お金に働かせる」ことの重要性を学びました。
鋼鉄業界への進出とその後の成功の要因
カーネギーは鉄道業界での経験を活かし、1860年代に鉄鋼業に進出します。彼の成功の要因は、「垂直統合」と「技術革新」という2つの戦略にあります。
- 垂直統合戦略
当時の鉄鋼業界では、原材料の調達から製造、流通まで多くの企業が関与していました。しかし、カーネギーはすべての工程を自社で管理する「垂直統合」モデルを採用しました。これにより、コストを大幅に削減し、市場での競争力を強化しました。実際、カーネギーの会社が生産する鋼材の価格は業界平均の約30%低いとされ、彼は市場を支配することに成功しました。 - 技術革新と生産性向上
カーネギーは新技術の導入にも積極的でした。彼はイギリスで開発されたベッセマー製鉄法に注目し、この技術を早い段階でアメリカに導入しました。これにより、鋼鉄の生産コストが50%以上削減され、供給量が飛躍的に増加しました。彼の会社は短期間でアメリカ最大の鉄鋼メーカーへと成長し、1890年代にはアメリカ国内の鉄鋼市場の約60%を支配するに至りました。
若年期の経験が成功に与えた影響
カーネギーの若年期の経験は、彼の成功に影響を与えています。
- 貧困と労働の経験 → 努力と自己教育の重要性を学ぶ
- 読書習慣と自己教育 → 知識を武器にし、成長の機会をつかむ
- 鉄道業界での経験 → ビジネスの仕組みを理解し、投資の重要性を学ぶ
- 技術革新と戦略的思考 → 垂直統合とコスト削減の戦略を実践
彼の人生は、「学び続けること」と「環境を最大限に活かすこと」によって築かれたものであり、若いころの主体的な学びと経験が成功の基盤となったことは明らかです。
★この記事について:質問と答え
Q1:「エージェンシー(主体的な学び)」とは具体的にどのようなことを指すのですか? 子どもが自分で学ぶとはどういうことなのでしょうか?
A.
エージェンシーとは、学習者が「自らの意思で学びの目標を立て、学び方を選び、他者と協力しながら行動する力」を指します。たとえば、学校の授業だけでなく、自分で課題を見つけたり、興味のある分野について図書館やネットで調べたりする行動も、エージェンシーの一つです。教師や親に「こうしなさい」と言われて動くのではなく、「なぜそれを学びたいのか」「どうすればできるのか」を自分の言葉で考え、実行に移せる姿勢が含まれます。
Q2: レオナルド・ダ・ヴィンチやアンドリュー・カーネギーの若年期には、どんな共通点があったのですか?
A.
両者に共通していたのは、「貧しい環境下でも自ら学び続けた」という点です。ダ・ヴィンチは正規の教育を受ける機会が限られていた中で、観察とスケッチを通じて自然や技術に関する理解を深めました。一方カーネギーは、図書館に通い詰めて幅広い知識を独学で習得し、仕事でも積極的に学びを実践しました。つまり、知識が与えられるのを待つのではなく、自ら進んで環境を活かして学ぼうとした姿勢が、成功の原点にあったのです。
Q3:なぜ今、日本の教育でエージェンシーが求められるようになったのでしょうか? これまでの教育と何が違うのですか?
A.
日本の従来の教育は、知識の詰め込みや正解を求める画一的な学習が中心でした。しかし社会では、変化に柔軟に対応し、自分で考えて動く力が重視されるようになっています。文部科学省も「主体的・対話的で深い学び」を推進しており、「自分の考えを持ち、学びを他者と共有・発展させる力」=エージェンシーが重要視されてきました。つまり、受け身の学びから脱し、自分ごととして学びに関わる姿勢が、教育の中心に置かれるようになってきたのです。
▼▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。
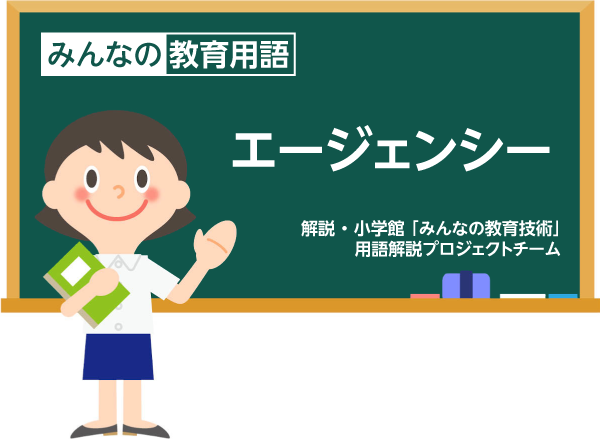

▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。






