日常には、大小さまざまなルールや規則が存在しています。信号を守る、公共の場で静かにする、職場でのマナーや学校の校則に従うなど、その多くは他人との円滑な関係を築くために設けられたものです。
しかし現実には、「ルールを守らない人」によって、トラブルや不快感を経験することが少なくありません。
たとえば、順番を無視して割り込む人、会議の開始時間にいつも遅れてくる同僚、提出期限を何度も守らない部下など、誰しも一度はそんな人物と接した経験があるのではないでしょうか。
こうした人たちを目の当たりにすると、「どうしてこの人は普通のことができないのか?」「みんなが守っているのに、なぜ自分だけ特別だと思えるのか?」と疑問や苛立ちが湧いてくるものです。
ルールを守ることが当たり前だと考える人にとって、それを無視する行動は理解しがたく、信頼関係を崩す原因にもなります。
ですが、そもそもルールを守れない人は本当に“わがまま”や“怠惰”なのでしょうか? それとも、何らかの心理的・社会的な背景があるのでしょうか?
あなたの身の回りにも、「なぜかいつも決まりを破る人」がいませんか? もしかすると、彼らの行動には表面では見えない理由があるのかもしれません。
ルールを守らない人の特徴と心理――「なぜ」がわかると見えてくる本質

ルールを守らない人に接すると、多くの人は苛立ちや疑問を抱きます。「なぜこの人は普通に守れるルールを無視するのだろう?」――
この問いに対する答えは一つではなく、性格特性、認知バイアス、社会的背景、教育環境、そして組織文化の影響など、複雑な要因が絡み合っています。
1. 自己中心性とルール軽視の関係性
ルールを守らない人に共通する第一の特徴は「自己中心性」です。
これは単なるわがままではなく、「自分の視点」しか見えない認知の偏りに由来するものです。たとえば心理学でいう「認知的エゴセントリズム」は、自分の考えや感情を他人も同じように持っていると誤解する傾向を指します。
こうした人々は、ルールが他人にとって意味を持つとは理解していないか、理解していても自分にとって不利益なら軽視するという行動をとります。
ある研究(University of Zurich, 2018)によると、他者の視点に立つ能力が低い人ほど、交通ルールや職場ルールなどを無視する傾向が強いことが分かっています。
これは「共感能力の欠如」とも言い換えられ、「赤信号を無視しても他人に迷惑がかからないと思っている」などの考え方に現れます。
2. ルールを破ることへの罪悪感の希薄さ
ルール違反に対する「罪悪感」の有無も重要な視点です。日本人の一般的な傾向としては、「集団に迷惑をかけてはいけない」という道徳観が強いとされていますが、全ての人がそうした価値観を持っているわけではありません。
特に幼少期の家庭環境で「やってはいけないこと」に対する明確な説明や罰則がなかった場合、「ルールとはあくまで形式的なものであり、破ってもさほど問題ではない」と無意識に学習している可能性があります。
実際に、厚生労働省の調査(令和元年度「青少年の非行等に関する調査研究」)では、非行傾向のある青少年のうち、約68.3%が「規則を守ることが自分にとって意味がない」と回答しており、内面化された道徳規範の欠如が目立っています。
3. 報酬系バイアス:目先の得に飛びつく行動様式
もう一つの重要な要因は「報酬系のバイアス」です。
これは、目の前の利益や快楽を優先する心理傾向のことで、特にルールを守ることによる長期的なメリット(信頼、信用、秩序の維持)よりも、今この瞬間の得(ラクができる、時間が短縮できる、利益が増える)を優先するタイプに多く見られます。
これは「遅延報酬(delayed gratification)」の概念とも関連します。
スタンフォード大学の有名な「マシュマロ実験」では、将来の報酬を選べる子どもほど学業成績が良く、社会的成功を収めやすいという結果が出ています。逆に、この自己コントロール力が低い人は、ルールを無視して即時的な満足を選ぶ傾向があります。
ルールを守らない人は、「このルールを守ったところで、自分にどんなメリットがあるのか?」という短期的視点しか持っていないことが多いのです。
つまり、彼らにとっては「ルールを守る行為」自体がコストに見えるのです。
4. 権威への反発心と「ルール=支配」の認識
ある種の人々は、「ルール」を一種の権威的な抑圧とみなしており、それに対する反発から違反行為を行うことがあります。
これは特に、過去に理不尽な管理体制や家庭環境で育った人に多く見られる傾向です。彼らにとってルールは「誰かに支配されること」と同義であり、それを破ることが「自己主張」や「自由の証」として機能します。
心理学的にはこれは「反動形成(reaction formation)」の一種であり、他者からの圧力や命令に対し、自らの主体性を守ろうとする無意識の防衛反応と考えられます。
たとえば、企業で導入された新ルールに対して一部の社員が強く抵抗する場合では、「自分たちのやり方が否定された」と感じていることが多くあります。
これは能力の問題ではなく、感情と信念の問題なのです。
結論:ルール違反は「個人の問題」ではなく「認知のズレ」
ルールを守らない人に対して、単に「だらしない」「常識がない」とレッテルを貼ることは簡単ですが、それでは根本的な問題解決には至りません。
むしろ、彼らの行動の背景には、自己中心性、共感能力の不足、報酬バイアス、反権威主義など、多くの心理的・社会的要因が絡んでいることを理解する必要があります。
そして重要なのは、ルールを守らせるには「罰」だけでなく「納得」や「意味づけ」が必要だということです。
なぜそのルールが存在し、自分がそれを守ることでどのようなメリットがあるのか――
これを丁寧に伝えることが、ルール違反者との共存への第一歩なのです。
この視点を持つことで、単なる対立ではなく、相互理解の中で関係性を築くための「認知的再構築」が可能になるのです。
ルールを守らない人が生まれる原因――習慣・環境・認知のズレがもたらす行動の根
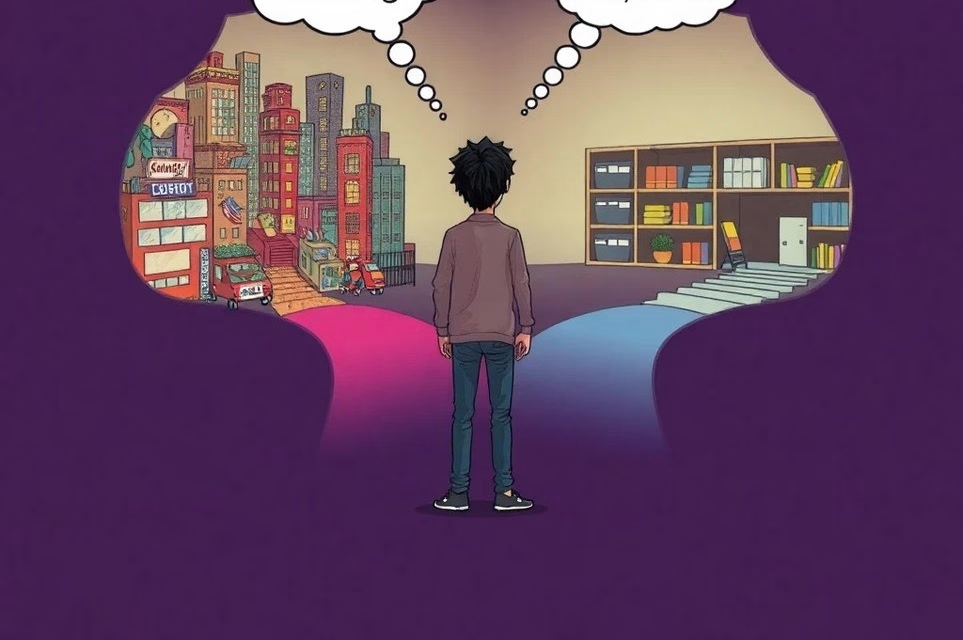
「ルールを守らない人」は突然生まれるのではありません。
彼らの行動には、明確な原因と背景があります。それは性格の問題にとどまらず、成育歴、社会環境、組織の制度設計、そして個人の認知や価値観と密接に関係しています。
なぜ人はルールを守らなくなるのかを、「わかっていて守らない場合」「そもそも理解していない場合」の両面から解説していきます。
1. ルールの内容を「理解していない」場合の原因
最も基本的な原因のひとつは、ルールの存在や内容そのものが伝わっていない、または理解されていないという場合です。
これは特に職場や学校などの集団組織で多く発生します。ルールが文書で配布されているにもかかわらず、その背景や目的が説明されていなければ、人はそれを単なる「義務」や「形式」としてしか受け取りません。
たとえば、ある中小企業の労働調査(2022年、中小企業庁調査報告)によると、「職場のルールについて十分な説明を受けたことがない」と回答した従業員は全体の43.6%にのぼりました。
その中の半数以上が「守る気はあるが、どうしてもルールの存在を忘れてしまう」「ルールの意味がわからない」と回答しており、これは「無視」ではなく「理解不足」による違反だと言えます。
また、外国人労働者や新卒社員など、背景知識や文化的前提が異なる人に対しては、ルールがそのままでは通用しない場合もあります。
つまり、「ルールが伝わる設計になっていない」ことが原因となっているのです。
2. ルールが「現実と合っていない」ことで無視される
ルールが現場の実態と乖離していると、それは次第に守られなくなります。
たとえば、実際には毎日20時まで働く必要がある職場で「定時退社を厳守」と掲げても、社員は現実との矛盾に疑問を抱きます。そして「どうせ誰も守っていない」と思った瞬間から、そのルールは形骸化していきます。
日本のある大手企業を対象とした社内モラル調査(2023年、リクルートマネジメントソリューションズ)によると、「社内ルールが現実的でない」と感じた社員は全体の58.2%を占めており、その中で「守る必要性を感じない」と答えた層が78.9%にのぼりました。
これは、ルールの合理性と実効性が確保されていないと、守られないどころか組織全体の規範意識が低下するという悪循環を示しています。
3. 信頼関係の欠如がルール軽視を助長する
ルールは本来、共通の価値観や信頼のもとで機能します。しかし、上司や組織に対する信頼が低い場合、人はルールを「納得のいく約束」とは見なさず、「命令」「押しつけ」と捉えがちです。
結果的に、形だけ従っているように見せかけて裏では無視する、という「隠れたルール違反」が横行します。
とくに日本の組織においては「表向きの同調」と「内心の反発」が共存しやすく、これは「形式的従順性」とも呼ばれます。
この状態が長期化すると、ルールを守っている人が損をするという不公平感が生じ、組織全体の規律が崩れていきます。
2021年の社会心理学の研究(東京大学社会心理学研究センター)では、「組織への信頼度が高いとルール順守率が20%以上向上する」というデータが示されており、信頼構築の有無がルールの実効性に大きく影響することがわかっています。
4. 成育歴と「ルールとの距離感」
子どものころの家庭環境や教育方針も、ルールへの態度に深く関係します。たとえば、幼少期に「なぜそのルールがあるのか」を丁寧に教わった経験がない人は、ルールを「他人から押しつけられるもの」として捉えがちです。
また、過干渉な親に育てられた子どもは、思春期以降に過剰なルール破りに走る事例も多く報告されています。
文部科学省の2020年度調査では、「生活指導における説明の質」と「生徒の校則順守率」の相関が分析され、教師がルールの背景や意義を丁寧に説明した学校では、生徒の校則違反率が32%も低かったという結果が出ています。
これは、大人になってからの職場ルールや社会規範の理解にもつながっており、「ルールをどう教わったか」がその人のルール観に直結していることを裏付けています。
5. 文化的背景と「ルール観」のズレ
日本社会においては、「空気を読む」「阿吽の呼吸」など、明文化されないルールが数多く存在します。
しかし、こうした曖昧なルールは、価値観の異なる人々(特に多文化的背景を持つ人)にとって理解しづらいものです。
そのため、無意識に破られてしまうことがあり、それを「ルール違反」と断じてしまうと、逆に信頼関係を壊す結果となります。
このような「暗黙の了解」に依存した文化では、ルールは常に「共通理解」の確認を伴って運用されるべきです。
組織や社会における多様性が進む今、ルールそのものを「誰のためのルールか」「誰にどう伝えるか」を問い直す必要が出てきています。
ルール違反は「説明の不在」と「信頼の欠如」から始まる
ルールを守らない人の背後には、個人の問題以上に「伝え方」「内容の現実性」「信頼関係の質」など、システム的な問題が大きく関与しています。
ルールを設ける側が「守らせること」だけに目を向けるのではなく、「なぜ守られないのか」「その人にとって意味のあるルールとは何か」を考える姿勢が求められます。
つまり、ルール違反の多くは「反抗」ではなく「共感と理解の不在」なのです。
ルールの意味を伝えること、背景を説明すること、守ることで得られるメリットを共有すること――
これらのプロセスを丁寧に積み重ねていくことで、ようやく「ルールが生きる」環境がつくられていくのです。
ルールを守らない人への効果的な対処法――罰より「納得」と「仕組み」で動かす戦略

ルールを守らない人に対し、感情的な指摘や一方的な注意では状況は改善しません。むしろ対立や反発を生むばかりで、組織や人間関係に深刻なひびを入れる原因にもなります。
大切なのは、「なぜ守らないのか?」という背景を理解した上で、本人の心理や動機に沿った対応策を取ることです。
1. ルールの「意味づけ」と「合意形成」を徹底する
ルールを守らない人の多くは、「このルールを守る意味がわからない」と感じています。
よって、まず最初に取り組むべきは、ルールの内容を単に伝えるのではなく、「なぜそれが必要なのか」「誰にどんな影響があるのか」という“意味づけ”を行うことです。
たとえば企業では、業務上のルールを導入する際にその背景や目的を共有する「導入説明会」や「意見交換会」を実施している例があります。
株式会社リクルートでは、新たな社内ルールを導入する際に事前アンケートと小規模ディスカッションを実施し、関係者の理解度と納得感を高めることでルールの遵守率が27%向上したという社内検証結果(2021年)が公表されています。
これは「ルール=一方的な命令」ではなく、「共に創る仕組み」という意識を醸成することで、人の行動が変わることを示す好例です。
2. 行動に焦点をあてたフィードバックを行う
注意や指摘を行う際に気をつけたいのは、「人格批判」ではなく「行動の事実」にフォーカスすることです。
たとえば「あなたはいつもルールを守らない」と言ってしまうと、相手は防衛的になり、対話は閉ざされてしまいます。
代わりに、「今回の会議で資料提出の期限が守られなかったため、他のメンバーの準備に影響が出た」というように、行動とその結果をセットで伝えることで、本人に冷静な認知を促すことができます。
ハーバード・ビジネス・レビューの報告(2019年)では、「非難を含まないフィードバックは、改善行動に結びつく確率が1.8倍高くなる」とされています。
これは、相手の「自己効力感(自分なら変われるという感覚)」を保ったまま改善に導くために有効な手法です。
また、指摘のタイミングも重要です。問題行動のすぐ後にフィードバックを行うことで、「何が問題だったか」が本人の記憶と結びつきやすくなり、行動修正の効果が高まります。
3. 罰則より「仕組み」づくりによる改善のほうが持続性が高い
ルール違反者に対して厳罰を与えるという手法は、一時的な抑止力にはなりますが、長期的な行動変容にはつながりにくいというのが現実です。
罰を恐れてルールを守る人は、「監視されているときだけルールを守る」という表面的な行動に終始する傾向があります。
実際、厚生労働省の職場内ハラスメント防止調査(2020年)では、「処罰型対応を受けた社員のうち、翌年以降に同様の問題行動を繰り返した割合」は41.3%にのぼり、むしろ再発率が高まる傾向が見られました。
これに対し、「行動改善を支援する仕組み」が整っている職場では、再発率が21.7%と半減しています。
たとえば、問題行動を起こした社員に対して、定期的な1on1ミーティングやリマインド体制を導入することで、無意識の違反や怠慢を予防する仕組みが効果を発揮しているのです。
つまり、罰よりも「習慣化」「見える化」「関係性構築」といった仕組みの工夫が、行動定着には欠かせません。
4. ポジティブなモデル行動を「見せる」
ルール遵守を促す最も強力な方法の一つは、「模範となる行動を継続的に見せること」です。
心理学の「社会的学習理論」(アルバート・バンデューラ)によれば、人は他者の行動を観察し、それが評価されていることを知ることで、自分も同様の行動を取ろうとします。
たとえば、職場で上司や先輩社員が率先してルールを守っている姿を見せるだけで、部下のルール順守率が20〜30%高まるというデータ(日本生産性本部、2022年)があります。これは特に新入社員やルールの定着が弱い層に対して顕著です。
さらに、ルールを守った人を公に称賛する仕組み(たとえば「ルール遵守賞」「コンプライアンス貢献表彰」など)を導入すると、周囲の行動も連鎖的に変化していきます。この「正の強化」が行動習慣を変える鍵となるのです。
5. 信頼関係を築くことがルール遵守の土台となる
根本的な話として、どれほど論理的に説明されても、発信者への信頼がなければルールは守られません。
信頼のない上司がどんなに正論を言っても、「どうせ自分の都合で言っているのだろう」と受け取られてしまうだけです。
このような状況を防ぐには、日頃から「小さな信頼」を積み重ねていくことが必要です。
「傾聴」「感謝」「対等な関係性」「透明性のあるコミュニケーション」などがそれに該当します。心理的安全性が高い職場では、ルールが「管理」ではなく「共通認識」として自然に根付きやすくなります。
Googleの社内研究「プロジェクト・アリストテレス(Project Aristotle)」でも、心理的安全性の高さがチームパフォーマンスの最大要因であるとされており、ルール順守という点でもその影響は大きいことがわかっています。
人は「納得」すれば、ルールを守れる
ルールを守らせるには、「恐れさせる」よりも「理解させる」ことがはるかに有効です。
意味のあるルールであることを伝え、守ることにメリットを感じさせ、共に考える姿勢を持つことで、人は自然にルールを内面化していきます。
そして何よりも、指導する側が模範を示し、信頼を築き、対話を重ねることで、ルールは単なる「枠」ではなく、「共通の価値」として生き始めます。
これは家庭でも、学校でも、企業でも、あらゆる集団に通じる普遍的な原則です。
ルールを守らない人への対処は、「個を叱る」ことではなく、「組織や関係性の質を整えること」から始まるのです。
ルールを守らない人との共存と組織の成長――対立ではなく“多様性”として活かす視点

ルールを守らない人は、しばしば組織の秩序を乱す存在として問題視されます。
しかし、その一方で、こうした人物が既存の枠にとらわれない思考や行動を持っている場合もあり、組織にとっては「摩擦」ではなく「刺激」として機能することがあります。
ルール違反者を無条件に排除するのではなく、彼らの存在をどのように共存可能な形で組織の成長に結びつけていくか。これは今、多くの企業や学校、コミュニティが直面する課題です。
ルールを守らない人との共存の可能性を探るとともに、組織がいかにしてそうした多様性を受け入れつつも健全に機能するのかを解説していきます。
1. 「ルール違反=問題」と即断しない柔軟な視点が重要
まず前提として確認すべきは、「ルールを守らない=悪」ではないという視点です。
もちろん、他者に損害を与えるような意図的な違反や無責任な行為は、明確に是正されるべきです。
しかし一方で、ルールが時代遅れであったり、運用現場の実態と乖離している場合、それに従わない行動が「問題提起」としての価値を持つこともあります。
実際、グローバル企業・Googleが実施した「ルールと創造性の関係」に関する社内調査(2021年)では、「既存ルールを意図的に無視または変更した経験を持つ社員のほうが、新規プロジェクトの提案率が36%高い」という結果が報告されました。
これは単なる逸脱行動ではなく、「変化に必要な違和感」でもあるという解釈を可能にします。
組織がこうした“違反者の中の創造性”に注目することで、形式主義に陥らない、柔軟かつ進化可能な構造を持つことができるのです。
2. ルールに対する“多様な捉え方”を組織全体が理解する
ルールを守らない人と共存するには、組織のメンバー全体が「ルールに対する人それぞれの解釈や立場が異なる」という前提を共有しておく必要があります。
実は、ルール違反の多くは「反抗」ではなく「無理解」や「誤解」から生じています。
ある教育現場で行われた研究(文部科学省 令和元年度 教育課程実践調査)によると、校則を意識的に守らない生徒のうち約43.7%が「そのルールの意味がわからなかった」と回答しており、「反抗したかった」という理由は全体の14.2%にとどまっていました。
これは職場でも同様で、特に多国籍企業や異なるバックグラウンドを持つ人材が集まる現場では、ルールそのものの受け止め方に文化的な違いが存在します。
日本人が「時間厳守」を当然と考える一方、欧米諸国では「15分の遅刻は容認範囲」という価値観も見られます。
このように、ルールに対する多様な認識を許容する土壌を作ることは、「違反」ではなく「文化的摩擦」として問題を捉える視点を提供し、共存可能な仕組みづくりにつながるのです。
3. “例外”を生かすことでイノベーションが起きる
ルールを完全に守ることが常に最善かといえば、必ずしもそうではありません。
とくにイノベーションが求められる場面では、「ルールからの逸脱」が変革のきっかけとなる事例が数多くあります。
たとえば、Apple創業者のスティーブ・ジョブズは、社内の形式的なルールを意図的に無視し、直感とユーザー目線を優先した設計思想を貫いたことで、従来のIT業界にない革新的な製品を次々と生み出しました。
こうした姿勢は一見「組織の和を乱す存在」として非難されかねませんが、その裏には明確なビジョンと倫理観があり、結果として企業価値を大きく引き上げました。
ハーバード・ビジネス・スクールの研究によれば、「企業内で建設的なルール逸脱(Constructive Rule-Breaking)が容認されている組織は、年平均で19%高いイノベーション成果を上げている」というデータもあります(2018年)。
このように、ルール逸脱者を「変化の先導者」として活かすマネジメントの視点は、現代の不確実な時代において極めて重要です。
4. 共存を可能にする「透明性」と「再設計」の仕組み
ルールを守らない人と建設的に共存するためには、「あいまいなルール」や「現場と乖離したルール」を定期的に見直し、透明性のあるプロセスで再設計していく必要があります。
ルールが固定化し、例外的な行動を許容しない文化が根づくと、組織は次第に硬直化し、変化への耐性を失っていきます。
大手電機メーカー・パナソニックでは、社員からの「ルールへの違和感」を匿名で提出できる仕組みを導入し、そのフィードバックをもとに社内ルールの一部を見直すという「現場フィードバック型ガバナンス体制」を構築しています。
この制度導入後、社員満足度が17%向上し、ルール違反の指摘件数も実質的に12%減少したと報告されています(2022年社内調査)。
これは、単なる監視強化ではなく、「ルールの再定義プロセスへの参加」を促すことで、ルールが組織全体の“自分ごと”になっていく好例です。
ルール違反者を「変化の触媒」として捉える
ルールを守らない人を「排除すべき問題」として扱うのではなく、「対話すべき存在」「成長のきっかけ」として捉える視点を持つことが、組織の成熟と持続的成長の鍵になります。
もちろん、すべてのルール違反を許容するわけにはいきませんが、少なくともその背景にある「意見」や「視点」を聞く姿勢を持つことは、組織の硬直を防ぎ、多様性を力に変える出発点になります。
共存とは、妥協ではなく“対話と共創”による選択です。ルールを守らない人の背後には、時にルールそのものを問い直す重要なサインが隠れています。
それを見逃さず、建設的に拾い上げ、組織全体の価値観や仕組みの再構築につなげていく。そのプロセスこそが、組織の真の「柔軟性」と「強さ」を形づくるのです。
▼以下の記事もお薦めです。
「なぜあの人はルールを守らないのだろう?」と悩んだ経験はありませんか?
「どうしてあの人はルールを守らないの?」──そんな疑問やストレスを抱えたことはありませんか?
相手の行動に振り回されると、自分の心が疲れてしまいますよね。そんなときに役立つのが、心理学や人間関係の知識を学べる書籍やサービスです。
📕 『嫌われる勇気』
他人の評価や行動にとらわれず、自分の軸を持つ大切さを教えてくれるベストセラー。
👉 Amazonでチェックする
📕 『反応しない練習』
イライラや不安を減らし、冷静な対応を可能にする「心のトレーニング本」。
👉 Amazonで詳細を見る
📕 『境界線(バウンダリー)の教科書』
「ルールを守らない人」に振り回されないための実践的アドバイスが満載。
👉 Amazonで購入はこちら
🌿 無印良品 アロマディフューザー
リラックス効果のあるアロマで、日々のストレスを和らげるのに最適。
👉 Amazonの商品ページを見る
🎧 Audible(オーディブル)
心理学や自己啓発書を耳で聴けるサービス。通勤や家事の合間に学べます。
👉 Audibleの無料体験はこちら
知識を身につけ、心を整えるアイテムを取り入れることで、ルールを守らない人に出会っても、必要以上に疲れずに付き合うことができます。まずは自分の心を守る準備を始めてみませんか?
★この記事について:質問と答え
Q1:ルールを守らない人にはどんな特徴がありますか?
A1:
ルールを守らない人の特徴には、「自己中心的な思考」「衝動的な行動傾向」「他者への共感の欠如」などが挙げられます。また、ADHDなどの注意欠如や、環境による影響(家庭環境・職場の風土)も関係することがあります。全員が悪意を持って違反しているわけではなく、「ルールの意味を理解していない」「そもそもルールを知らない」といったケースも多いです。
Q2:なぜルールを守らない人が生まれるのですか?
A2:
原因は一つではありませんが、大きく分けると①家庭や教育でのしつけ不足、②周囲のルール意識の低さ、③個人の性格傾向、④精神的・発達的な特性が関与します。特に日本では、「同調圧力に敏感な人」がルールを守る傾向にありますが、それに馴染めない人が反発して逸脱行動を取ることもあります。ルール違反には背景があり、ただの「非常識」と片付けるのは早計です。
Q3:ルールを守らない人にどう対処すればよいですか?
A3:
感情的に怒るよりも、「なぜそれが必要か」を論理的かつ冷静に伝えることが効果的です。また、本人の特性を理解し、場合によってはルールを柔軟に運用する工夫も必要です。職場では、ルールの明文化や共通認識の確認、継続的なフィードバックが有効です。重要なのは、「守らせること」より「納得して自発的に守れる環境」を整えることです。
▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。







