最近、SNSでふと目にした企業アカウントの投稿に、思わず笑ってしまったことはありませんか?あるいは、商品について問い合わせたときに、想像以上に丁寧で温かい対応を受けて「この会社、好きかも」と感じた経験はないでしょうか。
いま、多くの人が気づき始めています。単に製品の質が良いとか、価格が安いというだけでは、企業への信頼や愛着は生まれにくい。むしろ、「このブランド、まるで人みたいだな」と感じられる企業こそ、支持される時代になってきたのです。
たとえば、ユーモアのある返答、顧客の気持ちに寄り添う言葉づかい、ちょっとしたエピソードのシェア。こうした「人間らしい発信」が、顧客との距離を一気に縮めてくれることがあります。
しかし、多くの企業はまだそこに踏み出せていません。マニュアル通りの無機質な対応、画一的な発信ばかりが続き、「この会社って、結局ただの“法人”なんだな」と思われてしまっていないでしょうか?
どれだけ優れた商品をつくっても、顧客に「無関心な企業」という印象を与えてしまえば、ファンは増えません。では、どうすれば企業は“人格”を持った存在として見てもらえるようになるのでしょうか?そして、そこにどんな価値があるのでしょうか?
今回は、「ブランドパーソナリティ」という視点から、企業が“人のように愛される存在”になるための方法と、その実例を深掘りしていきます。あなたのビジネスにも活かせるヒントが、きっとあるはずです。
ブランドパーソナリティとは何か──企業を「人」に変えるマーケティングの中核概念

ブランドパーソナリティとは、企業や商品ブランドがまるで「人間のような性格」や「個性」を持っているかのように感じられる要素のことを指します。これは単なる広告やロゴ、色使いといった表層的なデザインを超えて、顧客がそのブランドに対してどのような「感情」や「印象」を抱くか、という心理的側面に深く関わるものです。
たとえば、あるコーヒーブランドに対して「都会的で洗練されている」と感じる顧客もいれば、別のブランドに対して「家庭的で温かい」と感じる人もいます。これがまさにブランドパーソナリティの働きであり、人間関係と同じように、「相性が合う」「信頼できる」といった感情的な選好がブランド選択の背景に存在しています。
「ブランドを人格として捉える」ことで生まれるメリット
なぜ企業はブランドパーソナリティを重視するようになったのでしょうか。その理由は、今日の消費者行動が機能的な価値だけではなく、感情的な価値に大きく影響を受けるようになってきたためです。
かつては「安い・早い・便利」といった機能的価値が重視されていましたが、現代の顧客は「そのブランドがどんな価値観を持ち、どう振る舞っているか」といった情緒的な要素をもとに、ブランドを選ぶ傾向が強まっています。特にSNSの普及によって企業と消費者の距離が近くなり、「この企業は信頼できるのか?」「自分の価値観と合うか?」といった視点で企業を見られるようになりました。
この点でブランドパーソナリティは、顧客との信頼関係を築き、長期的なブランドロイヤルティを獲得する上で、不可欠な戦略資源となっています。
ブランドパーソナリティの5つの基本軸:Aakerモデル
学術的にもブランドパーソナリティは体系化されています。マーケティング心理学者ジェニファー・アーカー(Jennifer Aaker)が1997年に提唱した「ブランドパーソナリティ5次元モデル(Big Five)」は、その代表的な枠組みです。このモデルでは、ブランドの個性を以下の5つの特性に分類しています。
- 誠実さ(Sincerity):親しみやすさ、正直さ、温かみ(例:コカ・コーラ、ディズニー)
- 興奮(Excitement):大胆さ、想像力、現代的(例:Red Bull、ナイキ)
- 有能さ(Competence):信頼性、知性、成功(例:IBM、トヨタ)
- 洗練(Sophistication):上品さ、魅力、高級感(例:シャネル、レクサス)
- 頑健さ(Ruggedness):頑丈さ、冒険心、アウトドア的(例:ジープ、パタゴニア)
これらの特性をもとに、自社ブランドがどのような人格を持つかを明確にすることで、ターゲットとなる顧客層との結びつきが強化されます。ブランドに一貫した人格があることで、顧客の記憶にも残りやすくなり、ブランド選好の形成につながるのです。
なぜパーソナリティは顧客の「選ぶ理由」になるのか?
人は商品を買うとき、必ずしも論理的・合理的に選んでいるわけではありません。消費者心理の調査によれば、約60〜70%の購買決定は「感情」によって左右されているとされています(Harvard Business Review, 2015年)。
たとえば、機能や価格がほぼ同等のA社とB社の製品があった場合、消費者はどちらに「好感」や「信頼」あるいは「共感」を感じるかで選ぶ傾向があります。つまり、ブランドに「人間的な魅力」が感じられるかどうかが、最終的な意思決定を左右するということです。
実際、米国の調査会社Salsifyが行った2022年のブランド調査によると、「ブランドの価値観やストーリーに共感できるかどうか」は、Z世代の購買において72%が「非常に重要」と回答しており、ブランドパーソナリティの設計が売上に直結することを裏付けています。
企業事例:パーソナリティが急成長を後押ししたブランド
ブランドパーソナリティの構築が成功した代表的な事例として、以下の企業が挙げられます。
1. ダブ(Dove):「ありのままの美しさ」を訴求する誠実なブランド
ユニリーバの化粧品ブランド「Dove」は、「リアルビューティーキャンペーン」で知られ、誠実さと共感を軸にブランドを構築しています。加工されていない一般女性を広告に起用し、ボディポジティブを強調することで、既存の美容広告へのアンチテーゼを打ち出しました。
結果として、Doveは広告キャンペーンを開始した2004年からの10年間で、世界売上が2倍以上に拡大。顧客の心に訴える「人格」がいかにブランドの成長に寄与するかを示す好例です。
2. Netflix:「親しみやすく、かつユーモラスな賢者」
NetflixのSNS運用は、ブランドパーソナリティ戦略の最前線とも言われています。公式アカウントでは、視聴者とのカジュアルなやり取りや、時事ネタを絡めたユーモラスな投稿が人気です。顧客と対等な立場で会話をする「親しみやすい賢者」としてのポジションを築き、フォロワー数の増加やブランドエンゲージメントの向上に大きく貢献しています。
Netflixは、SNS上のユーモラスな対応でしばしばバズを生み出し、Twitter(現X)では1000万以上のフォロワーを獲得しています。これは、エンタメ業界の中でも極めて高い水準です。
ブランドパーソナリティは「記憶」と「選択」の起点になる
ブランドパーソナリティの本質は、「人間が人間を好きになる心理」と同じ構造にあります。人が誰かに惹かれるのは、その人の性格、価値観、表現方法、そして一貫性にあるように、ブランドに対しても「このブランド、好きだな」と感じさせる“人間味”があるかどうかがカギになります。
そして一度好かれたブランドは、他の選択肢があっても記憶の中で優先順位が高くなり、指名買いされるようになります。これこそが、数ある競合の中で「選ばれるブランド」になるための最大の武器なのです。
このように、ブランドパーソナリティは単なる「印象操作」や「デザイン演出」ではなく、顧客との感情的な接点を深め、記憶と信頼を構築するための本質的な概念です。企業はこの「人格」を丁寧に育て、あらゆるブランドコミュニケーションにおいて一貫して表現することで、顧客との強固な関係を築くことができるのです。
ブランドパーソナリティの成功事例

ブランドパーソナリティを効果的に活用している企業の事例を紹介します。
Nike – 挑戦を促す革新的なブランド
Nikeは「Just Do It」というスローガンに象徴される、挑戦的で革新的なブランドパーソナリティを確立しています。トップアスリートとの戦略的なパートナーシップや社会的な課題に挑戦するマーケティングキャンペーンなどを通じて、単なるスポーツ用品メーカーを超えた存在感を示しています。
Apple – 革新と洗練を極めるテクノロジーブランド
Appleは製品デザインから販売方法まで、一貫して洗練された世界観を表現しています。ミニマリスティックで優美な製品デザインや直営店での統一された高品質な顧客体験などにより、テクノロジー製品の高級ブランドとしての地位を築いています。
Starbucks – コミュニティに根ざしたコーヒーブランド
Starbucksは、高品質なコーヒーの提供と社会的責任を組み合わせたユニークなブランドパーソナリティを構築しています。バリスタの専門教育やサードプレイスとしての店舗環境づくりなどを通じて、コミュニティの中心としての存在感を確立しています。
Patagonia – 環境保護を実践するアウトドアブランド
Patagoniaは、環境保護への強いコミットメントと高品質な製品開発を通じて、独自のブランドパーソナリティを確立しています。環境保護活動への1%寄付プログラムや製品の修理サービスなどにより、持続可能なビジネスのロールモデルとして評価されています。
ブランドパーソナリティの構築方法──顧客の心に残る「人格」をつくる実践的アプローチ

ブランドパーソナリティを実際に企業がどのように構築していくのか。それは単なる「印象操作」ではなく、綿密な戦略と一貫した行動を通じて、「このブランドは信頼できる」「自分に合っている」と感じてもらうプロセスです。言い換えれば、ブランドの内面を形づくり、それを顧客とのあらゆる接点において「人格として表現する」ことこそが、成功するブランドの鍵なのです。
ステップ1:ブランドの核となる「価値観」と「信念」の明確化
ブランドパーソナリティの構築は、まず「そのブランドが何を信じ、何のために存在しているのか」を明確にすることから始まります。これはいわば「人間で言えば信条や性格の根本」にあたる部分です。
たとえば、アウトドア用品ブランドのパタゴニアは「環境保護」が中心的な価値観です。この理念は製品選定、素材選び、広告キャンペーン、企業の社会的活動すべてに一貫して表現されています。こうした明確な価値観があることで、ブランドは単なる製品の集合ではなく、「人格ある存在」として認識されやすくなります。
統計データ: 調査会社Sprout Socialの報告によると、消費者の64%は「自分の価値観に近いブランド」に対してロイヤルティを感じると回答しています。ブランドの信念が明確であればあるほど、共感による関係構築が強まるのです。
ステップ2:ターゲット顧客の「理想の人格像」を理解する
ブランドが一方的に性格を設定するだけでは、顧客との共鳴は生まれません。ブランドパーソナリティは、常に「ターゲット顧客にとって魅力的な人格」でなければ意味を持たないのです。
そのためには、ターゲットとなる顧客の価値観、ライフスタイル、抱えている問題、理想とする人間像を調査・理解する必要があります。たとえば、若年層向けのファッションブランドであれば、「自由さ」や「個性の尊重」がキーワードになるかもしれません。一方、ビジネスパーソン向けの金融ブランドでは、「信頼性」や「安定感」が好まれるでしょう。
実例: スターバックスは、都市部の若者やプロフェッショナル層をターゲットに、「洗練された」「落ち着きのある」「自分の時間を大切にする」という人格を構築し、それに即した空間設計、接客スタイル、商品ラインを展開しています。
ステップ3:言葉、デザイン、行動に人格を「宿す」
ブランドパーソナリティは、「口で言って終わり」ではなく、それが企業のあらゆる行動に反映されてこそ、初めて真の意味を持ちます。ここで鍵になるのが「トーン&マナー(Tone & Manner)」の一貫性です。
- 言葉づかい:公式サイトやSNSでの文章、商品説明、広告キャッチコピーなど、言語表現すべてにその人格を反映させます。たとえば、Z世代向けのブランドであれば、カジュアルで親しみやすい口調が合致します。
- ビジュアル:ロゴやカラーパレット、パッケージデザイン、WebサイトのUI/UXなど、視覚要素にも人格を表現します。
- 行動や対応:顧客対応、SNSでのリプライ、クレーム対応にも人格が現れます。ユーモアを重視する人格なら、少し冗談を交えた反応を返すことが許容されます。
調査データ: 米国のマーケティング企業Lucidpressの調査では、ブランド表現に一貫性がある企業は、売上を平均で23%増加させているという結果が出ています。一貫したパーソナリティ表現が、売上面でも効果を持つことが示唆されています。
ステップ4:社員の「言動」として具現化する
企業にとって最大の「パーソナリティ体現者」は社員です。とくに顧客と接するカスタマーサポートや販売員は、ブランドの「顔」として、人格を直接表現する存在です。
たとえば、ディズニーランドのキャストたちは、ブランドの人格である「夢・魔法・おもてなし」を身につけるために、徹底した研修を受けています。彼らの行動すべてがブランドの一部であり、世界中の人が「ディズニーってこういう人だよね」と思い描けるほどに、人格が組織全体に浸透しているのです。
数値の裏付け: Gallup社の調査によれば、ブランドパーソナリティが社内文化に浸透している企業は、そうでない企業に比べて顧客満足度が20%以上高いという結果が出ています。つまり、社員の「ブランドらしさ」が、顧客の印象形成に直結しているということです。
ステップ5:SNSと顧客接点で「人格」を日々実践する
現代におけるブランドパーソナリティの実践の場は、SNSやチャットなどの「日常的な接点」に集約されています。ここで企業は、広告のような一方的発信ではなく、顧客との「対話」を通じて、人格を体現する必要があります。
たとえば、ある飲料メーカーはTwitterでの顧客からの質問に、丁寧かつユーモラスな返答を続けた結果、フォロワーが半年で2倍以上に急増しました。これは、その企業の「親しみやすさ」「人懐っこさ」が、日々のやり取りを通じて自然に伝わった好例です。
実績データ: HubSpotのレポートによると、SNS上でのブランド対応に「人間味がある」と感じた顧客のうち、78%が「再購入の意欲が高まった」と回答しています。つまり、「人間のような対応」が、継続的な関係性を生む強力な要因になっているのです。
ブランドパーソナリティは、表面的なデザインや言葉遣いだけで成立するものではなく、企業の内面から生まれ、それが言葉、行動、ビジュアル、社員の振る舞い、顧客対応のすべてに貫かれている必要があります。
これを実現するには、経営陣から現場までが「ブランドは人である」という考え方を共有し、顧客との対話の一つひとつに人格を宿らせる覚悟と仕組みが求められます。パーソナリティは設計するものではなく、日々のふるまいの積み重ねで生きた「人格」になっていくものなのです。
顧客との感情的なつながりを生み出す──ブランドパーソナリティがもたらす心理的な絆

ブランドパーソナリティが確立されたとき、企業は単なる「商品提供者」ではなく、顧客にとっての「共感できる存在」となります。そのときに生まれるのが、単なる購買行動を超えた“感情的なつながり”です。これは、現代の顧客がブランドに求めている最も本質的な価値のひとつです。人は理屈だけで動くのではなく、感情によって意思決定をしているからです。
感情が購買行動を決定づけるメカニズム
ブランドと顧客との関係を強くするうえで、最も注目すべきは「感情の働き」です。神経科学の分野においては、人間の購買判断の約90%は感情によってなされているとされています(Harvard教授Gerald Zaltmanの研究より)。つまり、「理屈で選ぶ」のではなく、「なんとなく好きだから」「このブランドに共感できるから」という気持ちが購買の背後にあるのです。
この感情の基盤には、「信頼」「共感」「好意」「憧れ」といった心理的要素が含まれます。そして、それらを喚起させるのが、まさにブランドパーソナリティの役割なのです。
たとえば、Appleは「革新」「クリエイティビティ」「洗練」という人格を構築しています。この価値観に共鳴する人々は、スペックや価格ではなく「Appleらしさ」に惹かれて製品を選びます。Appleユーザーが感じるロイヤルティは、まさにブランドとの感情的なつながりの結果です。
感情的なつながりがもたらす効果
このような感情的な結びつきは、企業にとって多くのプラスをもたらします。以下のデータは、それを裏づけています。
- 感情的にブランドとつながっている顧客は、そうでない顧客に比べて306%高い生涯価値(LTV)をもたらす(Motista社の調査)
- 感情的なロイヤルティを感じている顧客の71%は、ブランドに対して批判的な状況でも擁護する姿勢を見せる(Edelman調査)
- 感情的つながりを持つ顧客は、平均的な顧客よりもブランドに対する支出額が2倍以上になる傾向がある(HBR調査)
これらの統計が示すように、「好き」「共感できる」と感じるブランドは、価格や機能を超えて選ばれる存在になります。つまり、感情的なつながりは、顧客の維持・拡大において最も強力な資産となるのです。
感情を動かすコミュニケーションのポイント
ブランドが顧客の感情に訴えかけるためには、コミュニケーションにも工夫が必要です。以下の3つのポイントが特に重要です。
- ストーリーテリングの活用
ブランドの理念や創業者の思い、困難を乗り越えてきた背景など、人間味あふれるストーリーは感情に強く訴えます。特にSNSでは、短くてもエモーショナルな物語が共感を呼び、拡散されやすくなります。 - ビジュアルの力を最大限に生かす
色、写真、イラストなど視覚要素は、言葉以上に直感的な感情を喚起します。たとえば、柔らかいトーンの色合いは安心感を、ビビッドな色は情熱や刺激を想起させるなど、視覚表現には強力な心理効果があります。 - 顧客一人ひとりを「個人」として扱う
定型文ではなく、その人の状況や感情に寄り添った対応をすることで、「このブランドは自分を理解してくれている」と感じさせることができます。これが、感情的な信頼感へと直結します。
共感を呼ぶブランドの実例
【例1:Netflix】
NetflixはSNSでの応答において、視聴者の趣味や感情を的確に汲み取るコミュニケーションが話題となっています。フォロワーに対してフレンドリーな言葉づかいや、共通のカルチャーを用いたジョークでつながることで、「ブランドとの会話が楽しい」という印象を確立しています。
【例2:無印良品】
「気取らず、自然体で、使いやすい」というブランドパーソナリティを持つ無印良品は、プロダクトデザインから広告表現、SNS対応まで一貫したスタンスを貫いています。顧客はその「素朴で誠実な人格」に感情的な信頼を寄せ、長年にわたって支持し続けているのです。
ブランドパーソナリティが感情的なつながりを生むという考え方は、マーケティングだけでなく、心理学や行動経済学の視点からも裏づけられています。そして、顧客との間に築かれる絆は、売上やリピート率といった数字以上の価値を企業にもたらします。それは、まさに「選ばれる理由」そのものであり、ブランドの長期的な成功の根幹なのです。
まとめ:人格を持つブランドが選ばれる時代へ

現代の消費者は、製品のスペックや価格といった表面的な要素だけでなく、その企業やブランドが「どんな人間であるか」を重視するようになっています。ブランドパーソナリティの重要性が増しているのは、まさにこの変化の中で顧客との感情的なつながりが、選ばれる理由となっているからです。
「企業の人格化」は一過性のマーケティングトレンドではありません。信頼、共感、関係性という、極めて人間的な感情に根ざした本質的なアプローチです。ブランドパーソナリティを通じて、企業が「人間らしさ」を持ち、感情のある存在として顧客と向き合う時、そこに新たな価値と競争力が生まれます。
あなたの企業に問いかけてみてください。
「私たちのブランドは、どんな人間ですか?」
この問いに真摯に向き合い、ブランドパーソナリティを育てることが、これからの時代に必要不可欠な戦略となるでしょう。顧客の心を動かし、深く結びつくブランドへ──その第一歩は、人格を持つブランドを築くことから始まります。
▼今回の記事を作成するにあたり、株式会社マイビジョン様の記事を参考にしました。
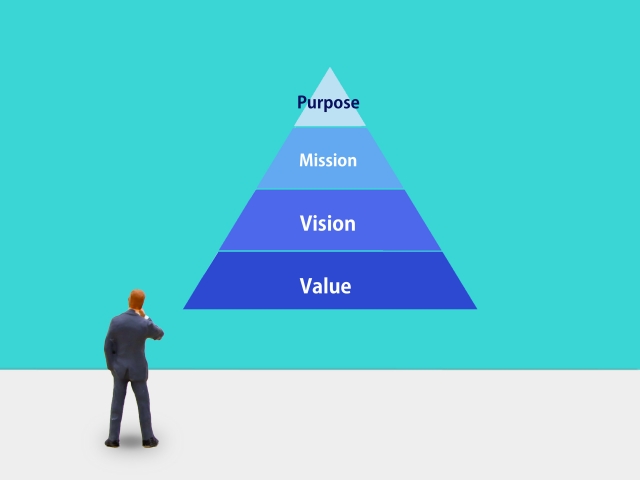
▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。




