「健康のために適度な運動をしましょう。」──
テレビでも雑誌でも、医療機関の案内でも、私たちは何度となくこの言葉に触れます。しかし、ふと立ち止まって考えてみたとき、「適度な運動って、具体的にどのくらい?」と疑問に感じたことはないでしょうか。
1日30分のウォーキングで十分なのか、週に何回ジムに通えば良いのか、それとも毎日10,000歩歩くべきなのか。情報が多すぎて、かえって正解が見えにくい──
そんな感覚を覚えている人も多いはずです。
さらに、SNSでは「朝5時からランニング」「週6で筋トレ」など、ストイックなライフスタイルが称賛されがちです。
一方で、忙しい毎日の中で時間を作って運動をするのが難しいと感じている人も少なくないでしょう。「運動した方がいい」とは分かっていても、現実的には続けられない。
その結果、運動不足の自覚はあるけれど、何から始めたらいいのか分からないまま、気づけば月日が経っている──
そんな経験、ありませんか?
このように、「適度な運動」の基準が人によって異なりすぎることが、私たちの“行動のきっかけ”を曖昧にしてしまっているのです。
では、本来の人間の体が求める“自然な運動量”とは、一体どれくらいなのでしょうか?
そのヒントは、実は私たちの祖先──
狩猟採集民の生活にあります。彼らが日々どれほど体を動かし、どんなエネルギー消費バランスの中で健康を維持していたのかを知ることは、私たち現代人が「無理せず健康でいられる運動習慣」を見つけるための大きなヒントになるはずです。
狩猟採集民の生活から学ぶ「適度な運動」の基準

現代における「適度な運動」とはどのくらいの運動量を指すのでしょうか。その参考として、狩猟採集民の生活が重要です。人間の体は長い進化の過程で、狩猟採集時代のライフスタイルに適応してきました。彼らの運動量を分析することで、人が本来必要とする活動レベルのヒントが得られると考えました。
狩猟採集民の一日の運動量
狩猟採集民は、毎日どれほどの運動をしていたのでしょうか。2016年の研究によれば、タンザニアに住むハッザ族の男性は平均して1日18,000歩、女性は14,000歩を歩いていたそうです。この数値は、現代で推奨される1日10,000歩を大きく上回ります。
また、彼らは歩くだけでなく、食料を得るために狩猟や採集を行い、以下のような運動をしていました:
- 短時間の全力疾走(獲物を追うときや危険から逃げるとき)
- 長時間の歩行(採集や移動時)
- 中程度の強度の筋力活動(木登りや動物の解体など)
これは、現代の運動プログラムで推奨される「有酸素運動と筋トレの組み合わせ」に似ています。
さらに、彼らの1日の総エネルギー消費量は、現代人とほぼ同じ2,500〜3,000kcal程度と報告されています。驚くべきことに、現代の平均的なオフィスワーカーの歩数は4,000〜5,000歩程度でありながら、同じくらいのエネルギーを消費しているのです。
このカロリー消費の仕組みには「制限されたエネルギー消費モデル」が関係しています。これは、体が一定のエネルギー消費範囲内で適応し、過剰なエネルギー消費を抑える仕組みです。つまり、運動量が増えても全体のエネルギー消費量が単純に増えるわけではないのです。
狩猟採集民の運動が健康に与える影響
狩猟採集民の運動習慣は、現代人の健康維持にとって重要な示唆を与えています。彼らのライフスタイルには、現代の生活習慣病を防ぐ要素が多く含まれています。
- 心血管系の健康を維持する
狩猟採集民は心臓や血管の健康を保つための運動量が理想的で、高血圧や動脈硬化といった現代病がほとんど見られないとされています。 - 糖尿病のリスクを低下させる
運動不足の現代人は2型糖尿病のリスクが高まりますが、狩猟採集民は常に体を動かしているため、血糖値の管理が自然とできています。 - 筋肉量の維持と老化の抑制
彼らの運動には筋力トレーニングに相当する要素があり、高齢になっても筋肉量が維持されやすいとされています。
現代人が取り入れるべき「適度な運動」
狩猟採集民の運動習慣を参考にすると、取り入れるべき「適度な運動」の基準が見えてきます。それは以下の通りです:
- 1日14,000歩以上を目指す(坂道や不整地を歩くことで負荷を高める)
- 週に150〜300分の中強度運動を行う(例:早歩き、軽いランニング)
- 筋力トレーニングを組み合わせる(スクワットやデッドリフトなど)
- 短時間の高強度運動を取り入れる(スプリントやジャンプなど)
このような運動習慣を意識することで、狩猟採集民の健康的な体の仕組みを現代に取り入れることができます。
「運動しすぎ」に注意するポイント
ただし、注意が必要です。狩猟採集民は自然に「適度な運動」を行っていましたが、現代人が急に激しい運動を始めると健康を害するリスクがあります。その場合には、以下のような問題が挙げられます:
- 長時間のランニングによる関節への負担(特に膝や足首)
- 過度な筋トレによるホルモンバランスの乱れ
- 持続的な高強度運動による免疫力の低下
したがって、運動は「やりすぎず」「継続できる範囲で」行うことが重要です。
目指すべき運動習慣とは
狩猟採集民の運動量を現代のライフスタイルに適応させるならば、理想的なのは「日常的に体を動かし、無理なく持続できる運動をすること」です。彼らはジムでトレーニングをするわけではなく、自然に体を動かす習慣がありました。これを応用し、以下のような工夫をすることで健康的な体づくりが可能になります:
- 歩行を意識的に増やす(階段を使う、遠回りする)
- 買い物や家事を運動として活用する
- アウトドア活動を取り入れる(登山やキャンプなど)
このように、日常生活の中で運動を取り入れることで、狩猟採集民のような健康的な生活を実現できるでしょう。
現代人の運動不足が引き起こす老化や病気のリスク

現代社会では、デスクワークの増加や便利な移動手段の発達により、運動量が少ない生活を送っています。昔の狩猟採集民のように日常的に体を動かしていた時代と比べると、現代人の活動量は低くなっています。その結果、肥満や糖尿病、心血管疾患、筋力低下、認知機能の低下など、老化を早めるさまざまな問題が起きています。
1. 運動不足がもたらす老化の加速:細胞レベルでの変化
運動不足は単に体力を低下させるだけでなく、細胞レベルで老化を加速させることがわかっています。その一つの要因が「テロメアの短縮」です。
テロメアの短縮と老化
テロメアとは、細胞の染色体の末端にある構造で、細胞が分裂するたびに少しずつ短くなります。テロメアが極端に短くなると、細胞は分裂できなくなり、老化や病気のリスクが高まります。運動はこのテロメアの短縮を抑える効果があります。
2017年の研究によると、定期的に運動を行う人は運動不足の人に比べて、テロメアが平均9歳分長いことが示されました。実際に、週に150分以上の中強度運動(ウォーキングや軽いランニングなど)を行う人のテロメアは、運動不足の人と比べて明らかに長かったです。これは、運動が細胞レベルで老化を遅らせることを示す強力な証拠です。
ミトコンドリア機能の低下
ミトコンドリアは、細胞のエネルギーを作る「工場」のような役割を果たしています。しかし、加齢とともにこの機能が低下し、エネルギー生産が減少します。これにより、疲れやすくなったり、筋力が低下したりします。
運動はミトコンドリアの新生を助け、エネルギー生産能力を維持します。特に、高強度インターバルトレーニング(HIIT)のような短時間の強い運動は、ミトコンドリアの数を増やし、その機能を向上させることがわかっています。ある研究では、週に3回のHIITを行うことで、ミトコンドリア機能が最大69%向上したと報告されています。
2. 運動不足が引き起こす病気のリスク
現代人の運動不足は、さまざまな慢性疾患の発症リスクを高めます。
心血管疾患と高血圧
運動不足は心血管疾患のリスク要因です。世界保健機関(WHO)の報告によると、運動不足は年間500万人以上の死亡原因となっています。特に高血圧のリスクが高まりますが、定期的な運動を行うことで血圧が5〜10mmHg低下することが示されています。これは、高血圧治療薬と同じくらいの効果です。
また、運動不足は悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を増やし、動脈硬化を進めますが、適度な運動は善玉コレステロール(HDLコレステロール)を増やし、血管の健康を保ちます。
2型糖尿病のリスク増加
運動不足によりインスリンの働きが悪くなると、血糖値が上昇し、2型糖尿病のリスクが高まります。研究によると、週に150分以上の運動を行うことで、糖尿病の発症リスクが約58%低下することが分かっています。これは、運動が血糖値の管理に重要な役割を果たしていることを示しています。
運動をすることで、筋肉がブドウ糖を取り込みやすくなり、インスリンの働きが改善されます。この効果は運動後最大48時間持続するとされており、定期的な運動が血糖値の安定に寄与します。
3. 運動不足が認知機能に及ぼす影響
運動不足は脳の老化を早める要因でもあります。
脳の萎縮と認知症のリスク
運動不足の人は、記憶を司る海馬という脳の部分が縮小しやすく、認知症のリスクが高まることがわかっています。2011年の研究では、週3回の有酸素運動を1年間続けた人の海馬の体積が2%増加したという結果が報告されました。これは、運動が脳の萎縮を防ぎ、認知機能を維持するのに効果的であることを示しています。
さらに、運動によって脳由来神経栄養因子(BDNF)という物質の分泌が促進され、脳細胞の成長や修復が活発になります。
4. 現代人が運動を取り入れるための実践方法
運動不足のリスクを避けるためには、日常生活の中で無理なく運動を取り入れることが大切です。以下の方法が有効です:
- 1日8,000〜10,000歩を目標にする(歩数が多いほど死亡リスクが低下することが研究で示されています)
- 週に150〜300分の有酸素運動を行う(ウォーキング、ジョギング、水泳など)
- 週2〜3回の筋力トレーニングを取り入れる(スクワットや腕立て伏せなど)
- HIITを週に1〜2回行う(短時間で効率的にミトコンドリア機能を向上)
運動は老化を遅らせ、病気を予防し、健康寿命を延ばすために不可欠です。現代のライフスタイルに合った運動習慣を身につけることで、老化の進行を抑え、健康的な体を維持できるでしょう。
運動のしすぎが引き起こすホルモンバランスの乱れと老化

適度な運動が健康に良いことは広く知られていますが、過度に運動をすることが逆に健康に悪影響を及ぼすことがあります。特に、運動をしすぎることでホルモンバランスが乱れ、老化を加速させることが科学的に証明されています。
1. 過剰な運動がホルモンバランスを崩すメカニズム
ホルモンは体内のさまざまな機能を調節する重要な役割を果たしていますが、運動が過剰になると、ストレスホルモンの増加や性ホルモンの減少が起こり、健康に悪影響を与えます。
コルチゾールの過剰分泌と老化の加速
コルチゾールは副腎から分泌されるストレスホルモンで、適度に分泌されるとエネルギー供給や免疫機能の調整に役立ちます。しかし、過剰な運動はコルチゾールの慢性的な増加を引き起こし、以下のような問題を引き起こします。
- 筋肉の分解が進み、筋肉量が減少する
- 免疫力が低下し、感染症のリスクが上がる
- 皮膚の老化が進み、シワやたるみの原因となる
研究によると、2時間以上の持久系運動を行った後のコルチゾール濃度は通常時の2〜3倍に達することが確認されています。このような状態が続くと、慢性的なストレス状態となり、老化が加速します。
テストステロンとエストロゲンの低下
テストステロン(男性ホルモン)とエストロゲン(女性ホルモン)は、筋肉の成長や皮膚の健康、骨密度の維持に関与していますが、過剰な運動はこれらのホルモンの分泌を抑制します。その結果、以下のような問題が生じます。
- 筋力が低下し、筋肉の成長が妨げられる
- 骨密度が低下し、骨粗しょう症のリスクが増える
- ホルモンバランスの乱れが不妊症のリスクを高める
過度なトレーニングを行うアスリートを対象とした研究では、運動の強度が高まるほどテストステロンの分泌量が低下することが報告されています。特に、週に10時間以上の高強度運動を行う男性ではテストステロン濃度が平均20%低下し、女性では月経不順の発生率が著しく増加すると確認されています。
2. 過剰な運動が体内の回復機能を妨げる
運動後の疲労回復には成長ホルモンやメラトニンが重要ですが、過剰な運動はこれらのホルモンの分泌にも悪影響を与えます。
成長ホルモンの分泌低下による修復機能の阻害
成長ホルモンは筋肉や骨の修復、脂肪燃焼、肌の再生に関与していますが、過剰な運動によってその分泌が抑制されます。成長ホルモンは通常、睡眠中に多く分泌されますが、過度な運動によるストレスが交感神経を活性化させ、睡眠の質が低下し、ホルモン分泌が妨げられます。
実際、過剰な運動を行うアスリートの中には、慢性的な不眠症や深い睡眠の減少が見られます。また、睡眠の質が低下すると体内の炎症マーカーが増加し、老化や病気のリスクが高まることもわかっています。
メラトニンの分泌低下による老化の促進
メラトニンは睡眠ホルモンとして知られていますが、抗酸化作用を持ち、老化を抑制する働きもあります。しかし、過剰な運動はメラトニンの分泌を抑え、以下のような影響を及ぼします。
- 睡眠の質が低下し、深い睡眠が減少する
- 細胞の酸化ダメージが蓄積し、老化が進む
- 免疫機能が低下し、感染症やアレルギーのリスクが増加する
長時間の過度な運動を行った後は、メラトニンの分泌量が通常の30〜50%減少することが研究で報告されています。
3. 過剰な運動を避け、健康的なホルモンバランスを維持するために
適切な運動量を守ることでホルモンバランスを整え、健康を維持できます。
運動の最適な範囲とは?
- 週に150〜300分の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)
- 週2〜3回の筋力トレーニング(適度な負荷で筋肉を維持)
- 1回の運動時間は60分以内を目安に(過度な長時間運動は避ける)
- 十分な休息と栄養を確保する(運動後のリカバリーを意識する)
また、オーバートレーニング症候群を防ぐために、運動の合間に休息日を設けることも重要です。特に、強度の高い運動を行った後は、最低でも48時間の回復時間を確保することが推奨されています。
総じて、過剰な運動はコルチゾールの過剰分泌や性ホルモンの低下、成長ホルモンやメラトニンの減少を引き起こし、老化や健康リスクを高める要因となります。適度な運動を心がけ、十分な回復を確保することで、健康的なホルモンバランスを維持し、若々しさを保つことができるでしょう。
★この記事について:質問と答え
Q1:適度な運動って具体的にどのくらいの運動量を指すの?
A:
一般的には、週150〜300分の中強度の有酸素運動(例:速歩や軽いジョギング)と、週2回以上の筋力トレーニングが「適度な運動」とされています。参考として、狩猟採集民のハッザ族は1日に約14,000〜18,000歩も歩いており、現代人の平均(約5,000歩)と比べてはるかに活動的です。これを現代に応用するなら、「1日8,000〜10,000歩+週2回の筋トレ」が現実的かつ効果的です。
Q2:狩猟採集民の運動量を参考にすることで、どんなメリットがあるの?
A:
人間の体は進化の過程で狩猟採集民のような生活に最適化されてきたため、彼らの運動パターンに学ぶことは自然で無理のない健康習慣を築くヒントになります。たとえば、彼らは1日あたり2,500〜3,000kcalを消費しながらも、生活習慣病とは無縁でした。心疾患、糖尿病、肥満の発症率が極めて低かったというデータ(Pontzer et al., 2016)は、日常的な中強度の運動が予防医学的に非常に効果的であることを裏付けています。
Q3:運動不足が老化に与える影響ってどのくらい深刻なの?
A:
運動不足は、細胞のテロメア(寿命の指標)の短縮、筋肉量の減少、ミトコンドリア機能の低下などを通じて、老化を加速させます。研究によれば、運動習慣のある人のテロメアは、運動不足の人と比べて平均9歳分長いという結果もあります(Tucker, 2017)。また、定期的な運動をすることで認知機能の低下や骨粗しょう症、生活習慣病のリスクを大幅に抑えることができると報告されています。
▼今回の記事を作成するにあたり、以下のサイト様の記事を参考にしました。
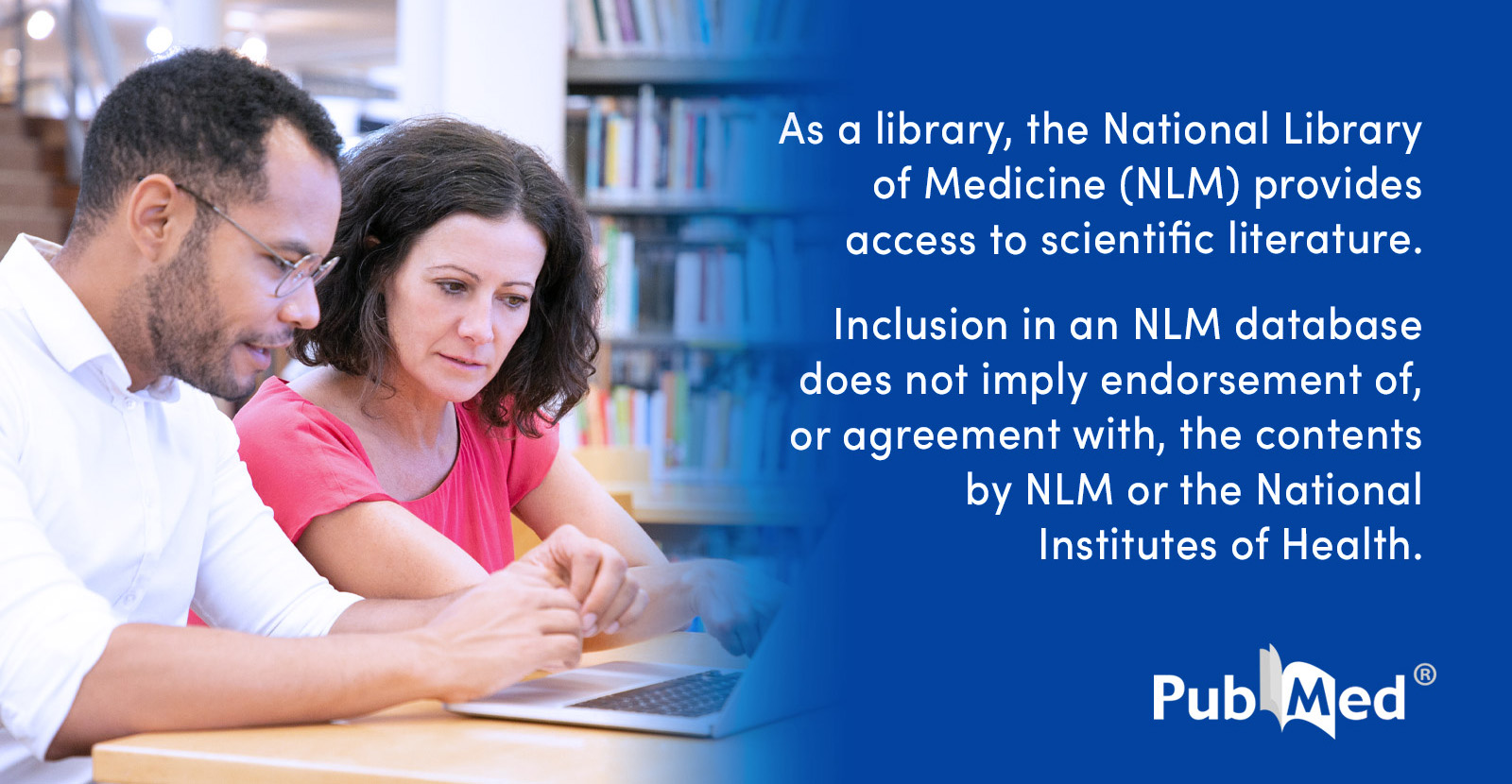
▼また、以下のリンク先の記事もお薦めです。






